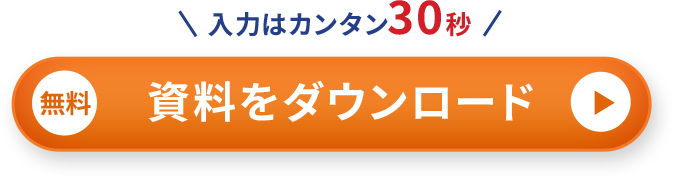総合型選抜は「学力試験だけでは測れない力を評価する入試」として、近年注目を集めています。学力だけでなく、志望理由や将来の目標、課外活動などの取り組みなど、受験生自身の「人となり」や「可能性」を多面的に評価することが大きな特徴です。
しかし、一般選抜との違いは多くの受験生が把握していますが、総合型選抜と旧AO入試、学校推薦型選抜との違いはやや曖昧に捉えられがちで、出願準備の段階で戸惑う受験生も多いと思います。
そこで本記事では、総合型選抜の概要から、流れ、メリット、学校推薦型選抜や一般選抜との比較まで、徹底解説していきます。
大学受験を目指す中高生や保護者の方は、総合型選抜の特徴をしっかり押さえるためのヒントとして、ぜひご活用ください。
総合型選抜とは?AO入試との違い
総合型選抜は、従来の筆記試験の点数だけでなく、受験生の考え方や大学への思い、人物像、将来性などを多面的に評価して合否を決定する入試方法です。
一般選抜が主に学力試験の点数で合否を判断するのに対し、総合型選抜は受験生の個性や意欲、大学・学部との適性(アドミッション・ポリシーとの合致)を重視するのが大きな特徴です。
ここからは、以下の観点から総合型選抜について解説していきます。
- アドミッション・ポリシーとは?
- 総合型選抜の概要
- AO入試との違いとは?
- 選考の仕組み
- 出願期間や試験日程
- 合格率や難易度
アドミッション・ポリシーとは?総合型選抜の評価の基準となる考え方
アドミッション・ポリシーとは、大学が掲げる「入学者受け入れ方針」のことです。「どんな学生に入ってほしいか」「大学でどんな力を伸ばしてほしいか」といった大学の価値観や教育方針を示す指針です。
内容は大学・学部によってさまざまで、例えば「課題を発見し、解決する力」「他者と協働する姿勢」「自ら学びを深める意欲」など、育成したい資質が書かれている場合もあります。また、「地域社会に貢献したい人」「国際的に活躍したい人」のように、将来の方向性や社会的な目標を示す形で表現されることもあります。
さらに、学問分野によっては「英語検定○級以上」「探究活動や資格の取得経験があること」など、具体的なスキルや実績が求められるケースもあります。こうした項目は、大学が「どんな学生と学びたいか」を明確にしている証拠と言えるでしょう。
総合型選抜の概要
総合型選抜は、大学が掲げる「アドミッション・ポリシー」に受験生がどれだけ合致しているかを重視する入試方式です。そのため、受験前に志望大学のアドミッション・ポリシーをしっかり確認し、自分の考えや経験がどのようにマッチするかを整理しておくことが大切です。
選考方法は面接や小論文、プレゼンテーション、グループディスカッション、英語外部検定試験のスコア提出など、大学によってさまざまな評価手法が用いられます。
また、総合型選抜は高校からの推薦書は基本的に不要で、出願条件を満たせば誰でも出願できるところも特筆すべき点です。
総合型選抜では、「なぜこの大学で学びたいのか」「自分の経験や将来の夢をどう実現したいのか」といった点を、自分の言葉でしっかり伝える力が求められます。
AO入試との違いとは?
総合型選抜は、以前は「AO入試」と呼ばれていましたが、2021年度入試から名称が「総合型選抜」に変更されました。
旧AO入試では、学力試験を課さずに人物評価や意欲、適性を重視することもありましたが、総合型選抜ではアドミッション・ポリシーへの合致や人物評価に加え、何らかの形で学力の評価を行うことが原則となっています。
たとえば、評定平均値や資格・検定試験の成績、大学入学共通テストの活用や基礎学力試験など、学力面での基準を設ける大学が増えています。これにより、学力と人物の両面からバランスよく評価する体制へと進化しました。
選考の仕組み
総合型選抜の選考方法や流れは大学ごとに大きく異なります。ここでは、具体的なイメージを持ってもらうために、2つの大学の総合型選抜を例に解説します。
早稲田大学 国際教養学部
・出願時期:9月上旬から出願受付が始まります。
・一次選考(書類審査):Application Formに志望理由や自己PR、国際体験、将来の夢などの記入と、英語外部検定試験スコア(英検®・TOEFL iBT・IELTSなど)の提出が必須です。
・二次選考(筆記審査):「Critical Writing(クリティカル・ライティング)」と呼ばれる120分の筆記試験が課されます。この試験では、与えられた資料を分析した上で、自分の考えを論理的に表現する力が問われます。
東北学院大学
・出願時期:9月の上旬から出願受付が始まります。
・一次選考(書類審査・面接):提出書類の審査に加え、約30分の個人面接が行われます。選考結果は4段階(A、B、C、D)で評価され、A〜C評価の受験者のみが二次選考に進むことができます。なお、学科によっては面接以外の審査を実施する場合もあります。
・二次選考(小論文・書類審査):出願書類の再審査に加え、小論文の試験が課されます。小論文では、与えられた文章の要約と、それに基づいた自分自身の考えを論理的に表現する力が求められます。また、一次選考でC評価となった受験者については、二次選考時に再度面接が行われます。最終的な合否は、一次選考の評価と二次選考の結果を総合的に判断して決定されます。
大学によっては、さらに面接やグループディスカッション、小論文、プレゼンテーション、体験授業などを組み合わせて選考する場合もあります。また、国立大学では共通テストを課すケースも増えており、選考の流れや内容は大学・学部によって様々です。
そのため、自分が志望する大学の公式ホームページで最新の募集要項を必ず確認し、早めに準備を進めることが大切です。
出願期間や試験日程〜合格発表までの流れとスケジュール
総合型選抜の入試は、一般選抜よりも早い時期から動き出します。国立大学協会の実施要項(※)によれば、総合型選抜の出願開始は原則として9月1日以降、合格発表は11月1日以降と定められています。
実際、2025年度入試では多くの国立大学で9月上旬から出願が始まり、書類選考や面接、小論文などの選考を経て、11月上旬以降に合格発表が行われています。
私立大学の場合は、国立大学よりも出願期間や合格発表時期が幅広いと言えるでしょう。多くの私立大学では12月以降も出願を受け付けており、出願期間が12月から翌年2月、合格発表が翌年2月から3月になるケースもあります。
また、私立大学では複数回に分けて選抜を実施することもあり、「総合型選抜第1期」「総合型選抜第2期」といった形で複数回のチャンスが設けられている大学もあります。
年間スケジュールの目安
総合型選抜は大学や学部によって日程が大きく異なりますが、全体の流れを把握しておくと準備がスムーズになります。おおまかな年間スケジュールは次のとおりです。
| 時期 | 主な取り組み内容 |
|---|---|
| 3〜5月 |
・志望校リストアップ ・自己分析の開始 |
| 6〜8月 |
・オープンキャンパス ・エントリー受付開始 |
| 9〜10月 |
・出願 ・書類提出 ・面接・小論文など選考開始 |
| 11〜12月 |
・合格発表 ・入学手続き |
| 翌年1〜3月 | ・一部の私立大学で後期・追加募集実施 |
たとえば、日本大学生産工学部の2025年度総合型選抜は、以下のような日程で実施されました。
| 試験区分 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 10月3日(木)~10月10日(木) | 10月19日(土) | 11月1日(金) |
| 第2期 | 11月25日~12月3日(火) | 12月8日(日) | 12月16日(月) |
準備スケジュールの立て方
総合型選抜は出願までの準備内容(志望理由書・面接対策・活動実績整理など)が多く、「出願直前からの対策」では間に合いません。出願開始の3〜4ヶ月前には自己分析や志望理由書の作成を始め、夏までにオープンキャンパスで大学の方針を確認しておくのが理想です。
また、大学によっては「エントリー期間」「事前面談」「AOエントリーシート提出」などのステップが設けられている場合もあるため、公式サイトで最新情報を早めにチェックすることが重要です。
自己分析の準備について詳しくは下記も参考にしてください。

このように、総合型選抜は大学や学部によって出願期間や試験日程が大きく異なります。出願や試験の準備が間に合わないことを防ぐためにも、早めに情報収集を行い、計画的に入試の準備を進めることが大切です。
※参照:国立大学の2025年度入学者選抜についての実施要領|国立大学協会

総合型選抜の合格率や難易度
総合型選抜は、学力試験中心の一般選抜とは異なり、人物評価や志望理由など多面的に判断される入試です。そのため、合格率が高く見えても「準備不足では合格が難しい」点に注意が必要です。
総合型選抜の合格率は、大学や学部によって大きく異なります。現状では一般的に、総合型選抜は一般選抜よりも倍率が低く合格しやすい傾向があるものの、人気大学や学部では数倍から10倍程度の高倍率となることもあり、決して油断はできません。
総合型選抜と一般選抜の合格率比較
総合型選抜の倍率は大学によって大きな差があり、「準備を着実に進めた受験生が合格を勝ち取る入試」であることがわかります。
以下に、総合型選抜と一般選抜の合格率について表にまとめました。
国立大学(2025年度)の合格率
| 大学名 | 学部 | 総合型選抜合格率 | 一般選抜合格率 |
|---|---|---|---|
| 京都大学 | 総合人間学部 | 約15% | 約30% |
| 大阪大学 | 人間科学部 | 約26% | 約41% |
| 東北大学 | 文学部 | 約28% | 約40% |
| 北海道大学 | 工学部 | 約23% | 約15% |
| 岡山大学 | 農学部 | 約100% | 約42% |
私立大学(2025年度)の合格率
| 大学名 | 学部 | 総合型選抜合格率 | 一般選抜合格率 |
|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 国際教養学部 | 約20% | 約26% |
| 慶應義塾大学 | 法学部 | 約25% | 約24% |
| 中央大学 | 法学部 | 約27% | 約35% |
| 立命館大学 | 理工学部 | 約56% | 約44% |
| 近畿大学 | 情報学部 | 約60% | 約17% |
※ 合格率は、(合格者数)÷(志願者数)で算出
※参照:パスナビ
合格率について詳しくは、下記も参考にしてください。
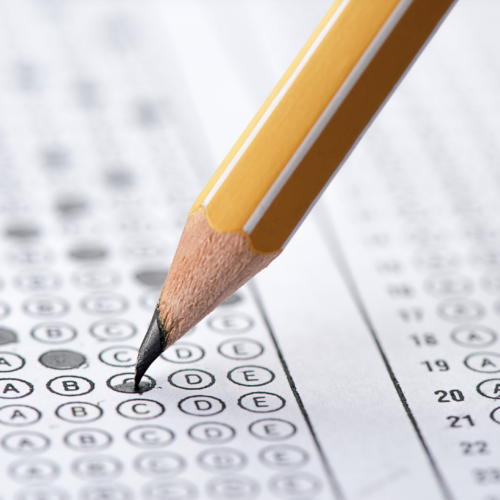
合格に向けた準備ポイント
総合型選抜で合格をつかむためには、次の3つが重要です。
- アドミッション・ポリシーを理解すること
大学が求める人物像を読み取り、自分の経験や目標と結びつけて表現する。 - 自己分析と志望理由の整理
「なぜその大学で学びたいのか」を具体的に言葉にする。 - 早期準備と実践練習
出願直前に仕上げようとせず、夏までに志望理由書や面接対策を始める。
総合型選抜では「受験すれば必ず合格できる」というものではなく、しっかりとした準備と自己分析、志望理由を明確にしておくことが合格の鍵を握ります。
そのため、志望する大学のアドミッション・ポリシーや選考方法をよく調べ、早めの対策を行うことが大切です。
総合型選抜を利用する5つのメリット
総合型選抜には、受験生にとってプラスとなるポイントがたくさんあります。
ここからは、以下の観点から総合型選抜における5つのメリットを解説します。
- 学力以外にも評価軸がある
- 早い時期に合格が決まる
- 高校からの推薦が不要
- 志望校の受験機会が増える
- 一般受験よりも合格率が高い大学もある
学力以外でも評価される
総合型選抜では、リーダーシップや探究心、社会への関心など、学力以外の面も重視されます。これまで部活動やボランティア、学校行事などの課外活動に力を入れてきた人は、その経験や成果をアピールできるところが大きな特徴です。
学力試験だけでは評価されにくい自分の得意分野や個性を活かせるため、学力に自信がない人でも、大学のアドミッション・ポリシーと自分の目標が合致すれば、高いレベルの大学に合格できる可能性が広がります。
また、大学側が重視するのは「どんな活動をしたか」だけではなく、その経験から何を学び、どのように成長したかというプロセスです。
例えば下記のような要素が評価されやすい傾向にあります。
- クラブ活動でチームをまとめた経験(協働力・リーダーシップ)
- 探究活動で課題を見つけ、解決まで取り組んだ経験(課題発見力・実行力)
- 地域活動やボランティアを通して社会と関わった経験(社会貢献意識)
自分の経験を「課題 → 工夫 → 結果 → 学び」の流れで整理し、志望理由書や面接で具体的に語れるようにしておくと効果的です。
早い時期に合格が決まる
総合型選抜の合格発表は、一般選抜よりも早い時期に行われることが多く、私立大であれば秋から初冬、共通テストを課す国公立大を志望する場合でも2月中旬には進路が決まります。これにより、受験のプレッシャーから早く解放され、精神的にとても楽になります。
また、進路が早く決まることで、残りの高校生活を有意義に過ごせるのも大きな魅力です。大学入学までの時間を活用し、大学で学ぶ専門分野の勉強の先取りや資格取得など、自分の将来に向けた準備も余裕を持って進められます。
高校からの推薦が不要
学校推薦型選抜とは異なり、総合型選抜は高校からの推薦状が基本的には必要ありません。
自分の意志で自由に出願できるため、「推薦がもらえないから…」と諦める必要がなく、より多くの受験生にチャンスがあります。出願条件さえ満たせばエントリーできるので、進路の選択肢が大きく広がるのが特徴です。
志望校の受験機会が増える
総合型選抜は、他の入試方式と併願できる場合が多いのも大きなメリットです。
たとえば、総合型選抜で合格した後でも、学校推薦型選抜や一般選抜にチャレンジできる大学もあります。また、総合型選抜で不合格だった場合でも、一般選抜に再挑戦できるため、受験のチャンスを最大限活かすことができます。複数の選択肢があることで、安心して受験に臨めるのが良いポイントです。
一般選抜よりも合格率が高い大学もある
総合型選抜は、大学によっては一般選抜よりも倍率が低く、しっかりと準備すれば高い合格率を狙えるケースもあります。
学力試験だけでなく、面接や小論文、課外活動など多面的に評価されるため、自分の努力が結果に直結しやすいでしょう。自分の強みや経験を丁寧に伝えることで、一般選抜では難しい大学にも合格できるチャンスが広がります。
ただし、特に医学部や上位校では、出願要件が極めて厳しく設定されているケースもあります。たとえば、「国際的な科学コンクールでの入賞実績」などを必須条件とする大学もあるので注意が必要です。
そのため、自分が志望する大学の募集要項を事前に確認しておきましょう。
さらに、総合型選抜で合格率が高くなる背景には、「早期に準備を始める受験生ほど有利になる仕組み」があります。書類や面接対策は一朝一夕では仕上がらないため、夏休みまでに方向性を固めておくことが重要です。
出願条件(評定・資格・検定など)も大学によって異なるため、早めの情報収集が成功への第一歩になります。
学校推薦型選抜や一般選抜との違い
総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜は、それぞれ選抜方法や出願条件、評価基準が大きく異なります。
総合型選抜は、受験生の人物像や意欲、将来のビジョンなどを多面的に評価する方式で、知識や技能だけでなく、思考力・判断力・表現力、学びへの意欲や人間性まで幅広く見られます。
一方、学校推薦型選抜は高校からの推薦が必要で、主に評定平均や課外活動の実績が重視されます。
また、一般選抜では、学力試験の成績が合否の決め手となり、主にペーパーテストの点数で評価されます。
| 選抜方式 | 評価方法 | 推薦状の有無 | 主な試験 | 出願時期 | 合格発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜 | 人物評価・適性など | 不要 | 面接・小論文・プレゼンテーションなど | 9月〜 | 11月〜 |
| 学校推薦型選抜 | 評定平均や課外活動 | 必要 | 面接・小論文 | 11月〜 | 12月〜 |
| 一般選抜 | 学力試験(ペーパーテスト) | 不要 | 共通テスト・個別試験 | 1月〜 | 2月〜 |
総合型選抜と学校推薦型選抜との違い
学校推薦型選抜は、出身高校からの推薦書が必要不可欠です。推薦を受けるためには、評定平均やスポーツ・文化活動で一定の基準を満たしていることが求められます。
一方、総合型選抜は高校からの推薦が不要で、出願条件さえ満たせれば誰でも出願できる点が大きな違いです。また、成績だけでなく、「大学で何を学びたいか」「将来どうなりたいか」といった学びへの意欲や目的意識、自己表現力、課外活動での経験なども重視されます。
さらに、両者の違いを整理すると次のようになります。
| 総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | |
|---|---|---|
| 出願条件 | 自由応募(推薦不要) | 学校長の推薦が必要 |
| 評価の中心 | 志望理由書・面接・小論文・活動実績 | 評定平均・出席状況・面接 |
| 主な選考時期 | 9〜12月 | 11〜12月 |
| 向いている人 | 自分の考えを伝える力や行動力をアピールしたい人 | 学校生活でコツコツ努力してきた人 |
総合型選抜は、「自ら大学を選び、大学に自分をプレゼンする入試」。
学校推薦型選抜は、「高校での実績をもとに大学へ推薦される入試」です。
どちらも人物評価を重視しますが、準備の方向性が異なります。志望理由書や面接対策など、求められる力が違うため、早めに方向性を定めて対策を始めることが大切です。
総合型選抜と一般選抜との違い
一般選抜は、主に学力試験の点数で合否が決まります。共通テストや大学ごとの個別試験で高得点を取ることが重要で、当日の試験結果がほぼすべてを左右します。
一方、総合型選抜は、学力だけでなく、自分の考えや将来のビジョン、大学で何を学びたいかをしっかりと伝えることが求められます。面接や小論文、プレゼンテーションなどを通して、自分の経験や意欲、課題解決力、コミュニケーション力などを多面的にアピールすることが大切です。
まとめ
今回の記事では、総合型選抜の仕組みや選考の流れ、受験のメリットなどについて、詳しく解説しました。
総合型選抜は、受験生が自分の目標や思いを言語化し、大学とのマッチングを丁寧に伝える力が問われる入試方式です。事前の準備が大きく合否に関わるため、早い段階から志望理由や自己分析に取り組むことが成功のカギになります。
以下に、総合選抜の主なポイントを改めて整理しておきましょう。
- 「学力試験だけでは測れない力」を評価する入試
- 以前のAO入試から名称と内容が変更された
- 面接・小論文・プレゼンなど多面的な評価を行う
- 共通テストや独自試験を導入する大学も増えている
- 学力以外の強みを活かして早期合格を目指せる
- 高校からの推薦が不要で自由に出願できる
- 一般入試と比べて合格率が高い大学もある
総合型選抜は、「自分の経験や将来のビジョンをしっかり伝えたい人」や「早めに進路を決めたい人」にとって、おすすめの入試方法です。しっかりと準備を重ねて、自分らしいアピールで合格をつかみましょう。
不安がある方は、志望理由書や自己PR文の書き方、面接練習など、早めに対策を始めることをおすすめします。トライでは、推薦・総合型選抜パーソナルプログラムでお子さま一人ひとりに合わせた対策が可能です。ご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。



合格へ導く4つのステップ
圧倒的な合格実績を生み出す、
他塾にはない徹底的なサポート
年間カリキュラム
の作成

目標とする志望校や現在の思考力レベルから、合格のために個別の専用カリキュラムを作成します。また、志望大学や興味のある学問から、併願校受験の戦略も提案します。
コーチング面接
【25コマ】

推薦・総合型選抜に特化した専門コーチが入試対策をサポートします。面談の際には生徒の将来像や志望理由の深掘りを徹底的に行い、より深みのある志望理由の完成に導きます。(質問対応も可)
動画コンテンツ
の視聴

推薦・総合型選抜の合格に必要な能力や対策方針をプロ講師が解説します。入試に精通したプロの目線でエッセンスを伝えますので、合格のためにすべきことが明確になります。
添削サポート
【全10回】

出願書類や小論文など、大学別に必要な書類を専門チームが添削しアドバイスします。執筆・添削・書き直し、という工程を繰り返すことで、書類の完成度を着実に高めます。
志望校に特化した
オーダーメイドの対策が可能です!