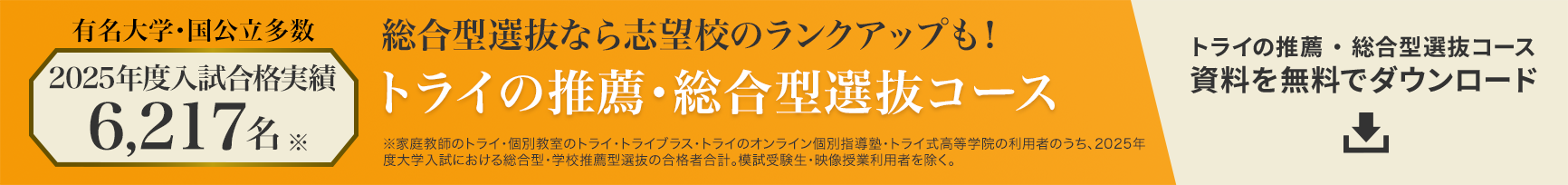総合型選抜のプレゼンテーションは、単なる情報伝達にとどまらず、受験生の個性や自己表現力を示す重要な機会です。この形式では、与えられたテーマに対して自分の視点や考えを効果的に伝えることが求められます。
そのため、プレゼンテーションの成功には事前の徹底した準備と練習が欠かせません。本記事では、総合型選抜のプレゼンテーションで高評価を得るための実践的な対策方法とアドバイスを紹介します。
総合型選抜で課されるプレゼンテーションとは?
総合型選抜のプレゼンテーションは、単なる発表とは異なり、受験生の自己表現力やプレゼンテーションスキルが重要です。
発表形式の入試では、決められたテーマに対して情報や知識を正確に伝えることが求められるのに対し、総合型選抜では、テーマに対する自分の考え方や視点をどれだけ効果的に伝えられるかが評価されます。
プレゼンテーションでは独自の視点を示しながら、聞き手を引き込む力が求められるため、単なる情報提供以上の説得力が必要です。
実施したい4つの対策方法
プレゼンテーションを成功させるためには、十分な準備と練習が欠かせません。特に総合型選抜のプレゼンテーションでは、自己表現能力やプレゼンテーションの技術が重視されるため、しっかりと対策を講じることが求められます。
以下の4つの方法を実践することで、効果的にスキルを向上させ成功に近づけることができます。
自分のプレゼンテーションを客観視する(録画する)
自分のプレゼンテーションを録画することで、話し方や表情、ジェスチャーを客観的に確認することができます。録画を繰り返し見返すことで、自分のパフォーマンスの良い点や改善が必要な点を見つけやすくなります。もちろん、録画ではなくて実際に生で見てもらえれば更に理想的です。
特に、声のトーンや発音、間の取り方など、聞き手に伝わりやすい話し方を意識して改善できるため、プレゼン全体の印象を良くすることができるでしょう。録画後に感じた点を次のプレゼンに活かすことで、どんどん洗練された発表ができるようになります。
質疑応答の内容を予想する
プレゼンテーションが終わった後、質疑応答の時間が設けられることがあります。そこでスムーズに答えられるよう、予想される質問に対する答えを事前に考えておくことが大切です。
質問はプレゼン内容に直接関連するものから、深掘りされたものまでさまざまです。そのため、予め想定される質問をリストアップし、自分なりの答えを準備しておくことで、緊張しすぎず落ち着いて答えることができます。一方で、綿密に準備をしたことにより、想定した質問に対する回答が早口になったり、想定外の質問があった際に全く対応できなくなったりといった弊害が生じることもあり得ます。想定される質問もなるべく一問一答の形式にすることを避け、内容的に幅広い問答への対応を心掛けつつ練習することが重要です。
質疑応答の準備は、自分の理解度を深めると同時に、プレゼン全体に対する自信を高めます。
うまい人のやり方を見る
上手にプレゼンテーションを行う人を観察することも大切です。特に、優れたプレゼンターがどのように聞き手と関わり、どんなタイミングで強調すべき点を伝えているのかに注目しましょう。
成功したプレゼンテーションを見て学ぶことで、話し方や進行の仕方、資料の使い方などのテクニックを実践に活かすことができます。模範的なプレゼンを参考にすることで、自分のプレゼンに応用することができるでしょう。
プレゼンテーションを繰り返す
プレゼンテーションは一度や二度の練習では完璧に仕上がりません。何度も繰り返し行い、自己評価を繰り返すことで、改善すべき点を洗い出すことが可能です。
繰り返し練習を行うことで、プレゼン内容の流れやタイミングを調整し、よりスムーズな進行が可能になります。繰り返し行うことで、自然に自信がつき、緊張感も薄れていきます。さらに、何度もプレゼンを行うことで予期せぬトラブルにも冷静に対応できるようになります。 制限時間を気にしすぎて、機械的な反復練習にならない様に気をつけましょう。
プレゼンの原稿を作成する際のポイント
プレゼンテーションの原稿作成は、その結果に大きく影響する重要なプロセスです。成功するプレゼンを行うためには、事前にしっかりと準備し、意識すべき点を押さえた原稿作成が求められます。
以下のポイントを踏まえて、効果的な原稿を作りましょう。
目的を明確にする
プレゼンテーションを作成する際には、まずその目的を明確にすることが大切です。プレゼンの目的をしっかりと定めておかないと話が散漫になり、話の意図が伝わりにくくなります。
目的によって伝えるべきメッセージが異なるため、最初に目的をはっきりさせ、その目的に沿った内容を組み立てることが重要です。例えば、新しい情報を提供する場合と、行動を促す場合では、そのアプローチが異なります。
目的を明確にすることで、伝えるべき要点が整理され、プレゼンがより効果的になります。
時間配分を意識する
プレゼンテーションには通常、制限時間があります。そのため、限られた時間内で要点をしっかりと伝えるには、適切な時間配分を考える必要があります。
原稿を作成する際には、イントロダクション、メインの内容、そして結論部分にどれくらいの時間を割くかを事前に計画し、それに基づいて内容を調整します。例えば、イントロダクションで長すぎる背景説明をすると、重要なポイントを伝える時間が足りなくなってしまう可能性があります。
その結果、結論部分が短くなりすぎると、聞き手が要点をしっかり理解できないまま終わってしまうかもしれません。原稿作成の段階で時間配分を考慮し、リハーサルを通じて実際のプレゼンに合った時間調整を行いましょう。
代表的なプレゼンの型を使う
効果的なプレゼンテーションには、よく使われる構成方法があります。
例えば、「起承転結」や「問題解決型」などの構成を活用することで、聞き手にわかりやすく伝えることができます。
起承転結型プレゼン この型は、プレゼンをストーリーのように展開する方法です。最初に話の導入(起)を行い、次に問題や背景(承)を述べ、その後、解決策や提案、予想される反論など(転)を示し、最後に結論(結)を述べる流れです。この構成は、内容をスムーズに伝えるのにおすすめです。
問題解決型プレゼン 問題提起から始まり、その問題を解決するための提案や方法を提示する構成です。この型は、直面しがちな問題を解決するアプローチを示すため、特にビジネスや研究発表などで効果を発揮します。短い制限時間のなかでは、こちらのほうが使いやすい場合が多いでしょう。
| 起承転結型プレゼン | この型は、プレゼンをストーリーのように展開する方法です。 最初に話の導入(起)を行い、次に問題や背景(承)を述べ、その後、解決策や提案、予想される反論など(転)を示し、最後に結論(結)を述べる流れです。 この構成は、内容をスムーズに伝えるのにおすすめです。 |
|---|---|
| 問題解決型プレゼン | 問題提起から始まり、その問題を解決するための提案や方法を提示する構成です。 この型は、直面しがちな問題を解決するアプローチを示すため、特にビジネスや研究発表などで効果を発揮します。 短い制限時間のなかでは、こちらのほうが使いやすい場合が多いでしょう。 |
これらの型をうまく使うことでプレゼンの流れが整理されるため、聞き手に理解してもらいやすくなります。原稿作成時には、目的に応じて最適な型を選び、内容を組み立てましょう。
効果的にプレゼンを行うコツ
プレゼンテーションを効果的に行うためには、話し方や態度が非常に重要です。聞き手にメッセージをしっかりと伝え、印象を残すためには、内容だけでなくその伝え方にも工夫を加えることが求められます。
以下のコツを意識して、プレゼンテーションをより魅力的で説得力のあるものにしましょう。
話し方に抑揚を付ける
プレゼン中、同じトーンで話し続けると聞き手の関心が薄れてしまいます。そのため、話し方に抑揚をつけることが大切です。声のトーンや話す速度を変えることで、重要なポイントを強調することができます。
例えば、重要なメッセージを話すときに少し声を高くしたり、逆に静かなトーンでゆっくり話したりすると、その内容が印象に残りやすくなります。抑揚をつけることで、プレゼンにリズムが生まれ、飽きさせることなくプレゼンを行うことができます。
ジェスチャーを取り入れる
言葉だけでは伝えられない感情やニュアンスを補うために、ジェスチャーを活用しましょう。手振りや体の動きを使うことで、メッセージに一層の力を加えることができます。たとえば、何かを強調するために手を広げたり重要なポイントを指で示したりすると、その内容に注目しやすくなります。
ジェスチャーを取り入れることで、プレゼンがよりダイナミックに感じられ、視覚的にも聞き手を引きつけることができます。ただし、過剰な動きは逆効果になり得るので、自然な範囲で使うことを心がけましょう。
大きな声でゆっくりと話す
プレゼンをする際には、明確で聞き取りやすい声で話すことが重要です。声が小さかったり、早口になったりすると、内容を理解しにくくなり聞き手の注意が散漫になることがあります。そのため、大きな声でゆっくり話すことを意識しましょう。
特に理解してほしい重要な内容は、ゆっくりと明瞭に話すことで、印象に残りやすくなります。ペースを調整することで内容をしっかり伝えられ、プレゼンを進行させやすくなります。
もちろん、教室の大きさやマイク等の機材の有無に応じた調整は行いましょう。序盤であまりにも大きな声を出してしまうと、その音量を維持できずにプレゼンテーションの内容によらず尻すぼみな印象を与えてしまう危険性もあります。
相手の目を見て話す
聞き手と目を合わせて話すことは、信頼感を築くための重要な手段です。アイコンタクトを取ることで、プレゼンターとしての自信を示し、誠実な印象を与えることができます。
また、目を見て話すことで、聞き手に関心を持って聞いてもらえるようになります。適切なアイコンタクトを取ることでより関心を持ち、積極的に内容を受け入れてくれるようになります。アイコンタクトについては、聞き手の人数や発表教室の状況等によって変動しますし、なかなか難しい部分ですが、ぜひ意識してみてください。
総合型選抜でプレゼンテーションを課す主な大学
ここでは、どの大学が総合型選抜でプレゼンテーションを課しているのか、以下にて参考例を紹介します。
ここに載っていない大学も、場合によっては、事前の告知なく数分間で自己紹介や自己アピールをする小プレゼンテーションが課されることも珍しくありませんので、ある程度の準備は必ずしておくことをおすすめします。
私立大学編
私立大学でプレゼンテーションが課されている大学の例は以下のとおりです。
● 立命館大学(映像学部 絵コンテ作画型)
● 関東学院大学(比較文化学科)
● 日本大学(経済学部)
国公立大学編
国公立大学でプレゼンテーションが課されている大学の例は以下の通りです。
● 横浜市立大学(国際商学部)
● 東京農工大学(工学部)
● 都留文科大学(教養学部 学校教育学科/図画工作系)
まとめ
総合型選抜のプレゼンテーションで成功するためには、徹底した準備と練習がカギとなります。プレゼンの内容を録画して自分のパフォーマンスを見直し、予想される質問に事前に備えておくことで冷静に対応できるようになります。
また、他の成功したプレゼンを参考にして、効果的な話し方や進行方法を学ぶことが重要です。繰り返しプレゼンを練習することで、スムーズに進行できるようになり、自信を持って臨めるようになります。
これらの準備を着実に実行することでプレゼンテーションスキルが向上し、総合型選抜での成功に繋がるでしょう。プレゼンは、特に自学自習での対策が難しい項目です。総合型選抜の対策が可能な塾や個別指導を活用し、より内容をブラッシュアップすることで、合格に一歩でも近づけるようにしましょう。




合格へ導く4つのステップ
圧倒的な合格実績を生み出す、
他塾にはない徹底的なサポート
年間カリキュラム
の作成

目標とする志望校や現在の思考力レベルから、合格のために個別の専用カリキュラムを作成します。また、志望大学や興味のある学問から、併願校受験の戦略も提案します。
コーチング面接
【25コマ】

推薦・総合型選抜に特化した専門コーチが入試対策をサポートします。面談の際には生徒の将来像や志望理由の深掘りを徹底的に行い、より深みのある志望理由の完成に導きます。(質問対応も可)
動画コンテンツ
の視聴

推薦・総合型選抜の合格に必要な能力や対策方針をプロ講師が解説します。入試に精通したプロの目線でエッセンスを伝えますので、合格のためにすべきことが明確になります。
添削サポート
【全10回】

出願書類や小論文など、大学別に必要な書類を専門チームが添削しアドバイスします。執筆・添削・書き直し、という工程を繰り返すことで、書類の完成度を着実に高めます。
志望校に特化した
オーダーメイドの対策が可能です!