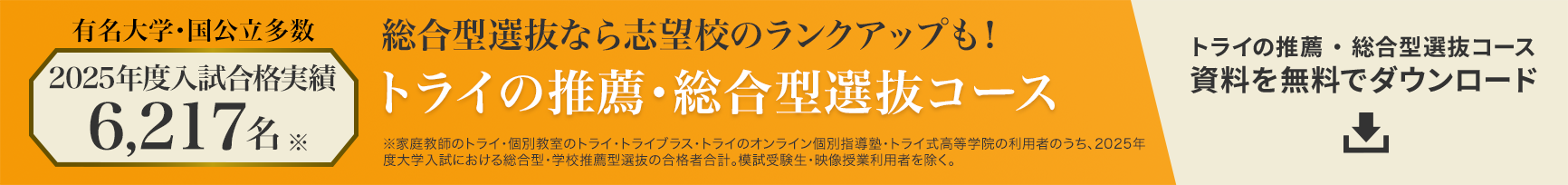総合型選抜では、筆記試験が一般選抜とは異なる形で実施されます。単なる知識や理解力の確認ではなく、思考力・表現力・適性を評価する目的で設けられており、大学ごとに試験の形式や内容が大きく異なる点が特徴です。本記事では、総合型選抜における筆記試験の種類や特徴を整理し、具体的な大学の事例とともに詳しく解説します。総合型選抜入試を検討している方は、試験形式の違いや求められるポイントを把握し、自分に合った準備を進めるための参考としてください。
総合型選抜での筆記試験とは?
総合型選抜における筆記試験は、一般的な学力試験とは異なる形式で実施されます。各大学が求める学生像に基づき、それぞれ独自の試験が設けられている点が特徴です。従来の大学入試では、知識の正確な理解や蓄積を測る試験が中心でしたが、社会の変化に伴い、主体性や多様性、協働性といった能力を評価する必要性が高まってきました。
こうした背景から、総合型選抜では単なる知識を問う試験ではなく、思考力や表現力を重視した筆記試験が多く採用されています。主に論述形式の問題が中心で、小論文や表・グラフを読み取って意見を述べたり、歴史や社会問題に関する知識が求められたり、また、国際系の学部などでは英語の長文読解のあと、英語または日本語、場合によっては双方での論述問題が出題されたりすることもあります。
一部の学部・学科では、専門的な知識を問う筆記試験が行われることもありますが、一般選抜のように知識重視の試験とは異なり、受験生の思考力や表現力を測ることに重点が置かれています。
このように、総合型選抜の筆記試験は、受験生の多面的な能力を評価するための重要な手段となっています。単なる学力対策だけでなく、論述力や思考力を養う準備が重要となるでしょう。
総合型選抜の筆記試験の種類と特徴
総合型選抜の実際の入試における筆記試験について、主に6つのカテゴリーに分けて解説していきます。
なお、総合型選抜の筆記試験は各大学の学部・学科により多岐に渡る形式で実施されており、以下の6つのどれかに明確に当てはまらない場合もあります。志望校の過去の出題傾向をできる限りリサーチして、出題の特徴を的確に把握することが重要となります。
一般小論文/作文
一般小論文/作文は、総合型選抜における筆記試験の一形態であり、受験生の思考力・表現力・論理的構成力を評価する目的で実施されます。試験では、与えられたテーマに対し、自身の考えを論理的に展開する「小論文」と、感性や価値観を自由に表現する「作文・創作」の2種類の形式が見られます。
一般小論文/作文の試験時間や文字数は大学ごとに異なり、事例として以下のような形式があります。
- 一般的な小論文:試験時間約60分、文字数800字程度
- 長文小論文:試験時間約180分、文字数600~800字+1,400~1,600字の2つの課題
- 英語を含む小論文:試験時間約90分、英語の資料を読解し日本語で論述
- 作文・創作:テーマに基づき自由に表現
一般選抜でも広く出題されている方式の小論文と同様です。
一般選抜であれば、国公立大学の後期日程や、一部の小論文重視型の選抜方式で課されます。(国公立大学の後期日程は実際には減少傾向)
国公立大医学部の2次試験等で英語の代わりに課されるケースや国公立大の後期試験でも見られる形式です。単科大学の英語試験では実質的に英語小論文と考えられる場合もあります。入試制度改革の影響で、近年は私大の一般選抜でも実施される傾向にあります。
文学系・芸術系学部を中心に、一般選抜・特別選抜を問わず以前から広く出題されている形式です。
小論文は、主に社会問題・時事問題・学問的テーマが出題され、受験生が論理的思考力を発揮しながら意見を述べることが求められます。一方、作文・創作は、指定されたテーマをもとに受験生が自由な発想で文章を作成し、独創性や表現力が重視される点が特徴です。
講義型レポート/講義理解力テスト
講義型レポート/講義理解力テストは、総合型選抜入試において、受験生の聴解力・要約力・論理的思考力を評価するための試験形式です。大学の講義形式に近い形で試験が実施されるため、入学後の学習適性を測る目的も含まれています。
この試験は、講義や講演(40~90分)を受講した後、記述式の試験(60分程度)に取り組む形式が一般的です。講義の内容を整理し、論理的に考察・表現する力が求められます。
講義型レポート/講義理解力テストは、以下のような試験形式が採用されることが多い傾向にあります。
- 要約問題:講義内容の要点を簡潔にまとめる
- 理解度確認問題:講義で述べられた概念や事例について説明する
- 考察問題:講義内容を踏まえ、自分の意見や解釈を述べる
- 課題解決型問題:講義の内容を応用し、特定の問題について解決策を提示する
この試験では、単なる知識の再現ではなく、論理的に整理し、自分の考えを的確に伝える力が問われます。特に学問的なテーマや専門的な内容が出題される傾向が強く、単純な暗記では対応できない試験形式となっています。
☑︎参考
講義を受講した後にレポートを書く形式と似ているものとして、ディベートやグループワークを実施した後に、その内容を小論文としてまとめるスタイルの試験があり、比較的多くの学部で課される傾向にあります。
基礎学力試験
基礎学力試験は、総合型選抜において受験生の学力を確認するために実施される試験形式です。大学によっては学力試験を課さない場合もありますが、一定の学力を重視する大学では、選考の一部としてこの試験を組み込んでいます。
試験では、主に国語・英語・数学の3科目が対象となり、高校1~2年生レベルの基礎的な知識を問う問題が出題されることが多いです。ただし、ほぼ中学レベルの内容しか問われない内容もあれば、大学入試の一般選抜と遜色ない難易度の問題が出題されるものもあります。
かつ、年度によってレベルや問題数、科目間の問題数の配分や出題範囲等が大きく変動することも少なくありません。特に数学においては、理系学部で理系固有の範囲が年度により出題されたりされなかったりすることが多く見られます。そのため、過去に文理共通の範囲しか出題されていなかった年度の試験情報だけを参考にして、「実施時期が早いから文理共通の範囲からしか出題されないだろう」と早合点しないよう注意が必要です。
基礎学力試験は、以下のような形式が採用されています。
- 3科目をまとめて実施する方式(国語・英語・数学)や、1科目のみを選択する方式など、さまざまなパターンが存在
この試験は、大学での学習を進める上で必要な最低限の学力を確認する目的で実施されるため、「基礎的」と表記されていても油断は禁物です。実際には大学ごとに難易度の差が大きいため、可能な限り具体的に内容を把握することが重要であり、事前にできる限り出題傾向を把握し十分な準備を行うことが求められます。
総合問題
総合問題は、総合型選抜において受験生の思考力・判断力・表現力を総合的に評価する試験です。単なる知識の確認ではなく、複数の科目や分野を横断する能力が必須です。特に、資料の分析・データの読解・論理的な記述が重要視される点が特徴です。
試験時間は80分程度が一般的で、国語・数学を中心に複数の知識を組み合わせた問題が出題されます。
総合問題は、以下のような特徴を持つ問題形式が多く採用されています。
- 複数科目の知識を活用する問題
- 統計データや資料の読解を含む問題
- 記述式の解答が中心
基礎学力試験とは異なり、単純な知識の暗記ではなく、複数の情報を組み合わせて解答する能力が求められます。
専門試験
専門試験は、受験する学部・学科ごとの専門性や適性を評価する試験です。一般的な学力試験とは違って「大学での専門分野の基本的な内容を問う試験」であり、「高校での学習内容を問う試験」ではありません。学問の基礎的な理解や応用力が試されるため、各学部のカリキュラムに沿った内容が出題されることが特徴です。
試験の形式は大学や学部ごとに異なりますが、主に以下のような試験が実施されます。
- 理系学部の専門試験
- 国際系・英語を重視する学部の英語試験
- デザイン・建築・芸術系のプランニング試験
- 実験・観察型試験
試験の名称が同じであっても、大学ごとに出題の意図や内容が異なる場合があるため、事前にしっかり確認することが求められます。
適性テスト
適性テストは、受験生の学部・学科に対する適性や基礎的な能力を評価する試験です。ただし「適性テスト」という名称は大学ごとに異なる意味で使用されることがあり、特定の分野に関連する思考力・判断力・表現力を測るものから、学力試験に近いものまで幅広い形式が存在します。
特筆すべきは、総合型選抜における数ある評価項目の中でも、適性テストは評価が著しく低い場合、他の評価項目の結果に関わらず不合格となる可能性が最も高い項目だということです。これは、本来の意味での適性が低いと判断された場合、当該学部・学科での学習についていけなくなる可能性も否定できないためです。そのため、受験生としては特に重視すべき試験と言えるでしょう。
本来は、クレペリン検査などの認知適性を測る試験が「適性テスト」として分類されるべきものですが、実際には基礎学力試験を「大学での勉学に対する適性を見る」という意味で「適性テスト」と呼んでいる場合もあります。
また、適性テストの中には、1年程度の対策で十分に準備可能なものもあれば、特殊な訓練や長期的な準備が必要なものもあります。そのため、「対策が1年程度で原理的に可能なものであるか否か」を事前に確認することが必須です。
適性テストの内容は大学・学部によって異なりますが、以下のような形式が採用されることが多い傾向にあります。
- 心理・行動に関するデータの読み取りと解釈
- 学部・学科の特性に応じた専門的内容
- 語学力判定試験
- 小論文形式の適性テスト
試験の名称が同じでも、大学ごとに内容が異なるため、過去の出題傾向を確認し、志望校の試験に適した準備を進めることが重要です。
その他の特殊な筆記試験
総合型選抜入試では、一般的な筆記試験のほかに、学部・学科の特性に応じた特殊な筆記試験が課される場合があります。これらの試験は、特定の専門分野への適性を測る目的で実施され、一般的な小論文や基礎学力試験などとは異なる形式を取ることが特徴です。
■芸術系学部
美術・音楽・演劇などの芸術系学部では、芸術作品の鑑賞後に、その作品に関する考察を求める小論文が課されることがあります。単なる感想ではなく、作品の表現技法や時代背景などを踏まえた分析力が問われます。
■体育・スポーツ系学部
保健体育に関する小論文や、スポーツ科学的な観点で競技のパフォーマンス改善策を述べる課題が出される場合があります。また、特定の競技の実演や、VTRを視聴した上での分析を求められることもあり、競技に対する理解力や指導力が評価の対象となります。
■教育学部
教育学部では、実技科目(音楽・美術・家庭科など)に関連する筆記試験が実施されることがあります。さらに、付属の幼稚園や小中学校が充実している大学では、教育実習的な活動を行い、その後、感想や反省点、改善策を述べる小論文を課すケースも見られます。
■宗教系学部
宗教系の学部では、その宗教の教義に関する筆記試験や小論文が課されることがあります。出願者が特定の宗教に対する理解を深めているか、学問としての宗教学にどの程度関心を持ち、論理的に考察できるかが評価のポイントとなります。
総合型選抜の筆記試験の事例
総合型選抜の筆記試験について、実際の入試での出題事例をご紹介します。一般選抜での学力確認のような筆記試験とは異なるスタイルであることが理解できると思います。
早稲田大学 創造理工学部 早稲田建築AO入試
与えられたテーマに基づき、鉛筆を用いたドローイングと文章による説明を通じて、提案や表現を行うスタイルです。単なる造形的な空間描写にとどまらず、社会的な知識や思考力、さらには工学的視点を取り入れた総合的な論理構築力が求められます。試験時間はおおよそ120分で実施されています。
東北大学 工学部 AOⅡ期入試
2024年度の入試では、英語・数学・理科(物理・化学)の3科目で構成され、各80分の試験時間で実施されました。英語は読解力と記述力を問う形式で、小論文を含む設問が特徴的でした。数学は基礎的な問題が中心で、迅速かつ正確な解答が求められる内容でした。理科は、物理・化学ともに幅広い分野から出題され、知識量と問題処理能力が試される内容となっていたことが特徴です。
帝京大学 薬学部 基礎能力適性検査
基礎能力適性検査は二次選考の一環として実施され、合否に大きく影響する重要な試験です。薬学部では3科目が課され、化学・数学が必須科目となり、残りの1科目は英語・国語・生物の中から選択する形式が採用されています。
武蔵大学 人文学部 ヨーロッパ文化学科 AO入試
学科適性重視方式と語学力重視方式の2つがあります。それぞれ筆記試験の内容が異なりますが、ここでは学科適性重視方式の事例を紹介します。
学科適性重視方式の筆記試験は、ヨーロッパ文化に関する日本語小論文と、英語・ドイツ語・フランス語の基礎語彙を問う小問で構成されており、試験時にいずれかの言語を選択する形式が採用されています。試験時間は90分間となっています。
神奈川工科大学 情報学部 適性検査方式
総合型選抜の全体配点の約40%を占める記述式の適性検査が実施されます。試験時間は60分で、数学(数学I・II・A)を出題範囲とし、知識・技能だけでなく、思考力・判断力・表現力が評価される形式となっています。
千葉商科大学 一般総合型選抜 適性試験型
国語・数学・英語・総合問題による基礎学力検査が実施され、PCを使用したCBT(Computer Based Testing)方式が採用されています。試験は 商経・総合政策・サービス創造・人間社会 の各学部で実施されます。
慶應義塾大学 法学部 FIT入試 A方式
50分間の模擬講義を受講した後、45分間の論述試験に取り組む形式となっています。テーマは法学や政治学に関連する社会問題が出題される傾向にあります。解答は、A3レポート用紙に2240文字以内で記述するスタイルが採用されています。
総合型選抜入試の筆記試験 まとめ
総合型選抜の筆記試験は単なる学力測定ではなく、受験生の思考力・表現力・適性を評価する重要な選考要素として位置づけられている傾向にあります。試験の種類は多岐にわたり、小論文や総合問題、専門試験、適性検査など、各大学・学部が重視する能力や適性を測る目的で、異なる試験形式が採用されています。
総合型選抜の筆記試験は、受験生が自らの能力や適性を示す場でもあります。知識の正確さだけでなく、情報を的確に整理し、論理的に考察・表現するスキルを念頭に、志望大学の学部・学科の出題傾向を踏まえた準備を行うことで、合格の可能性を高めることができるでしょう。もし、準備の進め方に不安がある場合は、総合型選抜を得意とする個別指導塾の活用がおすすめです。志望大学の具体的な事例や最新の情報を知ることができ、効率的に対策を進めることができます。




合格へ導く4つのステップ
圧倒的な合格実績を生み出す、
他塾にはない徹底的なサポート
年間カリキュラム
の作成

目標とする志望校や現在の思考力レベルから、合格のために個別の専用カリキュラムを作成します。また、志望大学や興味のある学問から、併願校受験の戦略も提案します。
コーチング面接
【25コマ】

推薦・総合型選抜に特化した専門コーチが入試対策をサポートします。面談の際には生徒の将来像や志望理由の深掘りを徹底的に行い、より深みのある志望理由の完成に導きます。(質問対応も可)
動画コンテンツ
の視聴

推薦・総合型選抜の合格に必要な能力や対策方針をプロ講師が解説します。入試に精通したプロの目線でエッセンスを伝えますので、合格のためにすべきことが明確になります。
添削サポート
【全10回】

出願書類や小論文など、大学別に必要な書類を専門チームが添削しアドバイスします。執筆・添削・書き直し、という工程を繰り返すことで、書類の完成度を着実に高めます。
志望校に特化した
オーダーメイドの対策が可能です!