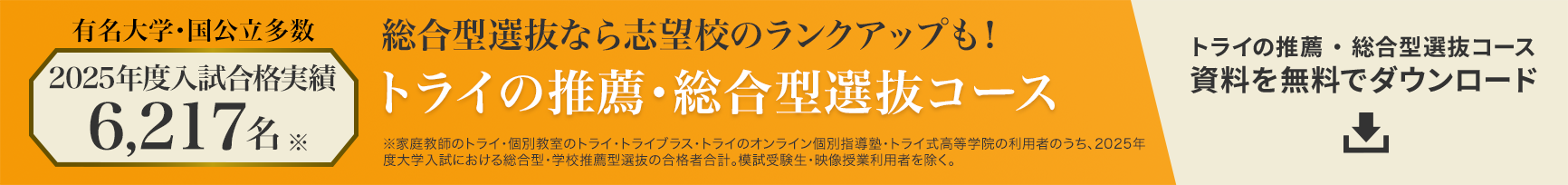総合型選抜では、学力試験の結果だけでなく、自分自身の興味・関心や強みを的確に伝える力が求められます。そのために欠かせないのが「自己分析」です。しかし、「具体的に何をどう分析すれば良いのかわからない」と悩む受験生も多いでしょう。
本記事では、総合型選抜における自己分析の重要性を解説し、効果的な進め方や活用できるフレームワーク・ツールを紹介します。「どの大学を選ぶべきか」「自分の強みをどう活かせるか」といった悩みを解決するために、自己分析の本質を理解し合格につながる準備を始めましょう。
総合型選抜における自己分析とは
総合型選抜を突破するために「自己分析」は合格に直結する重要なステップです。総合型選抜を経験し難関大学に合格した人のインタビューなどで、よく耳にする「自己分析をしっかり行った」という言葉。しかし、具体的にどんな自己分析をすれば良いのかわからず悩んでいる人も多いのではないでしょうか?
今回は、総合型選抜における自己分析の本質と、効果的なやり方について詳しく解説します。総合型選抜では、あなた自身の特性や将来のビジョンを的確にアピールすることが求められます。そのため、自分の強みや弱み、過去の経験を振り返り、どのように大学での学びに活かしていけるのかを自分自身で認識できるようになると、志望理由書や面接でのアピールポイントを明確にすることができます。つまり、他の受験生との差別化をするための土台が自己分析であるというわけです。
簡単にできそうなイメージもありますが、じっくり向き合っていくとかなりの時間と労力を要する作業です。志望理由にも大きな影響を与える要素でもあるため、期間的な余裕を持って取り組んでいくことが求められます。
自己分析で明確にしたいポイントとは?
自己分析を実施する際に、明確にしたいポイントをあらかじめ意識して行うことで、自己分析が効率的なものになります。ここでは、特に重要な以下のポイントについて解説します。
自分の興味・関心を明確にする
総合型選抜では、「将来的にどのようなことを実現したいのか」を具体的に示すことが重要です。そのため、まずは自身がどのような分野に興味を持ち、どのようなことに情熱を感じるのかを明確にすることが求められます。
興味のある領域・分野を洗い出すことで、大学入学後の学びと将来の目標がどう関連づけられるのかを論理的に整理しやすくなります。また、単純に「○○に興味がある」というだけでなく、なぜその分野に惹かれるのか、どのような経験が影響しているのかまで掘り下げることで、より説得力のある志望理由に繋げることができます。
自分の強みや性格の傾向を把握する
総合型選抜は、学力だけでなく、大学のポリシーとの相性が重視される入試形式です。そのため、大学が求める人物像と自分の特性が合致しているかを把握し、明確な根拠を伝えられるようにすることが必要です。
自分の強みや性格の傾向を明確にすることで、「なぜ志望大学や学部・学科が自分にとって最適なのか」を筋道立てて説明できるようになります。例えば、リーダーシップがあるのか、それとも協調性を活かしてチームで成果を出すタイプなのかなど、過去の経験を振り返りながら整理してみると良いでしょう。
志望大学・学部との相性を考える
総合型選抜では、自己分析をもとに志望大学・学部との相性を考えることも重要です。まず、大学の「建学の精神」や「校風」「独自のプログラム」などを調べ、自分の特徴や興味・関心と合致する点を整理しましょう。
また、志望学部・学科のアドミッション・ポリシーを確認し、自分の強みや経験と大学が求める人物像の方向性が合致するかを考えてみましょう。志望校の公式サイトやオープンキャンパスなども活用し、大学の特色と自分の特徴や将来ビジョンの相性を検討してみましょう。
総合型選抜の自己分析~具体的手法
SWOT分析
総合型選抜において自己分析を深める手法の一つがSWOT分析です。元来は会社の経営戦略を策定する上で使用するフレームのひとつですが、総合型選抜における自己分析にも応用可能であり、自分自身の状況を整理し、強みを最大限に活かしながら弱点やリスクに対処するための4つの要素から成るフレームワークです。
■S(Strengths / 強み)
自分の得意なことや、優れている点を明確にします。例えば、「計画的に物事を進められる」「リーダーシップを発揮できる」「部活動で優れた成績を収めた」など、内面的な特性や実績を振り返ることが重要です。
■W(Weaknesses / 弱み)
自分が苦手なことや克服すべき課題を整理します。例えば、「人前で話すのが苦手」「長期的な目標を立てるのが難しい」など、自己改善のポイントを把握することで、今後の成長につなげられます。
■O(Opportunities / 機会)
自分にとって追い風となる外部環境を特定します。例えば、「高校で探究学習や地域連携のプロジェクトに参加できる機会があった」「自分の特性と大学の教育方針やポリシーとの相性がよい」「志望大学に、自分の興味分野に関する専門的なゼミや研究室がある」など、自分の将来像と結びつく学びや環境に注目することが大切です。
■T(Threats / 脅威)
逆に、自分にとって不利になりうる外部要因を整理します。例えば、「他の受験生と比べて活動実績が少ないと感じる」「面接やプレゼンでうまく自分をアピールできるか心配」「社会の変化が早く、将来像を明確に描くのが難しいと感じている」「性格がのんびりしていて、○○な仕事には向いていない」など、リスクや不安を見つめることで、準備すべきことが見えてきます。
■SWOT分析を活用するポイント
SWOT分析を効果的に行うためには、まず思いつくままに自分の特性を書き出し、そこから不要なものを削ぎ落として整理する流れがおすすめです。試験本番が近くなるほど、このような活動に時間を割きにくくなるので、自己分析はその性質上、早めに行うに越したことがないのみならず、相応の手間がかかることを考慮して早めに実施することをおすすめします。
最初は細かいことを気にせず、自分の強みや課題を幅広く挙げていき、その後、大学での学びや将来のビジョンと結びつけられる要素に絞り込んでいきましょう。
また、事実に基づいて自己分析を行うことが重要です。例えば、「水泳が得意」という事実があっても、それが大学側にどのように評価されるかは学校ごとに異なります。特定の種目が得意であるだけでは、大学側にアピールすることは極めて難しく、大会出場歴・受賞歴や公式記録がないと事実上アピールは困難です。
唯一例外があるとすれば、面接での自己アピール手段の幅が広く、実演によるアピールも可能な場合ですが、この場合でもアピール可能な種目等は大幅な制約を受けることにも注意が必要です。自分で勝手に価値を決めつけるのではなく、客観的な視点で自分を分析する姿勢が求められます。
16 Personalities分析を利用する
国際的にも注目を集めている「16 Personalities」は、自己分析を深める際に大いに活用できる有益なリソースの一つです。この診断では、自分の長所や短所を明確にし、思考の傾向や価値観の特徴を把握することができます。
同時に、自身が能力を最大限に活かしやすい領域はどこなのかという視点でのアドバイスも得ることができるため、将来ビジョンの方向性や志望大学、学部学科選びを実施する際にも非常に参考になります。
ただし、診断結果・アドバイスを絶対視してしまうことは避けましょう。性格を完全に16タイプに分類できるわけではないことに注意する必要があります。
あくまでも自分自身を客観的に分析・理解する方法の1つであるという感覚を忘れずに、より的確に自身の可能性や新たな得意領域を模索するためのヒントとすべきです。このような的確な使い方ができれば、より質の高い志望理由の構築や、面接などで自分自身をより魅力的に伝えることができるでしょう。
自分史を作成する
自己分析とは、自分自身を掘り下げて、自分への理解を深めていく作業の中で、自身の興味があることや関心事を改めて認識していく流れになりますが、それらがどのような経緯、どのようなタイミングによるものだったのかを振り返る「自分史」を作成してみるのも効果的です。
自分の記憶をできる限りたどり、幼稚園や保育園などでの出来事から始まり、小学生、中学生を経て最近の出来事まで、できる限りの情報を整理してみましょう。スマートフォンの普及により、当時の画像や動画が鮮明な形で残っている可能性もあるので、ご家族に声をかけてみると良いでしょう。個人的な記録はもとより、幼少期に興味のあった音楽やテレビ番組等も、あまり費用をかけずにインターネットで現物を確認できる時代になっているので、幼少期の自分の興味・関心を掘り下げる手段として活用できます。
そのようなリソースを活用しながら年齢を軸にカテゴリー分けを行い、マインドマップやスプレッドシートなどで整理していきます。修正や加筆によって、さらなる完成度を高めましょう。
その際、よみがえった当時の感情も書き留めていく作業も行いましょう。嬉しかったことや楽しかったことには自身の関心が反映されており、好きなことややりたいことを将来ビジョンにつなげるヒントになります。
一方で、悲しかったことやつらかったことも貴重です。これらの記憶に刻まれた疑問やネガティブな感情は、自分が将来的に関心を寄せる社会的な課題を見出すヒントになるかもしれません。
自分自身で自分の性格を言語化してみる
自分の性格を言語化し客観的に捉えることは、自己理解を深めるために重要な手段です。まずは、自分の基本的な情報を整理し、どのような特性を持っているのかを明確にしてみましょう。
長所と短所の両方を意識しながら、自分がどのような場面で強みを発揮しやすいのか、逆にどのような状況で苦手意識を持ちやすいのかを整理してみるのも有効です。
その際、自分視点だけでなく、周囲からよく言われる自身への印象も活用します。主観と客観の両視点を絡めて言語化することで、自分がどのような人間なのか、より客観的に理解することに繋がります。自分で感じている性格と他者から見た印象を比較することで、新たな気づきを得られる可能性もあります。
また、思考や行動パターンを可視化してみることも重要です。何かを決断する際、どのような基準を拠りどころにしているか、どのような状況でストレスを感じやすいのかなどを明確にすることで、それまで気づくことのなかった自分の行動特性を再発見するきっかけにもなるでしょう。
自己分析をより上手く進めるポイント
過去の出来事を深く思い出す必要があることを理解しておく
過去を振り返ることで、思い出したくない記憶に遭遇し、感情的になってしまうことがあります。自己分析を進める際には、無理にすべてを明らかにする必要はありません。自分の心の状態を優先し、できる範囲で振り返りを行ってみるスタンスが大切です。
もし辛さを感じた場合、一人で抱え込まずに誰かに話してみるのも効果的です。信頼できる友人や家族など、感情をシェアできる相手がいると気持ちを整理しやすくなります。もし話せる相手がいない場合は、ノートに思いのまま書き出すことで心の負担が軽減され、感情的にならず気持ちの整理がうまく進む場合もあります。
どうしても気持ちが沈んでしまい先に進めなくなった場合は、無理に続ける必要はありません。自己分析は過去のすべてを掘り下げることが目的ではなく、今の自分を理解するための手段に過ぎません。無理に深掘りしすぎず、できる範囲で進めていきましょう。
分析の結果や過程を共有する
自己分析や自己理解を進める中では、一人でブレインストーミングするなどのアプローチが基本となりますが、分析や理解した内容について、自分以外の第三者とシェアしフィードバックを貰うことで、分析や理解の質を高めることができます。
共有相手は、家族や学校の先生などが一般的ですが、総合型選抜を経験した先輩や塾講師らとやり取りできる機会があれば、より実践的に分析や理解を活かすきっかけになるのでおすすめです。自分自身では全く気づくことのなかった強みや良さを、全く別の視点から改めて認識する流れになるかもしれません。
自己分析が苦手な人向けのアドバイス
自己分析が「何を分析すればよいかわからない」ことや、「強みやアピールポイントが見つからない」ことが原因で詰まってしまう場合があります。こうした際には、総合型選抜に精通した指導者のアドバイスを受けることも有効です。
特に個別指導スタイルの塾では、一人ひとりの特性に合わせたフィードバックを受けられるため、自己理解を効率的に深めることができます。また、分析の方向性も整理し直し、志望理由書や面接により効果的につながる形で経験を言語化するサポートも得られるでしょう。
自己分析に行き詰まったときは、専門的な指導を活用するのも有効な選択肢です。
総合型選抜と自己分析 まとめ
総合型選抜において自己分析は、単なる自己理解ではなく、合格を勝ち取るための重要な戦略の一つです。自分の興味・関心や強みを明確にし、それを大学の求める人物像や学びの環境に結びつけることで、志望理由書や面接での説得力を高めることができます。
また、自己分析は一度行えば終わりではなく、何度も見直しながら深めていくものです。複数のフレームワークを活用し、具体的なエピソードと結びつけることで、より鮮明な自己像を描くことができます。うまく進められない場合は、総合型選抜に特化した個別指導などを活用するのも一つの手段です。
総合型選抜では「自分をどう表現するか」が合否を左右します。時間をかけて丁寧に自己分析を行い、自分なりのストーリーを確立し、自信を持って本番に臨みましょう。




合格へ導く4つのステップ
圧倒的な合格実績を生み出す、
他塾にはない徹底的なサポート
年間カリキュラム
の作成

目標とする志望校や現在の思考力レベルから、合格のために個別の専用カリキュラムを作成します。また、志望大学や興味のある学問から、併願校受験の戦略も提案します。
コーチング面接
【25コマ】

推薦・総合型選抜に特化した専門コーチが入試対策をサポートします。面談の際には生徒の将来像や志望理由の深掘りを徹底的に行い、より深みのある志望理由の完成に導きます。(質問対応も可)
動画コンテンツ
の視聴

推薦・総合型選抜の合格に必要な能力や対策方針をプロ講師が解説します。入試に精通したプロの目線でエッセンスを伝えますので、合格のためにすべきことが明確になります。
添削サポート
【全10回】

出願書類や小論文など、大学別に必要な書類を専門チームが添削しアドバイスします。執筆・添削・書き直し、という工程を繰り返すことで、書類の完成度を着実に高めます。
志望校に特化した
オーダーメイドの対策が可能です!