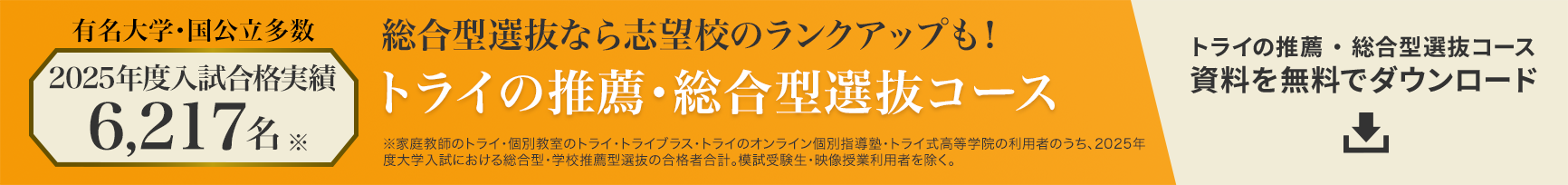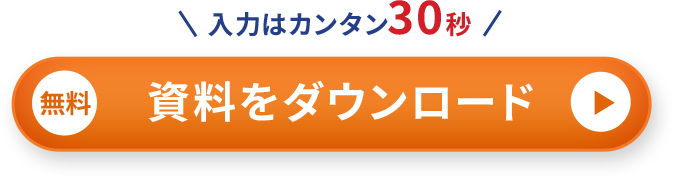総合型選抜は、学力試験だけでは評価されにくい個性や経験、意欲を活かせる入試方式として注目を集めています。しかしその一方で、対策の難しさや早い段階からの準備が求められる点など、事前に知っておくべきポイントも多く存在します。
本記事では、総合型選抜のメリットとデメリットを客観的に整理した上で、どのような人に向いているのかをわかりやすく解説します。これから受験を検討している方が、自分に合った入試形式を選ぶための参考になれば幸いです。
総合型選抜とは?他の入試との違い
総合型選抜は、学力試験の点数だけでなく、意欲や人物像、これまでの経験を総合的に評価する入試です。ここでは、一般選抜や推薦型選抜との違いを整理しながら、どのような大学で実施されているのかを紹介します。
総合型選抜(旧AO入試)の概要
総合型選抜は、出願書類や面接、小論文、プレゼンテーションなどを通して受験生の意欲・適性を評価する入試です。学力試験中心ではなく、これまでの活動実績や将来の目標と大学の教育方針が一致しているかが重視されます。高校生活での経験を活かせる点が特徴です。
学校推薦型選抜・一般選抜との違い
学校推薦型選抜が「高校からの推薦」と評定を基にした選抜であるのに対し、総合型選抜は自己推薦の要素が強く、学力以外の側面を自ら発信する形式です。一般選抜のような筆記試験がない分、早期の準備と自己分析力が求められます。
総合型選抜を実施する大学の傾向
総合型選抜は私立大学を中心に広がっていますが、近年は国公立大学でも導入が進んでいます。私立では、学部・学科の特色を生かし、探究活動やボランティア、リーダー経験などを評価する選考が多いのが特徴です。
一方、国公立大学では「地域貢献」「研究意欲」「課題発見力」といった観点を重視する傾向が強く、共通テストを課す大学も少なくありません。
同じ「総合型選抜」でも大学によって評価軸が異なるため、募集要項や過去の出題傾向を確認し、自分の強みが活かせる大学を見極めることが重要です。

総合型選抜のメリット
総合型選抜には、学力以外の力を評価してもらえること、早期に進路を決められることなど、多くの利点があります。受験生にとっての主なメリットを見ていきましょう。
学力が選考基準の全てではない
総合型選抜の大きなメリットの一つとして、従来の学力試験中心の選考ではないという点が挙げられます。総合型選抜では、志望大学の学部・学科が求める人物像に合致し、その学問領域を学ぶ意欲や資質を持つことを上手く伝えられるかが合否の分かれ目となります。部活動でリーダーシップを発揮してきた経験や、ボランティアやその他の社会的な活動での実績など、いわゆる学力試験以外の要因も評価される入試形式です。
ワンランク上の大学へのチャンスがある
総合型選抜では、筆記試験による学力評価が中心となる一般選抜とは異なり、主体性や協調性、行動力など多面的な力が重視されるため、たとえ学力が平均的な水準であっても、その他の面において際立った強みがあれば、ワンランク上、あるいはそれ以上の大学に合格することも珍しくありません。
上位大学への進学が実現することで、得られる人脈や環境が将来的なキャリア形成において良い影響をもたらすだけでなく、社会的評価の高い学歴として、その後の人生にもプラスに働く可能性があります。
倍率が低い場合がある
さまざまな大学の総合型選抜入試データを見ていると、倍率が2倍以下であるケースが意外と多いことに気付くと思います。出願要件が非常に厳しい、あるいは本部が首都圏にあるだけで実際に通うキャンパスは首都圏外にある学部であるといった特殊な事情が介在するケースもあるのですが、倍率が低いということは、単純に競争率は低いことには変わりありません。
ただし、倍率が低い=誰でも合格できるというわけではない点には注意が必要です。総合型選抜は、大学が求める人物像に合致しているか、志望理由書や面接でどれだけ熱意を伝えられるかといった「質」の勝負になるため、出願者の準備レベルが総じて高い傾向にあります。そのため、見かけの数字よりも競争を厳しく感じることもあります。
出願の詳細を確認し、自身の希望と合うようであれば大きなメリットのある出願先と言えるでしょう。さらに、過去の募集要項や合格者の傾向を調べ、大学がどのようなタイプの学生を評価しているかを把握しておくと、合格の可能性をより高めることができます。
評定が低くても出願できる場合がある
同じく推薦の一形式である学校推薦型選抜では、評定が大きく影響する場合がほとんどを占めます。そのため、評定平均が足りないために、推薦での進学をあきらめることになる場合もあるかと思いますが、総合型選抜を実施している大学の学部・学科によっては、出願において評定を問わない入試方式を設けている場合があります。評定以外にアピールポイントがしっかりとあるのであれば、出願を検討する価値があります。
総合型選抜の「評定」に関して詳しくは下記もご参考にしてください。

将来の就職活動に活かせる
総合型選抜の対策や準備は、自分自身を分析しながら、強みや弱み、それまでの課外活動や取得している資格などを含めた掘り下げを行いつつ、自分自身が志望校に適していることを明確に伝えることが必要です。
このような取り組みは、就職活動時に、自身が志望する企業に貢献できることを効果的に伝えられることと重なる部分が多く、かなり早い段階からその土台を構築しておくことができるという長期的視点でのメリットとなります。
一般入試では問われにくい自己分析やビジョンの言語化などを総合型選抜では重視するため、一般入試との違いとして、社会で求められる力を鍛えられる入試とも言えます。
自分に合う学びを深められる進学先を選べる
総合型選抜では、志望理由書の作成や面接対策などを通じて、自身が何に関心があるのか、何を学びたいのか、どのような将来ビジョンを描いているのかを明確にした上で進学先を選ぶ流れとなるため、入学後の学びがより深く主体的なものになりやすい傾向があります。
一般選抜に比べて大学のカリキュラムや研究環境を詳しく調査する機会が多くなるため、例えば臨床心理士を目指していなくても心理学を学びたい人が、他学部の科目履修のハードルが低い大学の法学部や経済学部を志望するなど、自分の興味と将来のキャリアを両立させる選択がしやすくなります。
ただし、就職市場では依然として大学の偏差値や知名度が評価される現実もあるため、自分の学びたい内容と大学のステータスのバランスを考慮することも重要です。総合型選抜では、こうした多角的な視点から進学先を選ぶことができるのがメリットと言えるでしょう。
年内に受験を終えられる可能性も高い
特に私立大学の総合型選抜において、早ければ10月から11月上旬に合格発表が行われる大学もあり、年内に進路を確定できる可能性が高いことも大きなメリットと言えます。
一般的には、多くの受験生が年明けに緊張感の高まる受験直前期を迎えますが、総合型選抜ですでに進路が確定していれば、そのようなプレッシャーに向き合うことなく、自分なりに更に学問を深めたり、留学やフィールドワークをする為の費用を稼ぐためにアルバイトをしたり、さらには大卒レベルの資格取得の為の勉強や国家総合職・マスコミ等の難関とされる就職先への就活準備の時間に充てたりすることが可能になります。
一般入試と併願すれば受験機会を拡大できる
一般選抜と総合型選抜という異なる形式で併願することで、単純に受験する機会を拡大させることができ、合格を手にするチャンスを広げることが可能になることも大きなメリットと言えます。
それぞれの入試形式において求められることが異なるため、その分、準備すべきことも多く負担となりますが、それらを上手く取り組めるのであれば、志望大学への合格により近づくことができるでしょう。
好きなことや得意なことを活かした受験ができる
総合型選抜では、これまで熱中して取り組んできたことや得意分野を活かして受験に挑むことができます。一般選抜では科目ごとの学力が重視されるため、学習内容に興味が持てない場合は苦しい受験になりがちですが、総合型選抜では自分が本当に好きな活動や経験をもとに志望理由を組み立てられるため、受験そのものが前向きな体験になりやすい傾向があります。
好きだからこそ積み上げてきた実績やエピソードを言語化し、大学でどのように学びに活かしたいかを伝えるプロセスは、主体性や行動力のアピールにもつながります。また、自分の将来像を描いた上で進路を選ぶため、入学後も高いモチベーションを保ちやすく、学びへの姿勢も自然と能動的になりやすくなります。
総合型選抜のデメリット
一方で、総合型選抜には対策の難しさや準備期間の長さなど、注意すべき点もあります。ここでは、受験生が見落としがちなデメリットやリスクを整理し、受験前に知っておくべき現実的な課題を紹介します。
正解がわかりにくく対策が難しい
総合型選抜は、明確な正解が存在しない入試形式であるため、対策が難しいと感じる受験生も少なくありません。一般選抜のように点数で評価されるわけではなく、志望理由書や面接、プレゼンテーションなどを通じて自分をどのように伝えるかが重要になるため、何をどこまで準備すればよいのか判断しづらく、一人で進めるのが不安になることがデメリットとして挙げられます。
また、大学によって重視される評価基準が異なる点も難しさの一つです。ある大学では「学問への探究姿勢」を重視する一方で、別の大学では「課外活動でのリーダーシップ」や「地域貢献」を高く評価するなど、大学ごとに求める人物像が異なります。そのため、同じ内容の志望理由書を複数大学に提出しても十分な評価を得られない場合があります。
こうした難しさに対応するため、各大学のアドミッション・ポリシーを丁寧に読み込み、大学が何を重視しているのかを把握することが大切です。また、専門的な指導を受けられる塾や予備校を活用することもおすすめです。
早期からの対策が求められる
総合型選抜は、出願時期が一般選抜よりも早く、高校3年生の9月頃に出願を受け付ける大学が多く見られます。なかには、6月中にエントリーが必要な大学もあるため、進路を決めるタイミングも早まります。
そのため、総合型選抜を目指す場合は、できるだけ早い段階から志望理由の整理や活動実績の蓄積を意識することが重要になります。ただし、出願期限に間に合わせることだけを目標にするのは危険です。十分な準備をせずに出願しても、書類審査で不合格になるだけでなく、その間の精神的負担や不要な対策に費やした時間が一般選抜の準備にも悪影響を及ぼす可能性があります。
勉強時間の配分が難しくなる
総合型選抜は、書類作成や面接対策などに多くの時間と労力を要するため、特に高校3年の夏は準備のピークを迎えます。私立大学では9月上旬から出願が始まり、10月には本格的な選考が行われるため、この時期は総合型の対策に集中せざるを得ません。
その一方で、一般選抜も視野に入れておく必要があるため、2つの受験方式を並行して進める受験生が多く見られますが、総合型対策に時間を割く関係上、バランスを取ることが難しくなりがちです。特に英語・数学などの主要科目の学習量が減ってしまい、一般選抜の模試で成績が下がるケースもあります。
合否結果を待ちながら一般選抜向けの準備も続けなければならず、精神的・体力的な負担が大きくなる点は注意が必要です。可能であれば、高校2年のうちから総合型を意識して準備を始めておきましょう。3年の秋以降の学習バランスを取りやすくなります。早期に志望理由を整理し、共通科目の基礎学力も維持して、どちらの入試にも対応できる体制を整えておくと安心です。
高校で孤独になる可能性もある
総合型選抜を選ぶ生徒は年々増加していますが、高校内では、一般選抜や指定校推薦を目指す生徒が大多数を占める場合もあります。そのため、周囲が一般入試に向けての準備を進める中で、一人だけ早い時期に出願や面接対策に取り組んでいると、孤立感を抱きやすくなります。
特に9月から10月にかけての入試本番の時期には、まだ学校全体が受験ムードに入っていないことも多く、自分だけが直前期の緊張感にさらされている状況は、精神的な負担につながることもあります。
こうした環境の違いから孤独を感じやすい点は、総合型選抜の隠れたデメリットの一つと言えるでしょう。しかし、同じ入試方式を目指す仲間と励まし合い、専門塾の講師から情報を得ることで、孤立感は軽減するでしょう。個別指導型の専門塾であれば、講師と二人三脚で集中して取り組むことができ、迷いや不安を感じる時間を最小限にできます。
総合型選抜で注意するべきよくある誤解
「総合型選抜は誰でも受かる」「勉強しなくてもいい」といった誤解は少なくありません。そうした誤ったイメージを払拭し、実際に合格をつかむための大切な要点を知っておきましょう。
「学力が不要だ」と誤解しない
総合型選抜は筆記試験の比重が小さいものの、基礎学力が不要というわけではありません。志望学部に関する知識や、教養をもとに論理的に考える力は面接や小論文で問われます。
入学後の学習についていくためにも、主要科目の復習や読解力・表現力の鍛錬を並行して続けることが大切です。
合格後も学力維持は不可欠
早期に合格を得た場合でも、学習を止めてしまうと大学入学後に授業についていけないリスクがあります。
総合型選抜では意欲や適性が評価されますが、入学後は高度な専門学習が待っています。合格後こそ、基礎科目の復習や課題研究の継続など、学ぶ姿勢を保つことが将来の力になります。
出願条件・提出書類を軽視しない
総合型選抜では、大学ごとに細かな出願条件や提出書類の形式が異なります。志望理由書や活動報告書など、提出形式の不備があると選考対象外になることもあるため注意が必要です。
募集要項を早めに確認し、学校や専門指導者にチェックしてもらうなど、書類面での準備を怠らないことが合格への第一歩です。
総合型選抜は国公立でも実施されている?
総合型選抜は私立大学だけでなく、国公立大学でも広く導入されています。ここでは、国公立での実施例や私立との違い、注意すべきポイントを取り上げます。
国公立大学での実施例と特徴
近年では、東京大学の「推薦入試」や京都大学の「特色入試」をはじめ、大阪大学・東北大学・九州大学・筑波大学など、多くの国公立大学で総合型選抜が導入されています。
評価内容は大学によって異なりますが、研究意欲・地域貢献・探究活動の成果などを重視する傾向が強く、書類審査や面接に加え、共通テストやプレゼンテーションを課す大学もあります。単なる人物評価ではなく、学力と意欲の両面をバランスよく見る点が国公立型の特徴です。
私立大学との違い(倍率・評価基準など)
私立大学の総合型選抜は倍率が高く、独自の小論文やプレゼンを重視するケースが多い一方、国公立は比較的倍率が低く、学力・意欲・社会性の総合評価を行う傾向があります。
また、私立では面接の自由度が高いのに対し、国公立は評価基準がより明確に設定されており、学問的な適性が重視されるのが特徴です。
国公立を目指す人が注意すべきポイント
国公立大学の総合型選抜は、共通テストと出願書類の両方に対応する二重の準備が必要です。一般選抜よりも出願時期が早いため、早期に志望分野を明確にし、活動記録を整理しておくことが欠かせません。
さらに、評価の対象となる探究テーマや研究計画書の内容を深め、「なぜこの大学・学部で学びたいのか」を明確に示すことが合格の鍵です。
総合型選抜をおすすめする人・向いている人
総合型選抜に向いているのは、目的意識がはっきりしており、自分の強みを言葉で伝えられるタイプの受験生です。ここでは、総合型選抜に向いている人の特徴を具体的に紹介します。
特定の分野で秀でた才能や実績がある人
スポーツ、芸術、研究活動など特定の分野で優れた経験や実績を持つ人は、まさに総合型選抜に向いている人の典型です。従来の学力試験だけでは測れない能力が評価の対象となるため、自分の得意分野を武器にした受験が可能になります。
自分の学びたい分野が明確で熱意がある人
将来の目標や学びたい分野が明確な人は、総合型選抜に向いています。志望理由を深く掘り下げ、自分の意欲やビジョンを伝えることで、高い評価を得られる可能性があります。
面接やプレゼンが得意な人
自己表現力に自信がある、または、対話の中で自分の考えを上手く伝えることが得意な人は、総合型選抜でその力を発揮しやすい傾向にあります。面接やプレゼンテーションを評価対象としている大学の学部・学科は多いため、口頭で的確にアピールできるスキルは非常に有利となります。
一般選抜では評価されにくい強みを持つ人
成績や偏差値ではなく個性や独自の社会経験などを持つ人にとって、総合型選抜は自分を正当に評価してもらえる貴重な機会となります。高校生活での活動や実績を重視するため、一般選抜では評価されない対象が評価に繋がり、合格を勝ち取る可能性は十分にあると言えます。
総合型選抜をおすすめしない人・向いていない人
総合型選抜は、すべての受験生に最適な入試方式ではありません。ここでは、そんな受験生のタイプを紹介します。
一般選抜で十分合格できる学力がある人
模試で安定して高い判定が出ているなど、一般選抜で十分に合格圏内にある学力を持っている場合は、無理に総合型選抜を選ぶ必要はありません。特に国公立大学では今も多くの枠が一般選抜に割かれており、学力で勝負する方が効率的なケースもあります。
総合型選抜の対策には時間と労力が必要なため、その分、一般選抜の学習がおろそかになってしまうリスクもあります。確実に学力で合格を狙えるなら、一般選抜に専念する選択も非常に効果的と言えます。
さらに、一般選抜で上位の成績(首席や次席レベル)で合格した場合、大学入学後も教員から注目されやすく、学業面での評価にもプラスに働く傾向があります。また、多くの大学では優秀な一般選抜合格者を対象に学費減免制度や奨学金制度を設けており、総合型選抜合格者が対象外となっているケースも少なくありません。学力に自信がある場合は、大学での学業の充実と経済的負担の軽減の両面から考えても、一般選抜での上位合格を目指す方が長期的には効率的でしょう。
学校の成績が極めて高く、指定校推薦で進学できる人
評定平均が非常に高く、5.0に近いような成績を維持している場合は、総合型選抜よりも指定校推薦を活用した方が、確実性が高いケースもあります。
総合型選抜は評価基準が多面的で不確定要素も多いため、成績を武器に確実な合格を目指せる指定校推薦の方が合理的な選択になることもあります。特に総合型選抜を導入して間もない大学では、年度間で評価基準にばらつきが生じることもあり、予測が難しい場合があります。
該当する成績を持っている場合は、あえて総合型を選ばなくても十分に希望の進学先を狙える可能性があるでしょう。
苦労せず楽して大学合格したいと考えている人
総合型選抜は、「一般入試より楽そう」といったイメージを持たれがちですが、実際には十分な準備が求められる入試形式です。自己分析や志望理由書の作成、面接対策、場合によってはプレゼンテーションやディスカッションなど、取り組むべき課題は多岐にわたります。
「何もしなくても受かる」といった誤った考えを持ってしまっている人にとっては、想像以上に大変だと感じる流れになる可能性が高いです。むしろ総合型選抜は、「自分の経験や考えをどう表現するか」を問う入試であり、勉強とは異なる意味で深い準備が必要です。思考力・表現力・課題発見力といった力を高める過程そのものが評価の対象となります。
楽をしたいという気持ちだけで臨むには不向きな入試方式です。早い段階で自分の強みを言語化し、指導者と相談しながら準備を進めていくことが重要です。
総合型選抜で失敗しないためのポイント
制度を理解していても、準備不足や情報の見落としによって失敗するケースは少なくありません。ここでは、総合型選抜を成功に導くための注意点や、受験計画の立て方を紹介します。
募集要項で「専願・併願可否」を必ず確認
大学によっては、総合型選抜で出願した場合に他大学との併願ができない「専願制」を採用している場合があります。これを見落とすと、ほかの受験機会を逃すリスクもあるので要注意です。
必ず募集要項を読み込み、出願条件・併願可否・提出書類の締切を早めに確認しましょう。学校の先生や専門塾に相談してスケジュールを整理しておくことが重要です。
志望理由書・面接・活動報告書は「一貫性」が鍵
総合型選抜では、志望理由書・面接・活動報告書の内容が相互に矛盾していないかが重視されます。「なぜこの大学なのか」「将来どう社会に貢献したいのか」など、軸を一本に通すことが合格への近道です。
また、表現の統一やエピソードの信頼性も重要です。専門塾の講師など第三者にチェックを受けて、説得力ある自己PRに仕上げましょう。
一般選抜と併願してリスクを分散
総合型選抜は評価の幅が広いため、必ずしも努力が結果に直結するとは限りません。そのため、一般選抜や学校推薦型選抜を併願し、複数の受験機会を確保しておくことが現実的な戦略です。
スケジュール管理が難しい場合は、早めに出願日程を洗い出し、無理のない学習計画を立てることが重要です。
早期対策・専門サポート塾の活用も有効
出願時期が早く対策期間が短いため、総合型選抜は高校2年生のうちから準備を始めるのが理想的です。
志望理由書の添削や面接練習、小論文の指導などを専門的にサポートする塾を活用することで、効率的に対策が進められます。志望理由書・小論文・面接まで一貫サポートが可能な塾で対策しましょう。
総合型選抜のメリット・デメリット まとめ
総合型選抜は従来の学力試験だけでは測れない個性や経験を活かせる入試形式であり、早期に受験を終えられる可能性がある点や、自分に合った進学先を主体的に選べる点など、多くの魅力があります。一方で、正解の見えにくさや早期の準備の必要性、一般選抜との併願による負担といったデメリットも存在します。
総合型選抜は自分の経験や将来の目標を丁寧に言語化し、それを大学に伝える力が問われる入試です。「総合型選抜はどのような人が受かるのか」という問いに対しては、単なる実績だけでなく、自分の意欲や適性をどのように伝えられるかが大きなカギになると言えるでしょう。自分がどのような強みを持ち、どのような環境で学びたいのかを丁寧に見つめ直すことが総合型選抜を活かすための第一歩であり、その上で、最適な対策を講じることが欠かせません。
総合型選抜は独学で進めるにはハードルが高く、一般選抜のように体系的な情報や教材が整備されているわけではありません。そのため、志望校の学部・学科ごとの特色に合わせた対策を行える専門塾、特に個別に対策を講じられる指導スタイルのサポートの検討も効果的です。
トライなら、志望校ごとの出願書類・面接・プレゼン対策まで、一人ひとりの強みを引き出す個別指導が可能です。独学では見落としがちなポイントを徹底的にサポートし、合格に向けて最短ルートで伴走します。
自分の可能性を最大限に引き出すためにも、メリット・デメリットの両面を正しく理解した上で、最適な準備を進めていきましょう。




合格へ導く4つのステップ
圧倒的な合格実績を生み出す、
他塾にはない徹底的なサポート
年間カリキュラム
の作成

目標とする志望校や現在の思考力レベルから、合格のために個別の専用カリキュラムを作成します。また、志望大学や興味のある学問から、併願校受験の戦略も提案します。
コーチング面接
【25コマ】

推薦・総合型選抜に特化した専門コーチが入試対策をサポートします。面談の際には生徒の将来像や志望理由の深掘りを徹底的に行い、より深みのある志望理由の完成に導きます。(質問対応も可)
動画コンテンツ
の視聴

推薦・総合型選抜の合格に必要な能力や対策方針をプロ講師が解説します。入試に精通したプロの目線でエッセンスを伝えますので、合格のためにすべきことが明確になります。
添削サポート
【全10回】

出願書類や小論文など、大学別に必要な書類を専門チームが添削しアドバイスします。執筆・添削・書き直し、という工程を繰り返すことで、書類の完成度を着実に高めます。
志望校に特化した
オーダーメイドの対策が可能です!