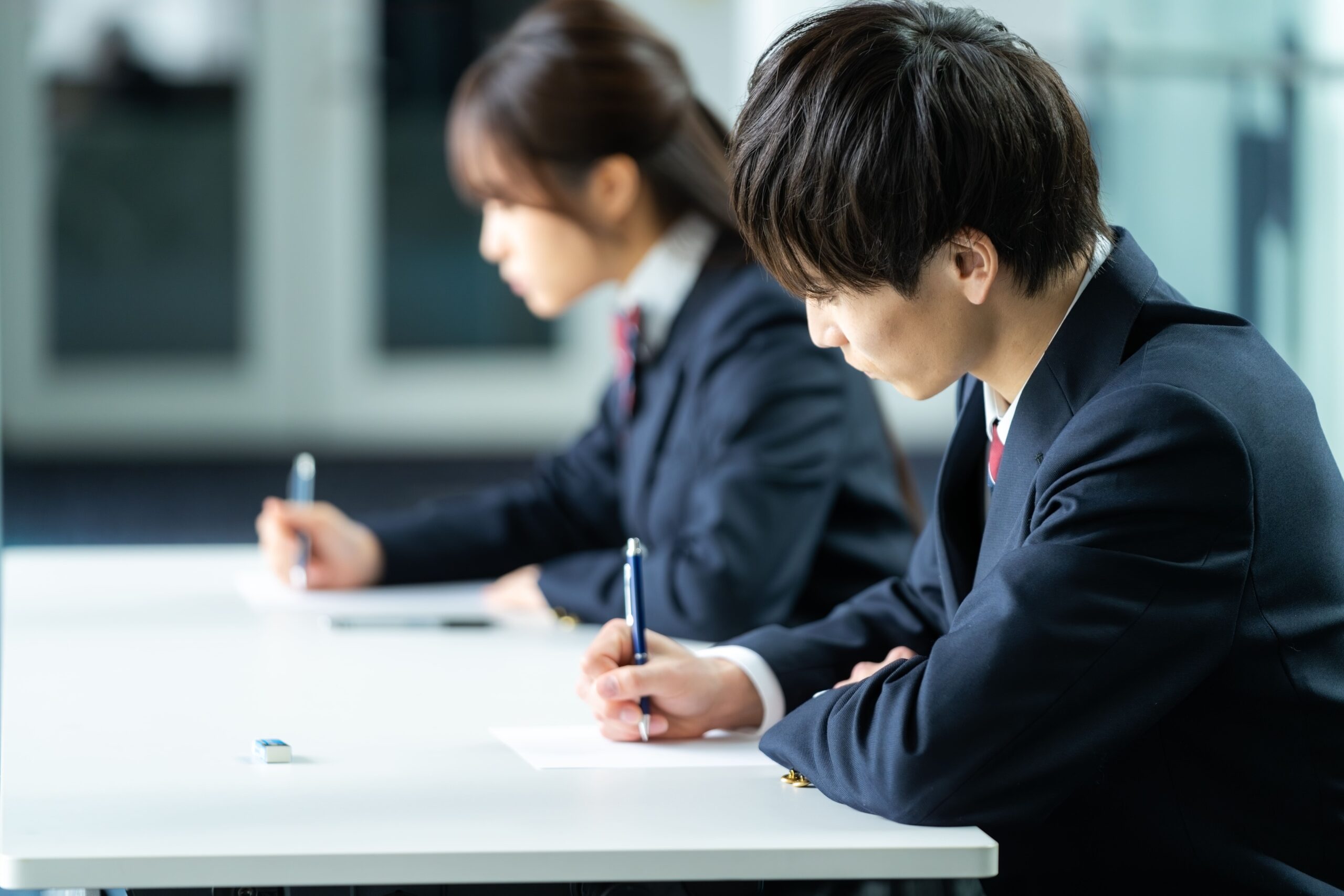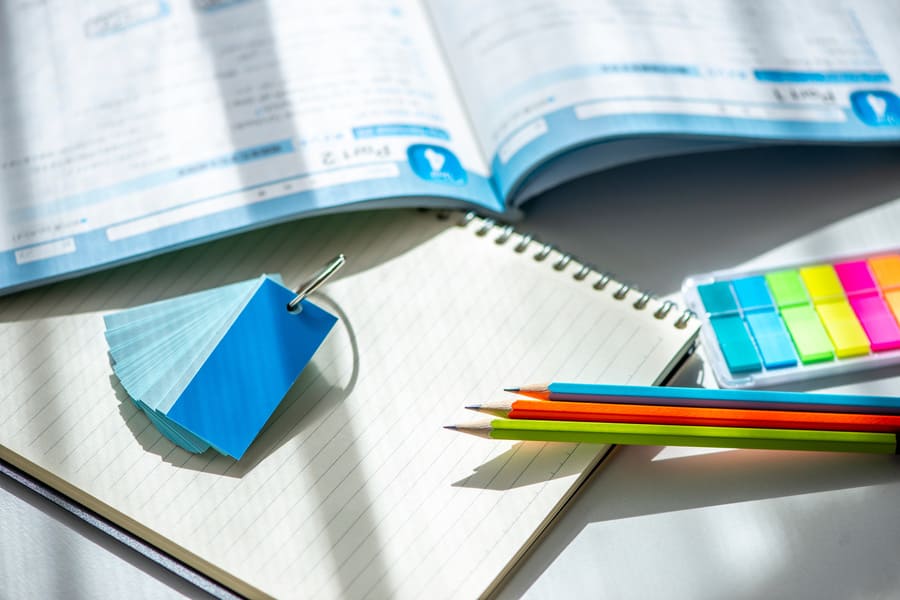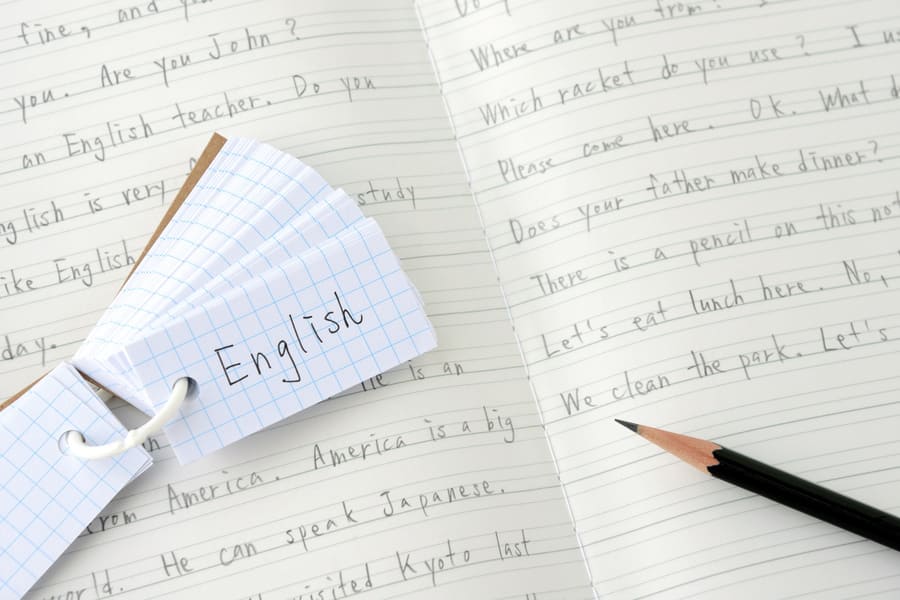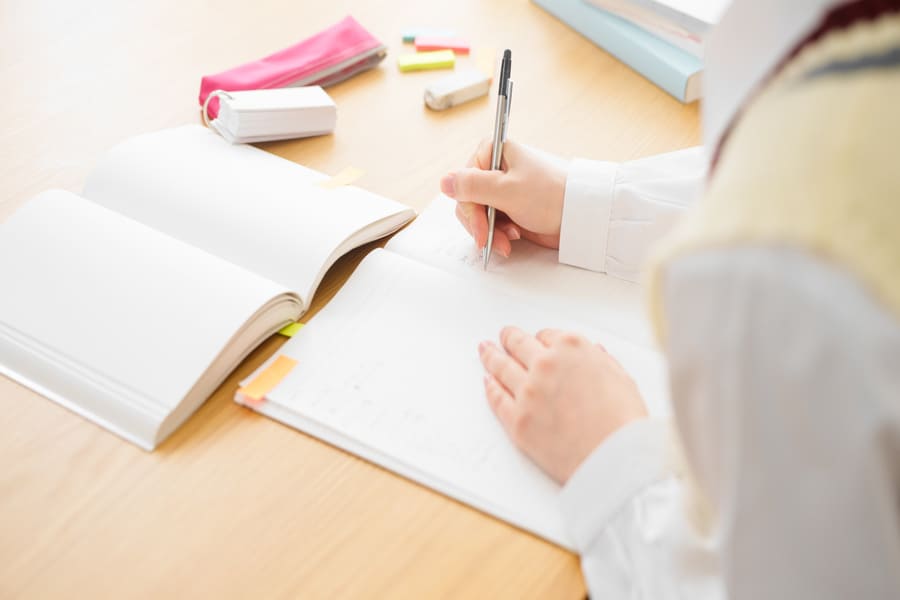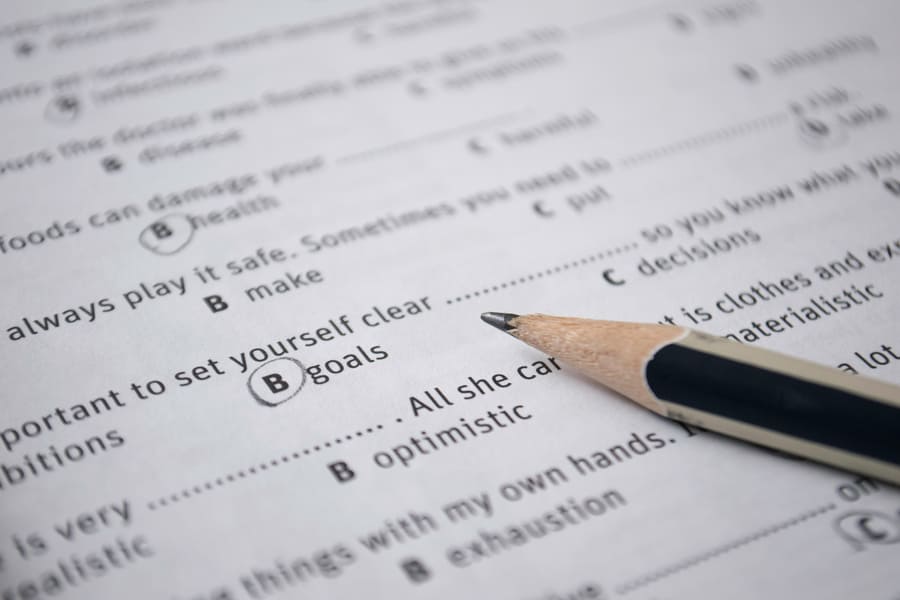模試の結果がD判定でも、すぐに諦める必要はありません。
模試の判定に一喜一憂してしまう受験生は多いもの。しかし、模試はあくまで「今の実力」を測る指標にすぎず、「合否そのもの」を決めるものではありません。
実際、D判定からの逆転合格を果たした先輩たちは数多く存在します。重要なのは、結果にとらわれすぎず、状況を冷静に見極めながら最後まで努力を続けることです。
本記事では、模試でD判定が出たときに志望校を変えるべきかどうかの判断ポイントや、逆転合格を目指すための勉強法について詳しく解説します。
トライのオンライン個別指導塾では、完全マンツーマン形式で一人ひとりに合わせたオーダーメイドのカリキュラムを作成します。
わからない部分はその場で質問できるため、苦手をそのままにせず、着実に学力を積み上げることが可能です。「D判定からでも合格を目指したい」「自分に合った学習方法で確実に力をつけたい」という方は、ぜひトライのオンライン個別指導塾にご相談ください。
\トライのオンライン個別指導塾について詳しくみる!/
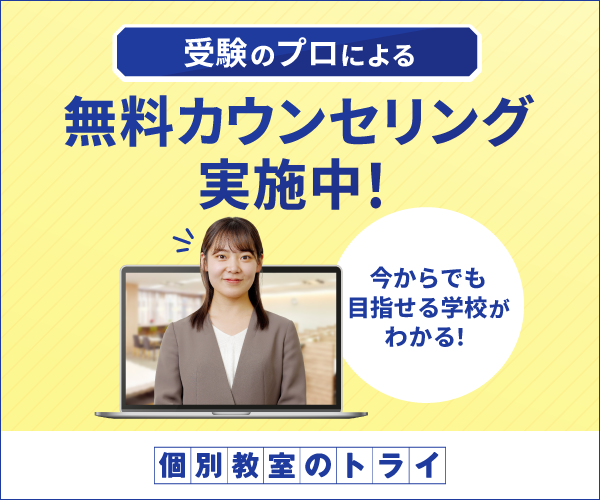
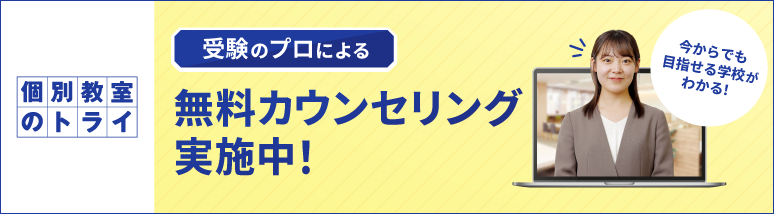
この記事の目次
模試でD判定が出ても志望校は変えなくて大丈夫?まずは合格率をチェック

D判定が出ても、必ずしも志望校を変える必要はありません。前提として模試の結果は、AからEまでの5段階で合格可能性を示します。
- A判定:合格可能性80%以上
- B判定:合格可能性60%~80%
- C判定:合格可能性40%~60%
- D判定:合格可能性20%~40%
- E判定:合格可能性20%以下
D判定の合格可能性は「20%〜40%」とされており、決して楽観視できる数字ではありません。しかし、まだ逆転のチャンスは残されています。
特に高1〜高3の夏頃までのD判定であれば、志望校変更を考えるよりも、まず「どこをどう伸ばすべきか」の戦略を立てることが重要です。
模試でD判定が出たときに志望校を変えるか決める判断ポイント

模試でD判定が出ると、「志望校を変えた方がいいのでは」と不安になる方も多いでしょう。確実に合格を目指すなら、志望校の見直しも一つの選択肢です。
ただし、模試の判定は「現時点」の成績によるものであり、今後の努力次第で十分に挽回は可能です。
そして、志望校を変えるべきかどうかは、模試がD判定だった時期や入試内容によっても異なります。志望校を変えるか決めるときの判断ポイントは、以下のとおりです。
- 高1〜高3夏までは合格の可能性が十分残っている
- 高3秋はそれまでの成績の動き方で判断する
- 入試の内容に大きな差がない場合は共通テスト後に決める
以下で、それぞれのポイントについて詳しく解説します。安易に諦めず、冷静に分析して進路を考えましょう。
高1〜高3夏までは合格の可能性が十分残っている
高1〜高2の段階で模試の結果がD判定だったとしても、過度に不安になる必要はありません。
この時期はまだ受験勉強が本格化しておらず、学校の授業や部活動との両立に精一杯で、学習まで手が回らないことも多い時期です。
そのため、模試の成績が振るわないのは珍しいことではなく、今後の努力次第で挽回が可能です。
ただ、勉強に時間を割いているにもかかわらず成績が振るわないのであれば、勉強方法や勉強時間の配分を見直すことも検討しましょう。
特に基礎学力がしっかりとついていけば、高3以降の応用問題や演習にも対応できる可能性があります。
また、高3の夏にD判定が出た場合でも、焦る必要はありません。
たとえば、もしこれまで暗記科目を中心に取り組んでいたのであれば、秋以降に演習や過去問対策に力を入れることで得点力が伸びるかもしれません。
判定に一喜一憂するのではなく、自分に何が足りていないかを冷静に分析し、適切な対策を取ることが大切です。
高3秋はそれまでの成績の動き方で判断する
高3の秋に受けた模試でD判定が出た場合は、すぐに志望校を変えるのではなく、これまでの成績の推移をもとに冷静に判断しましょう。
たとえば、夏以降に成績が上向いてきている中でのD判定であれば、今後の伸びしろに期待できるため、引き続き志望校を目指して学習を続けると良いでしょう。
一方で、「以前はC判定やB判定だったのに、最近になってD判定に落ちてしまった」というように、成績が下降傾向にある場合は注意が必要です。
学習方法や生活習慣、苦手科目の放置など、何かしらの原因がある可能性があります。早急に原因を分析し、対策を講じましょう。
高3秋は、受験直前期の学習方針を固めるうえで非常に重要な時期です。成績の動きを丁寧に振り返ることで、より現実的な進路選択ができます。
入試の内容に大きな差がない場合は共通テストの結果や合否状況を見て決める
志望校同士で入試科目や出題傾向に大きな差がない場合は、共通テストの結果や、その時点での合否状況を見て判断することも有効です。
国公立大学志望の場合、共通テストの得点率から志望校を検討できます。
また、基礎学力テスト型入試など年内に合否が発表される形式を利用すれば、状況を見てどの大学に出願するか判断できることがあります。
入試シーズンに入ってから、思わぬ得点の伸びが起こることもあります。そのため、早い段階で目標を下げるのは早計かもしれません。
まずは第一志望に集中して対策を進めつつ、併願校や出願戦略も事前に準備しておきましょう。
D判定からの志望校合格を実現させる5つの勉強法

先述のとおり、D判定が出ても志望校合格は決して不可能ではありません。大切なのは、これからの勉強の取り組み方です。
D判定から逆転合格を目指すために優先して実践したい5つの勉強法を紹介します。
- 徹底的に基礎固めを行う
- 目標から逆算した学習計画を立てる
- 模試の結果を細かく分析する
- 重点的に取り組む勉強の優先順位をつける
- 志望校の過去問演習を繰り返す
志望校を諦めたくない人は、ぜひ実践してみてください。
1.徹底的に基礎固めを行う
模試でD判定が出た場合、各科目の基礎的な知識や解法が十分に定着していない可能性があります。
特に模試では、教科書レベルの基本問題が確実に解けるかどうかが成績に大きく影響します。
まず、英単語や古文単語、公式や定理の暗記など、覚えるべき知識を着実に身につけましょう。
基礎問題を何度も繰り返して「確実に解ける」状態にしておくことで、徐々に応用力も伸びていきます。
基礎が不安定な状態でいきなり応用問題に取り組んでも、得点にはつながりません。まずは教科書や基礎問題集を使って土台をしっかり固めましょう。
2.目標から逆算した学習計画を立てる
D判定から志望校合格を目指すには「目標から逆算した学習計画」を立てることが重要です。
まずは「志望校に合格する」というゴールを明確にし、そこから必要な得点力や科目別の課題を洗い出します。
そのうえで、1ヶ月・1週間単位といった短期目標を設定することで、日々の学習にメリハリが生まれ、今やるべきことが明確になります。
たとえば、「今月は英語の長文読解を重点的に」「今週は古文単語を100個覚える」といった具体的な目標を持つことで、計画的に成績を積み上げられるでしょう。
家庭教師のトライではお子さまの目標・学力に合わせたオーダーメイドのカリキュラムを作成

参照:家庭教師のトライ – 満足度No.1約33万人教師からあなたに最適な家庭教師をご紹介
家庭教師のトライでは、お子さま一人ひとりの目標や現在の学力に合わせて、完全オーダーメイドのカリキュラムを作成します。
得意・不得意科目のバランスや、志望校の出題傾向に応じた学習プランを組むことで、効率的な学習が可能です。
D判定からの逆転合格を目指すためには、「今やるべきこと」を明確にし、着実に実力を積み上げることが重要です。
トライでは経験豊富な教師がマンツーマンで指導を行い、お子さまの理解度に応じて柔軟に内容を調整します。
さらに、定期的な進捗管理と学習相談により、学習習慣の定着やモチベーションの維持もサポート。
どの時期からでも、志望校合格を諦めたくないお子さまを全力でサポートします。
3.模試の結果を細かく分析する
D判定から志望校合格を目指す上で、模試の結果を細かく分析することは欠かせません。
模試は単なる判定を知るためのものではなく、自分の状況を把握することで、学習の軌道修正を行うためのものです。
どの教科で何点取れているか、どの大問で点数を落としているかを確認し、得意・不得意分野を具体的に洗い出しましょう。
たとえば、英語の文法問題は正解しているのに長文で失点している場合は、読解対策に重点を置くなど、結果を学習計画に直結させることで効率的に弱点を克服できます。
また、時間配分やケアレスミスといった要素も分析の対象です。こうした丁寧な振り返りが、次の模試や本番での得点力アップにつながります。
4.重点的に取り組む勉強の優先順位をつける
D判定から志望校合格を目指すには、限られた時間を活用するためにも、勉強の優先順位を明確にすることが大切です。
すべての教科を同じ比重で勉強しようとすると、時間が足りなくなり、かえって成績が伸び悩むこともあります。
まずは志望校の入試で配点の高い教科や、合格に直結しやすい科目を確認しましょう。
次に、模試の結果や過去問演習をもとに、自分の中で基礎が定着していない科目を把握し、重点的に学習することで効率的に得点アップを狙えます。
たとえば、苦手な数学が入試で高配点なら、早めに克服しておくことで全体の得点力が大きく上がります。
やみくもに手を広げず、「今どの科目・単元を伸ばせば一番効果的か」という優先順位を意識した学習が、逆転合格のポイントです。
5.志望校の過去問演習を繰り返す
基礎固めが一通り終わったら、入試対策の問題集で実戦演習を行いましょう。
大学入試では、基礎知識を実際の問題で応用する力が問われるため、問題演習を通じて解答力を鍛えることが重要です。
問題集での練習を重ね、解法パターンが身についてきたら、志望校の過去問に挑戦します。
過去問を解くことで、自分の実力を客観的に把握できるだけでなく、出題傾向や時間配分、問題の難易度にも慣れることができます。
その上で、「どの部分で点が取れていないのか」「どの形式に弱いのか」を具体的に知ることが大切です。
過去問は1回解いて終わりにするのではなく、間違えた箇所の復習を繰り返すことで、解き方のパターンや出題意図が見えてきます。
何度も取り組むうちに得点力が安定し、自信にもつながるでしょう。不安なく本番に臨むためにも、早めに過去問に着手し、継続的に活用することが効果的です。
D判定からの逆転合格には塾・家庭教師の利用がおすすめ!メリット・デメリットを紹介

D判定からの逆転合格を目指すなら、塾や家庭教師の活用も有効です。
特に以下の3つの学習スタイルには、それぞれ異なるメリットとデメリットがあります。
- 集団塾
- 個別指導塾
- 家庭教師
それぞれの特徴を理解し、自分に合ったスタイルで受験対策を進めることが合格への近道です。
以下で、それぞれのメリットとデメリットを詳しく見ていきましょう。
集団塾
集団塾は、「ある程度自分で勉強のペースを作れる人」「周囲と競い合いながら成長したい人」「一人ではサボってしまうタイプの人」に特に向いています。
集団塾の大きなメリットは、周囲の生徒と切磋琢磨できる環境にあります。競争意識が刺激となり、モチベーションを高く保ちながら学習を進められるのが強みです。
一方、授業の進度が全体に合わせられているため、自分の理解が追いつかないときに質問しにくい、苦手分野を集中的に補強しづらいといったデメリットもあります。
個別指導塾
個別指導塾は、「自分のペースで学習を進めたい人」「特定の教科や分野を重点的に強化したい人」「集団での学習が苦手な人」に向いています。
個別指導塾のメリットは、生徒一人ひとりに合わせた指導が受けられる点です。
理解度や学習ペース、志望校に応じて柔軟に内容を調整できるため、苦手分野の克服や基礎からのやり直しにも適しています。
また、質問しやすい環境が整っており、わからない部分をその場で解決しやすいというメリットもあります。
ただし、講師との相性や指導力に左右されることがあるほか、集団塾に比べて費用が高くなりやすい点がデメリットです。
家庭教師
家庭教師は、「自分に合ったペースで落ち着いて学びたい人」「周囲の目を気にせず質問したい人」「学習習慣がまだ十分でない人」に特に向いています。
家庭教師のメリットは、自宅でマンツーマンの指導を受けられる点です。
生徒一人ひとりの理解度や学習状況に合わせて授業を進めてもらえるため、苦手な部分を集中的に克服したい場合や、基礎から丁寧に学び直したい場合に適しています。
また、通塾の必要がなく、移動時間がかからない点も大きな魅力です。
一方で、教師との相性が学習効果に直結しやすいほか、料金が比較的高いというデメリットがあります。
家庭教師のトライでは、専任教師と正社員の教育プランナーがf受験勉強を徹底サポート。
一人ひとりに合わせたオーダーメイドのカリキュラムと完全マンツーマン指導で、志望校合格へと導きます。
無料学習相談も受け付けているため「D判定からでも間に合うか不安……」という方は、家庭教師のトライにお気軽にご相談ください。
\家庭教師のトライについて詳しくみる!/
オンライン塾・オンライン家庭教師
オンライン塾・家庭教師は、「時間や場所にとらわれずに学習したい人」「自分に合った教師を全国から選びたい人」「自宅で集中できる環境がある人」に向いています。
オンライン塾・オンライン家庭教師のメリットは、自宅にいながら質の高い指導を受けられる点です。
移動時間が不要で、全国どこにいても自分に合った教師やカリキュラムを選べる柔軟性があります。
特に、近くに通える塾がない場合や、家庭のスケジュールに合わせて学習時間を調整したい人には非常に便利です。
その反面、通信環境の影響を受けやすいことや、画面越しのやり取りでは集中力が続きにくいことがデメリットです。
トライのオンライン個別指導塾では志望校の合格実績が高い教師を全国から選べる
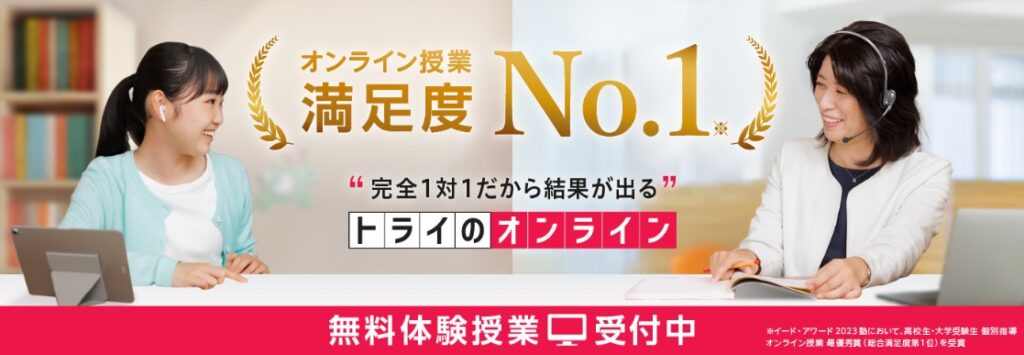
トライのオンライン個別指導塾では、全国から志望校合格実績の高い教師を選べるため、地域にとらわれず最適な指導が受けられます。
志望校の入試傾向を熟知した教師がマンツーマンで指導するため、出題傾向に合わせた的確な対策が可能です。
自宅にいながら質の高い授業を受けられるので、効率よく合格を目指せることはもちろん、対面と変わらないサポート体制により最後までしっかりとサポートを受けられます。
まとめ

本記事では、模試でD判定が出たときに志望校を変えるべきかどうかの判断ポイントや、逆転合格を目指すための勉強法について解説しました。
志望校を変えるか決めるときの判断ポイントは、以下のとおりです。
- 高1〜高3夏までは合格の可能性が十分残っている
- 高3秋はそれまでの成績の動き方で判断する
- 入試の内容に大きな差がない場合は共通テスト後に決める
また、D判定から逆転合格を目指す勉強方法は、以下のとおりです。
- 徹底的に基礎固めを行う
- 目標から逆算した学習計画を立てる
- 模試の結果を細かく分析する
- 重点的に取り組む勉強の優先順位をつける
- 志望校の過去問演習を繰り返す
D判定でも、やり方次第で合格のチャンスは十分あります。
本記事の内容を参考に、焦らず、戦略的に行動していきましょう。