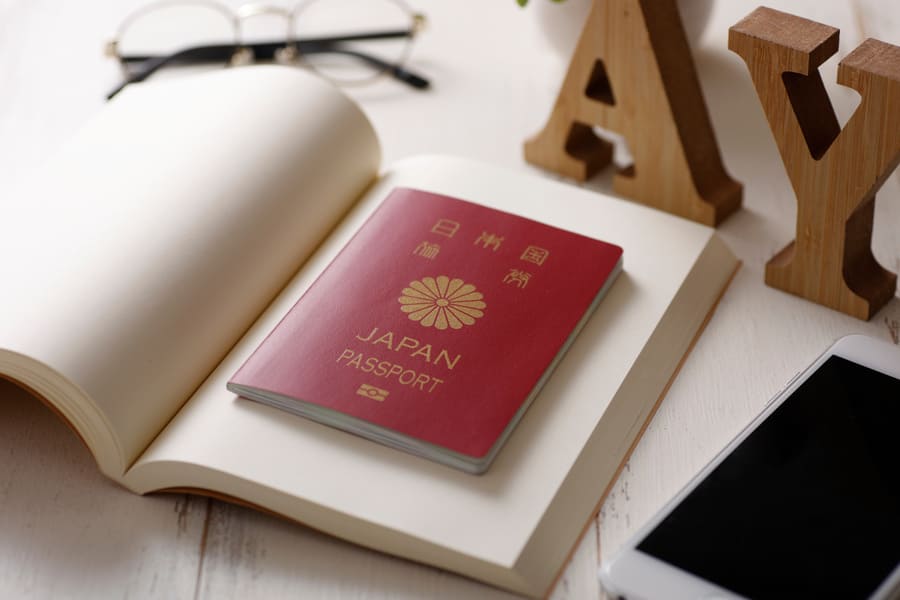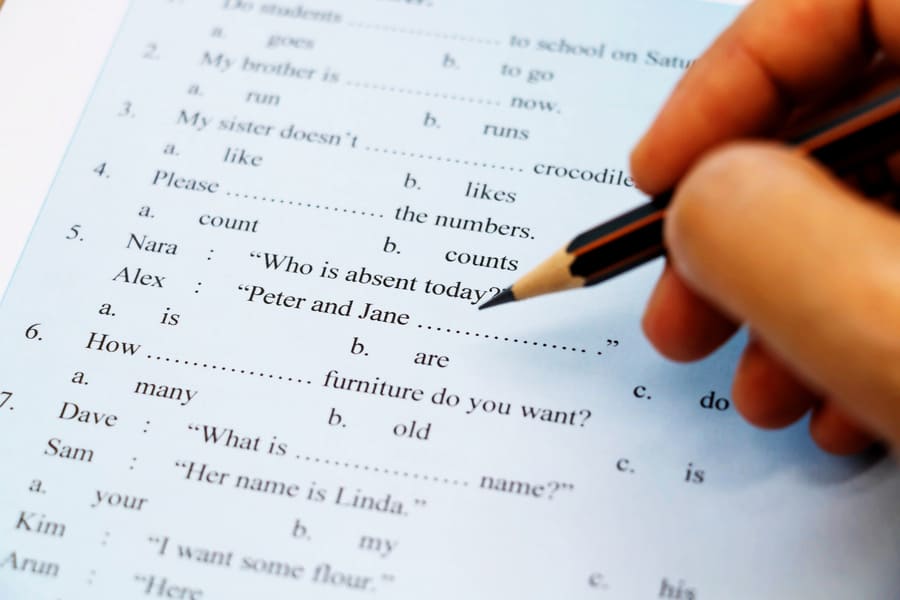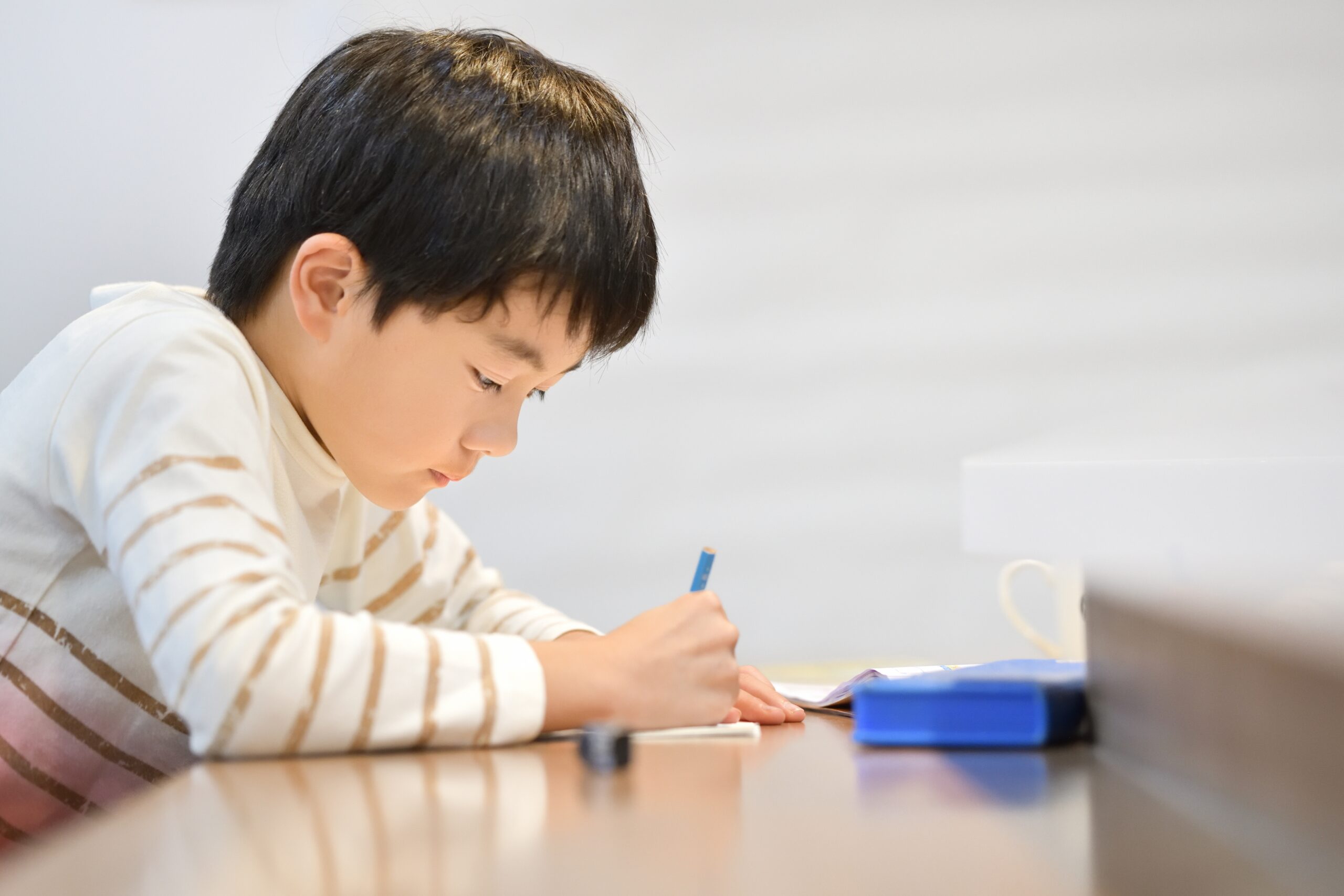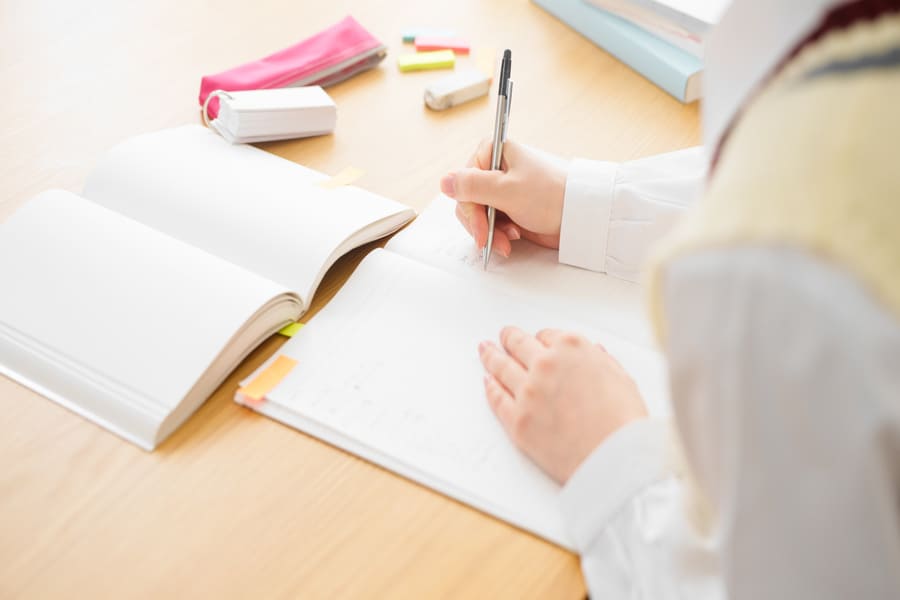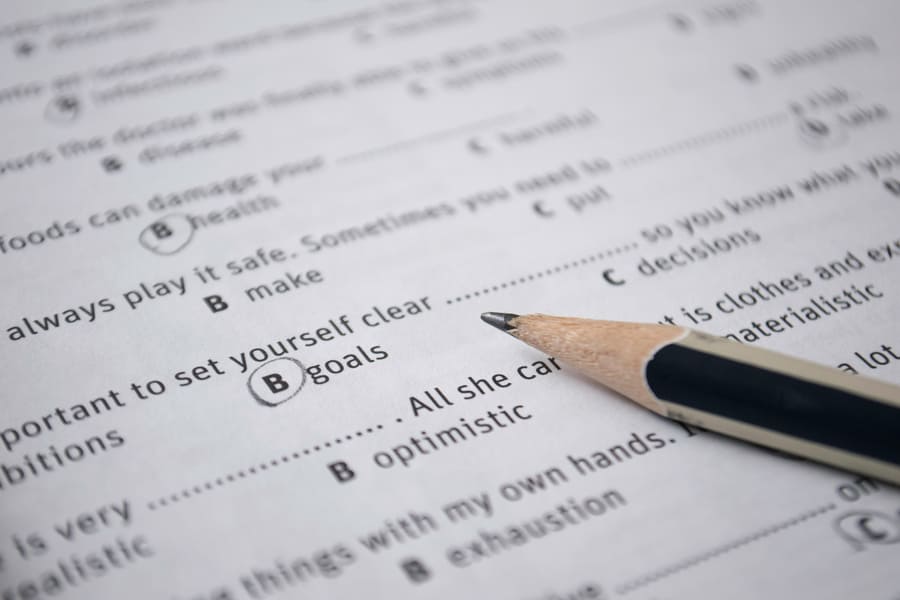「Vもぎを受けようと思っているけれど、どんな模試なのかイマイチわからない」
「Vもぎはいつ頃から、何回受ければ志望校に合格しやすくなるのだろう」
首都圏最大級の高校入試に向けた模擬試験である「Vもぎ」は、年間延べ38万人以上の中学3年生が受験する公開テストです。
しかし、初めてVもぎに挑戦する生徒や保護者の方は、どのように活用すべきか迷うことも多いでしょう。
Vもぎは、志望校のタイプごとに複数の種類があるため、自分の目標に合わせて適切な模試を選ぶことが重要です。
それぞれの特徴を理解し、計画的に学習を進めることで、志望校合格の可能性も高めることができます。
そこで本記事では、Vもぎの基本情報や種類別の特徴、Vもぎのメリットや偏差値を上げるためのコツを解説します。
Vもぎの効果を最大限活かして、高校受験を有利に進めたい方は、ぜひ参考にしてください。
個別教室のトライでは、「Vもぎ」や高校受験に向けて着実に学力を伸ばせるよう、完全マンツーマン授業で徹底サポートします。
「Vもぎの適切な対策方法がわからない」「高校受験に向けてVもぎを有効活用したい」などのお悩みをお持ちの方は、個別教室のトライにお気軽にご相談ください。
\個別教室のトライについて詳しくみる!/

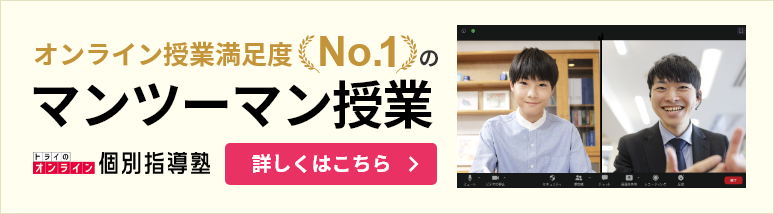
首都圏最大級!高校入試に向けた模試「Vもぎ」とは

Vもぎは、中学3年生が対象の高校入試に向けた模擬試験で、入試本番さながらの環境で試験に臨めるのが大きな特徴です。
年間延べ38万人以上が受験しており、都立高校や千葉県公立高校、難関私立高校を志望する多くの受験生が、自分の実力を測るために活用しています。
ここでは、Vもぎの試験科目や年間スケジュールといった基本情報から、当日の流れ、成績表の見方まで詳しく解説します。
初めてVもぎを受験する方はこれらの情報を押さえて、効果的に活用して志望校合格につなげましょう。
「Vもぎ」とは
Vもぎは、株式会社進学研究会が主催する模擬試験です。対象は中学3年生のみで、中学1〜2年生は受験できません。
首都圏で最も規模が大きい中学生向け模試の一つで、年間延べ38万人以上が受験しています。特に、都立高校を受験する予定の中学生が多く利用しており、都内受験生にとって定番の模試となっています。
そのため、膨大な成績データが集まりやすく、他の模試に比べて偏差値や合格判定の信頼性が高いと言えるでしょう。
Vもぎは、毎年6月から翌年1月まで定期的に実施されます。年間を通じて受験すれば、自分の学力推移を客観的に把握でき、志望校合格に向けて具体的な戦略を立てることが可能です。
「Vもぎ」の試験科目・年間スケジュール・受験料の目安
Vもぎは、高校入試に準じて国語・数学・英語・社会・理科の5教科が出題されます。試験の出題範囲は、Vもぎの公式サイトに掲載されているため、事前に確認しておきましょう。
Vもぎは例年6月から開始され、翌年1月まで月1回以上のペースで実施されます。8月以降の試験では、入試本番に近い難易度・形式の「そっくりもぎ」が実施され、多くの受験生が参加します。
10〜12月はVもぎの実施回数が増えるため、学習の進捗に合わせて受験すると、志望校合格に向けた最終調整がしやすくなるでしょう。
受験料は1回あたり4,900円ですが、独自問題で入試を行う都立高校に対応した「都立自校作成対策もぎ」は5,700円と高く設定されています。
3回以上の受験を予定している方は、1回あたり400円の割引を受けられる「Vもぎ回数券」の活用がおすすめです。
「Vもぎ」当日の流れと会場の雰囲気
Vもぎは、入試当日に近い環境・緊張感で試験に臨めるよう、朝から昼過ぎにかけてスケジュールを進行しています。
たとえば、8〜1月に実施される「都立そっくりもぎ」の試験日程は、以下のとおりです。
| 7時45分 | 受付開始 |
| 8時20分〜8時35分 | 志望校カード記入 |
| 8時40分〜9時30分 | 国語(50分) |
| 9時40分〜10時30分 | 数学(50分) |
| 10時40分〜11時30分 | 英語(50分) |
| 11時40分〜12時30分 | 社会(50分) |
| 12時40分〜13時30分 | 理科(50分) |
私立高校を目指している受験生向けの「私立Vもぎ」は、国数英の3教科のみで、11時30分頃に終了する予定となっています。
Vもぎの試験会場は、都内や千葉県内の私立高校や大学が中心です。普段の教室とは異なる空間に多くの生徒が集まることで、適度な緊張感を持ちながら試験に臨むことができるでしょう。
このようにVもぎでは、さまざまな面で本番さながらの臨場感を味わえるため、試験慣れにつながります。
「Vもぎ」の成績表の見方
Vもぎの受験後は、約1週間程度で成績表が返却されます。
成績表には科目ごとの得点・平均点・偏差値・志望校の合格判定など、さまざまな分析結果が記載されているため、正しく読み取ることが大切です。
たとえば、偏差値は同じ模試を受けた集団内における相対的な学力位置を示す数値で、「偏差値50」が平均的な成績を意味します。
そのため、成績表から自分の学力を見極める際は、偏差値50からどれくらいの差があるのかをチェックしましょう。
合格判定は、以下の合格可能性を基準にA〜E判定で示されます。
- A判定:80%以上
- B判定:60%以上
- C判定:40%以上
- D判定:20%以上
- E判定:20%未満
なお、成績優秀者にはS判定(90%以上)が付くこともあります。
成績表の学力分析表を見る際は、「×→◎」や「×→★」といったマークに注目してみてください。
これら2種類のマークは、本来解けたはずの問題や、もう少し理解を深めていれば正解できる可能性が高い問題を指します。
正答率80%以上の問題で間違えたものがある場合は、すぐに復習しておきましょう。
家庭教師のトライでは、Vもぎの結果からお子さまの弱点を分析し、オーダーメイドの学習プランを立てることで志望校合格へと導きます。
「プロ教師による完全マンツーマン授業を受けたい」「徹底的に苦手を克服したい」などの悩みをお持ちの方は、家庭教師のトライにお気軽にご相談ください。
\家庭教師のトライについて詳しくみる!/
「Vもぎ」の種類とそれぞれの特徴
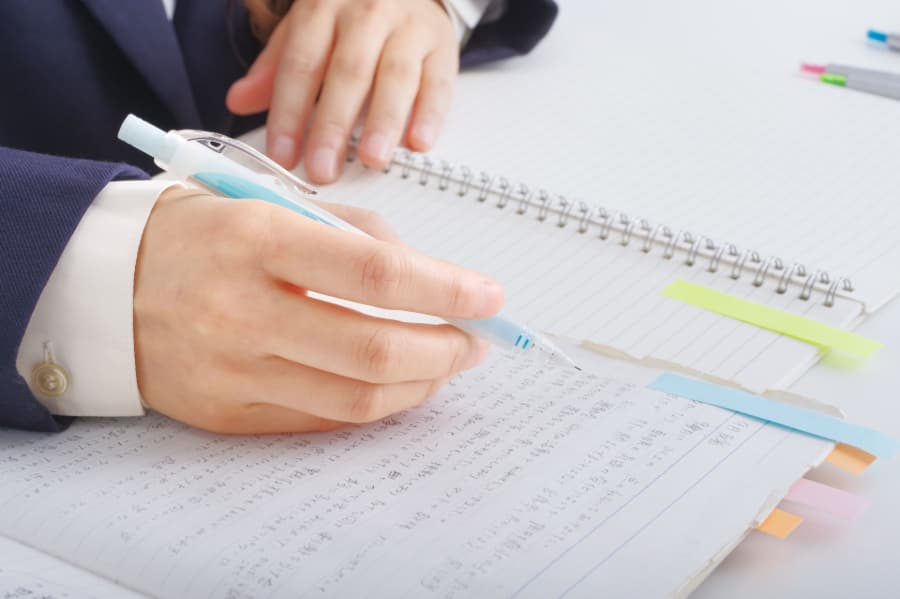
Vもぎには、志望校のタイプに応じて以下の種類があり、受験生は目的に合わせてどの試験を受けるか選択できます。
- 「都立Vもぎ」・「都立自校作成対策もぎ」|都立高校の受験者向け
- 「県立Vもぎ」|千葉県公立高校の受験者向け
- 「私立Vもぎ」|難関私立・国立高校の受験者向け
高校受験を突破するためには、それぞれの特徴を理解した上で、適切な対策を進めることが重要です。
模試の対象エリアや出題傾向を知り、自分に合った模試選びの参考にしてください。
「都立Vもぎ」・「都立自校作成対策もぎ」|都立高校の受験者向け
「都立Vもぎ」は、第一志望が都立高校である受験生向けの、スタンダードな模試です。
都立高校入試の共通問題に準拠した出題内容となっており、6月から翌年1月まで毎月実施されています。
8月以降は、試験時間や難易度がより本番に近い形式の「そっくりもぎ」が実施されるのが特徴です。
国語・数学・英語・社会・理科の5教科すべてが出題され、都立高校入試に似た問題が出題されます。受験料は1回あたり4,900円となっており、受験後は約1週間で成績表が返却されます。
「都立自校作成対策もぎ」は、日比谷高校・青山高校・国分寺高校など、入試で独自問題を出題する高校志望者向けの模試です。
英作文や数学の証明問題など、記述中心で難易度の高い問題が多く出題される傾向があります。
実施時期は10月から翌年1月までの全4回と限定的で、入試直前期の総仕上げとして活用すると良いでしょう。
受験料は1回あたり5,700円と高めですが、実際の入試レベルに近い高度な問題に挑戦することで、難関校を突破できる応用力をつけることができます。
「県立Vもぎ」|千葉県公立高校の受験者向け
「県立Vもぎ」は、千葉県公立高校の出題形式に沿って作成された、県内有数の大規模模試です。
都立Vもぎと並び、毎月1回以上のペースで実施され、8月以降は入試本番により近い形式で行われます。
千葉県の公立高校入試の特徴である「英語60分」の試験時間も再現されているため、リスニングや記述も含めて本番を意識した演習が可能です。
成績表では中学1〜3年生の内申点を用いた合格判定が提示されるなど、千葉県独自の計算方法にも対応しています。
試験会場は千葉県内の高校や大学で、受験料は都立Vもぎと同じく1回あたり4,900円となっています。
千葉県の公立高校を受験する予定のある方は、時間配分や問題のレベルに慣れるためにも、定期的な受験を検討しましょう。
「私立Vもぎ」|難関私立・国立高校の受験者向け
「私立Vもぎ」は、首都圏の主要な私立高校を目指す受験生向けの模擬試験です。試験の難易度は、「都立Vもぎ」や「県立Vもぎ」よりも高めです。
難関私立高校の入試難易度を踏まえた問題が出題され、合格判定も主要な私立高校を中心に行われます。
実施時期は9〜12月の計4回となっており、他の模試より受験できる回数が少ない点に注意が必要です。
試験科目は国語・数学・英語の3科目のみで、1回の試験は比較的短時間で実施されます。詳細な所要時間は公式案内等で確認してください。
なお、受験料は1回あたり4,900円です。
「Vもぎ」を受ける2つのメリット

受験生の中には「Vもぎを受ける意味はあるの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。
結論、高校受験に向けて「Vもぎ」を受けるメリットは、以下の2つです。
- 本番さながらの緊張感で試験を受けられる
- 詳細な成績表で弱点を見つけられる
Vもぎのメリットを最大限活用することで効果的な対策が可能となり、高校受験を有利に進められます。
以下で、それぞれ具体的に見ていきましょう。
メリット①本番さながらの緊張感で試験を受けられる
Vもぎ最大のメリットは、入試さながらの緊張感を体験できることです。
塾や学校で受けるテストと異なり、まったく知らない受験生たちが会場に集まるため、本番同様の緊張感を味わうことができるでしょう。
そのため、Vもぎを積極的に受けておけば、入試当日も独特の雰囲気に飲み込まれず、平常心を保った状態で実力を最大限発揮できます。
Vもぎは時間割も本番と同様に組まれているため、試験時間内にすべての問題を解くトレーニングとしても最適です。
「計算問題に時間をかけすぎて記述問題を解けなかった」など、時間配分の失敗も経験しておけば、早めの対策で高得点を狙うことができるでしょう。
メリット②詳細な成績表で弱点を見つけられる
Vもぎを受けるもう一つの大きなメリットは、詳細な成績表から自分の弱点が明確になることです。
成績表には、自分の得点や偏差値、各問題の正答率など詳細なデータが記載されています。こうした学力を客観的に測る指標を活用すれば、独学では気づけない弱点や課題が明確になるでしょう。
また、Vもぎの成績表は「正答率80%以上なのに間違えた問題」や「あと一歩で正解できた問題」も一目でわかる点が大きなメリットです。
重点的に補強すべきポイントを明らかにすることで、模試を受けた後も効率的に勉強を進めることができます。
個別教室のトライでは弱点発見から克服まで徹底サポート
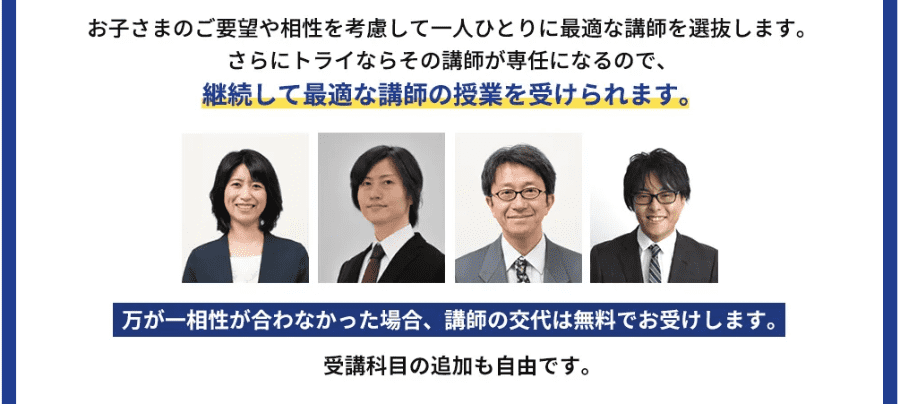
個別教室のトライでは、お子さまと相性の良い講師が、完全マンツーマン授業で弱点発見から克服まで徹底サポートします。
お子さまの学習する様子から、つまずきやすいポイントや苦手意識の高い単元・分野を把握し、丁寧な指導を行います。
Vもぎの結果からお子さまの弱点を分析し、最適な学習プランを提案することも可能です。授業中は不明点があってもすぐに質問できるため、疑問を残すことなく理解を深められます。
無料体験授業を実施しているため、プロ講師による指導を一度受けてみたい方は、お気軽にご相談ください。
「Vもぎ」を活かして偏差値を上げる3つのコツ

Vもぎを活かして偏差値を上げるには、以下3つのコツを押さえましょう。
- 受験スケジュールを立てる
- 模試後の復習にしっかり取り組む
- 過去問演習と時間配分の練習を並行して行う
志望校合格を実現させるためには、Vもぎを受けっぱなしにせず、結果を次につなげることが重要です。
模試の効果を最大限活かすことで、入試に向けてより効率的な学習計画を立てられるようになり、志望校合格に大きく近づけます。
受験スケジュールを立てる
Vもぎに挑戦する場合は、まず「年に何回」「いつ」試験を受けるのか計画を立てましょう。
一度受験するだけでは、問題との相性や当日の体調によって、正しい学力を測定できない可能性があります。
そのため、自分の正確な実力を把握するために、3回以上は受験するのがおすすめです。
受験のタイミングとしては、部活を引退して時間に余裕が生まれる「8〜9月以降」が良いでしょう。
8〜9月からVもぎを受けることを前提に学習計画を立てておくと、部活動が忙しい中でも効率的に勉強を進められます。
模試後の復習にしっかり取り組む
Vもぎを活かして偏差値を上げるために大切なのは、受験後の復習です。思い通りの点数が取れなかったときこそ、問題を解きっぱなしにせず、復習して次につなげるようにしましょう。
復習を通して自分の弱点を克服するための効果的なステップは、以下のとおりです。
- ステップ1. 全科目の答案を見直し、間違えた問題を分析する
模試の解答解説を参考に、各科目で誤答・空欄だった問題について「なぜ間違えたのか」「わからなかったのか」を分析します。 - ステップ2. 優先度の高い問題から解き直す
学力分析表の「×→◎」「×→★」マークが付いた問題は、真っ先に取り組みましょう。正答率が高い問題の取りこぼしを減らすことが、偏差値アップの近道です。 - ステップ3. 苦手分野の補強と再テストを行う
解き直しても間違えてしまった問題は、参考書や問題集を使って内容理解を深めましょう。
解答解説を見なくても解けるようになるまで復習を重ねれば、次の模試で似た問題が出題されても、確実に得点につなげられます。
家庭教師のトライでは完全マンツーマン授業で模試の結果を最大限に活かした学習をサポート
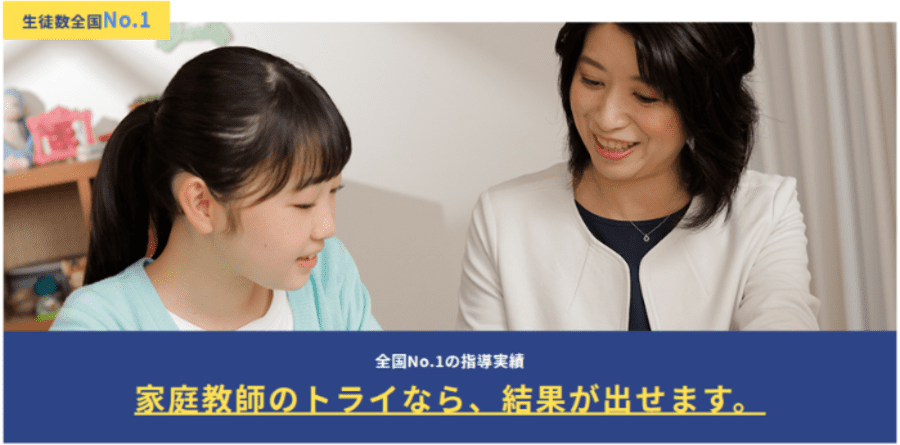
家庭教師のトライでは、厳しい審査基準を通過した教師による完全マンツーマン授業で、模試の結果を最大限活かして学習をサポートします。
周りのペースを気にせず学習を進めることができるため、お子さまが納得できるまで徹底的にサポート。
模試の結果に基づく学習のアドバイスや、オーダーメイドのカリキュラム作成も可能です。
高校受験に向けて必要な対策を見極め、最短ルートで志望校合格へと導きます。
過去問演習と時間配分の練習を並行して行う
Vもぎ対策や復習と並行して、過去問演習や時間配分の練習にも取り組みましょう。Vもぎの公式サイトでは、科目ごとの過去問集が販売されており、直近数年分のVもぎ問題に挑戦できます。
過去問演習は、1回分を通しで解いてみるのがおすすめです。実際の模試と同じ時間割で取り組めば、適切な時間配分の感覚をつけることができるでしょう。
また、タイマーを利用して、本番さながらの時間配分と緊張感で臨むことも大切です。
まとめ

本記事では、Vもぎの基本情報や種類別の特徴、Vもぎのメリットや偏差値を上げるためのコツを解説しました。
Vもぎの特徴を理解し活用すれば、志望校合格に向けて効率的に対策を進めることができるでしょう。
Vもぎを活かして偏差値を上げるためのコツは、以下の3つです。
- 受験スケジュールを立てる
- 模試後の復習にしっかり取り組む
- 過去問演習と時間配分の練習を並行して行う
思うような結果が出なかったときこそ、問題を解きっぱなしにせず、弱点克服に役立てることで、着実に学力を伸ばすことができます。
ぜひ本記事を参考に、Vもぎのメリットを最大限活かして、高校受験の準備を進めてみてください。