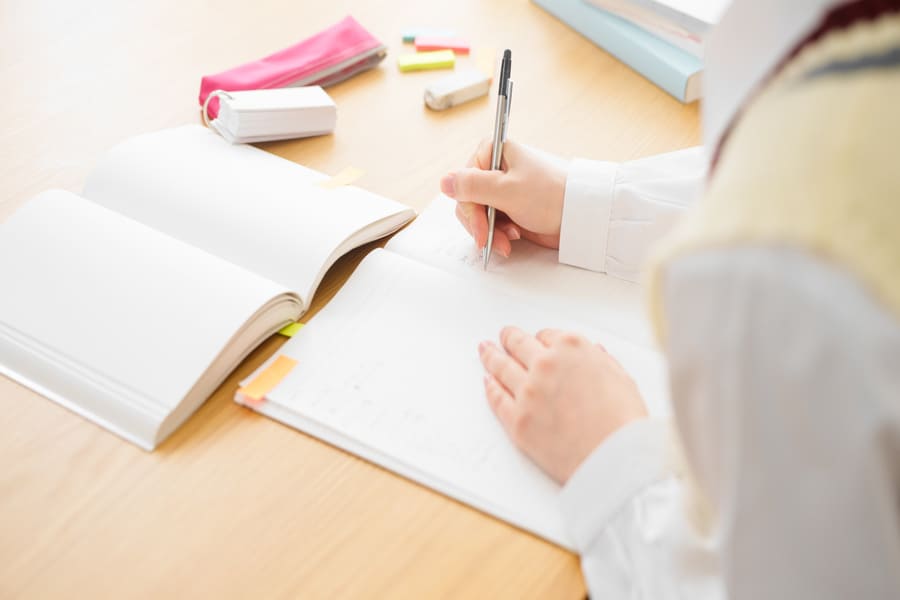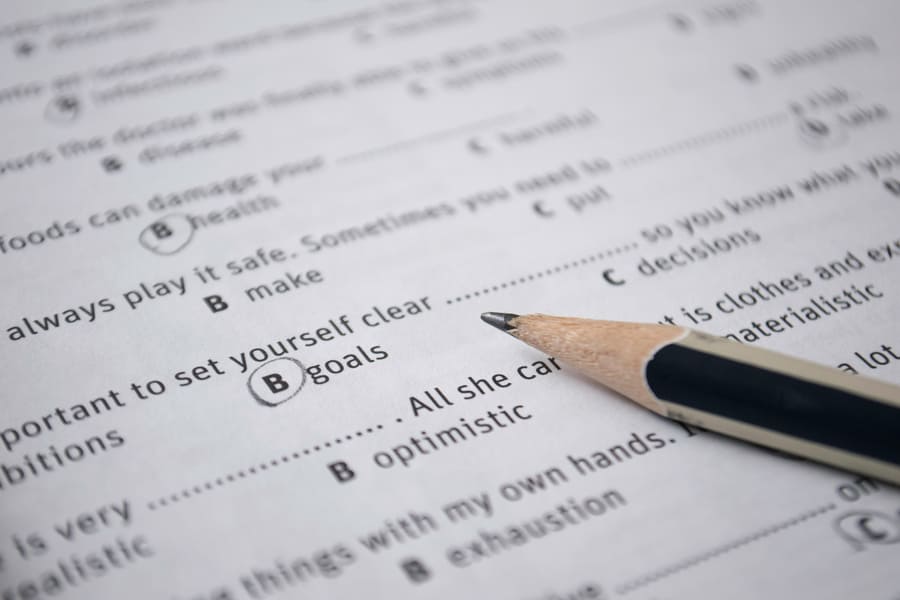「うちの子、最近学校に行きたがらないけれど、大丈夫かな…」
「小学生が不登校になる原因が知りたい」
「親として、どう対応するのが正解かわからない」
このように、子どもの不登校に直面し、不安や戸惑いを感じている保護者の方は少なくありません。
文部科学省の調査によると、年間30日以上欠席した小学生の数は過去最多を更新しており、多くの子どもが学校生活に不安や悩みを抱えています。
不登校の理由は一人ひとり異なり、解決策もさまざまです。大切なのは、子どもの気持ちに寄り添い、適切なサポートをすることです。不登校は決して珍しいことではなく、子どもが自信を取り戻すための時間でもあります。
この記事では、不登校の小学生の現状や主な原因、親ができる適切な対応、家での過ごし方などについてわかりやすく解説します。焦らず、子どもと一緒にできることから始めていきましょう。
完全マンツーマン授業で不登校の生徒でも周りの目を気にすることなく学習に集中できるほか、授業は同じ教師が担当することから、学校で授業を受けられていない単元や苦手な問題などを教師が把握でき、効率よく学習を進められます。
また、不登校の生徒への指導実績がある教師も多数在籍しているのも特徴です。不登校の小学生のお子さまの学習にお悩みの方は、トライのオンライン個別指導塾にお気軽にご相談ください。
\トライのオンライン個別指導塾について詳しくみる!/

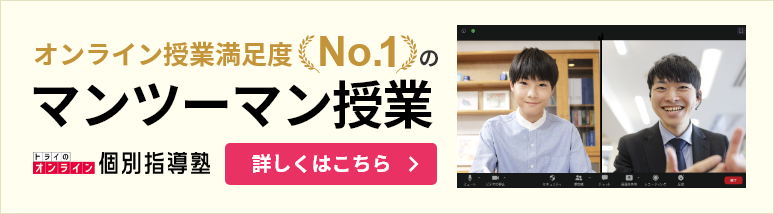
この記事の目次
不登校の小学生は増えている?自信を取り戻すには適切なサポートが大切

文部科学省の調査によると、令和5年度に不登校となった小・中学生は約34万人。前年と比べて15.9%増加しており、小・中学生の約3.7%が不登校状態にあります。
参照:文部科学省「令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」
不登校とは、病気や経済的な理由を除き、年間30日以上登校しなかった状態を指しますが、定義に当てはまらなくても「学校に行きたくない」と悩む子どもは少なくありません。
不登校の原因には、以下のようなものが挙げられます。
- 友達との関係が上手くいかない
- 教室にいるのがしんどい
- 朝になると体調が悪くなる
- 授業についていけず苦痛
しかし実際には、さまざまな理由で学校に行けない子どもが増えています。
子どもが不登校になったら、まずは安心して休める環境を整え、本人の気持ちに寄り添ってサポートすることが大切です。焦って登校を促すのではなく、自信を取り戻せるような関わり方を心がけましょう。
【学年別】小学生が不登校になる主な原因

不登校の背景には、学年によって異なる悩みや不安があることが多く、子ども自身が「なぜ学校に行けないのか」をうまく言葉にできない場合もあります。
大人が無理に原因を探ろうとするのではなく、子どもの気持ちに寄り添いながら、学年ごとの特徴を参考に様子を見守ることが大切です。
- 低学年(1~2年生)|母子分離不安や環境の変化による不安
- 中学年(3~4年生)|勉強や人間関係の悩み
- 高学年(5~6年生)|人間関係・無気力・生活リズムの乱れ
- 全学年共通|発達特性・集団生活へのストレスなど
それぞれ解説していきます。
低学年(1~2年生)|母子分離不安や環境の変化による不安
低学年では、学校生活に慣れないことや親と離れることへの不安(母子分離不安)が不登校の原因となることがあります。入学やクラス替えといった環境の変化に戸惑い、学校に行くことそのものが「怖い」と感じてしまう子どもも少なくありません。
この時期の不登校は、子どもが安心できる居場所を求めているサインでもあります。
我が子が甘えてくる時は、無理に自立を促そうとしないことが大切です。優しく抱きしめたり話を聞いたりしながら「大丈夫だよ」「あなたの不安な気持ち、わかってるよ」と声をかけ、まずは子どもの気持ちを受け入れて寄り添いましょう。
子どもの不安に共感し、認める言葉を繰り返し伝えて安心感をもたせてあげてください。
中学年(3~4年生)|勉強や人間関係の悩み
中学年になると、理科や社会など新しい教科が加わり、勉強の難易度が上がることで戸惑う子どもが増えてきます。成績や授業への苦手意識から「どうせできない」という気持ちが強くなり、学校に行きたくなくなることもあります。
また、友達関係が複雑になってくる時期でもあり、ささいなトラブルや仲間外れをきっかけに不登校になるケースも見られます。
うまく言葉にできず、心の中で苦しんでいることもあるため、保護者が子どもの気持ちの変化に気付き、寄り添う姿勢が大切です。
高学年(5~6年生)|人間関係・無気力・生活リズムの乱れ
心身の成長が著しくなる高学年は自我が強くなる時期でもあるため、学校生活でさまざまなストレスを感じやすくなります。不登校の原因も複雑になりやすく、次のような要因が重なっている場合もあります。
- 人間関係のトラブル
友達との関係やグループ内での立ち位置などに悩み、居場所がないと感じてしまう - いじめ
無視や悪口、身体的ないやがらせなどのケースもあり、登校そのものが恐怖になってしまう - やる気の低下や無気力
反抗期と重なり、「なんで学校に行かないといけないんだろう」と目的を見失ってしまう - 生活リズムの乱れ
夜更かしや朝起きられないといった生活習慣の乱れが積み重なり、体調不良につながる
どの要因にしても、子どもの「つらい」という気持ちをしっかり受け止め、信頼できる大人がそばにいる安心感を伝えることが、次の一歩につながります。
全学年共通|発達特性・集団生活へのストレスなど
学年に関係なく、発達障がいの特性や集団生活への適応の難しさ、教師との相性といった理由で不登校になる子どももいます。自分でもうまく気持ちを整理できず、苦しんでいるケースも多いため、子どもの行動や感情の変化に敏感に寄り添いましょう。
また、朝起きられない・頭痛が続くといった症状がある場合は、「起立性調節障害」など体の不調が原因になっている可能性もあります。
思い当たる場合は、医療機関への相談も視野に入れてみてください。
小学生が不登校になったときに親ができる6つの対応

「突然の不登校に戸惑い、どう対応すればいいのかわからない」という保護者の方も多いのではないでしょうか。しかし、不登校は決して珍しいことではありません。今はまず、お子さまの「つらい気持ち」に寄り添うことが何より大切です。
子どもが安心して過ごせるようになるために、保護者の方ができる6つの対応を紹介します。
- 「学校を休んでもいいよ」と伝える
- 原因を深掘りせず子どもの話に耳を傾ける
- 子どもが安心できる居場所を作る
- 学校の教師やスクールカウンセラーと連携をとる
- 不登校を支援する専門機関に相談する
- 学校以外で子どもに合った学びの方法を検討する
焦らず、少しずつ前に進むための参考にしてください。
1.「学校を休んでもいいよ」と伝える
多くの子どもは、「学校には行かなければならない」と思いながらも、心や体がついてこない状況に苦しんでいます。そのような時は、「休んでも大丈夫だよ」と保護者が声をかけることで、子どもは安心し、自分の気持ちを素直に出せるようになります。
無理に登校を促すのではなく、まずは「休んでもいい」という選択肢を示しましょう。
2.原因を追求せず子どもの話に耳を傾ける
不登校の原因を知りたくなるのは当然のことですが、子ども自身がうまく言葉にできない場合も多くあります。無理に問い詰めると、かえって心を閉ざしてしまうこともあるので注意が必要です。
「どうして行けないの?」ではなく、「つらかったね」「話してくれてありがとう」といった言葉で、子どもが安心して話せる雰囲気を作りましょう。時間が経つと、少しずつ子どもの言葉で伝えてくれるかもしれません。
3.子どもが安心できる居場所を作る
学校以外でも、子どもが心から安心できる場所があることは、とても大切です。家庭の中で「ここにいていいんだ」と思える空間を作るのはもちろん、可能であれば次のような居場所も検討してみましょう。
- フリースクールや教育支援センター(適応指導教室)
- 興味のある習い事や地域の活動
- 信頼できる大人との交流の場 など
また、家庭が「安全基地」になることが、子どもの回復を後押ししてくれます。
子どもにとって一番の居場所は自宅です。学校に行けないことを否定せず、安心して過ごせる環境を整えましょう。
また、「教育支援カウンセラー」の資格を持った社員も多数在籍。部屋から出られないお子さまのご自宅に訪問し、お悩みの解決に向けて粘り強くサポートすることも可能です。
不登校のお子さまのサポートなら、家庭教師のトライにおまかせください。
\家庭教師のトライについて詳しくみる!/
4.学校の教師やスクールカウンセラーと連携をとる
長期間登校できなかったとしても、学校との関係を完全に断つ必要はありません。
担任の教師やスクールカウンセラーと連絡をとりながら、少しずつ登校への準備を進めたり、家庭学習のフォローを受けたりしましょう。
また、学習の遅れをそのままにしてしまうと、学校に戻った際に「授業についていけない」という不安や挫折感から、再び不登校になってしまうリスクもあります。
そのため、学習面のサポートを受けながら、無理のないペースで学びを取り戻していくことが大切です。
子どもが「戻っても大丈夫」と思えるような環境を整えていくことができます。
5.不登校を支援する専門機関に相談する
「どう接していいのかわからない」「自分の対応が正しいのか不安」と感じた時は、専門機関に相談してみましょう。保護者自身が安心して話せる場所を見つけることも、子どもを支えるうえで大切なことです。
- 教育相談センター
- 児童相談所
- 自治体の教育支援課や教育委員会
- スクールカウンセラー など
特に、スクールカウンセラーは子どもの支援だけでなく、保護者の気持ちを受け止める役割も担っているため、ぜひ気軽に相談してみてください。
一人で抱え込まず、周囲の力を借りることを前向きに考えてみましょう。
6.学校以外で子どもに合った学びの方法を検討する
「勉強についていけなくなりそう」「学力が心配」といった不安があると、子どもも保護者も焦りやすくなります。そのような時は、学校以外で子どもに合った学び方を取り入れてみるのも一つの方法です。
たとえば、以下のような選択肢があります。
- 家庭教師
- オンライン学習
- フリースクールの学習支援
- 適応指導教室の補習
子どものペースに合わせて「できた」を少しずつ増やすことで、自信を取り戻すきっかけになります。
トライのオンライン個別指導塾ではお子さまの学力に合わせた完全マンツーマンの授業で学校の勉強をカバーできる

トライのオンライン個別指導塾「不登校サポートコース」では、不登校のお子さま向けに、学力や性格に合わせたマンツーマン指導を行っています。
- 教育プランナーが一人ひとりに合わせた学習プランを作成
- オンライン授業なので、外出せず自宅で学べる
- 最初は勉強に抵抗があるお子さまでも、ゆっくり慣れていけるサポート体制
「いきなり教師と対面するのは不安」というお子さまでも、画面越しなら少しずつ慣れやすいでしょう。勉強の遅れに不安を感じている方は、まずはお気軽にご相談ください。
不登校の小学生に最適な家での過ごし方

「学校に行けない間、子どもとどう過ごせばいいかわからない」と悩む保護者の方も多いかもしれません。
無理に登校を促すのではなく、子どもの気持ちに寄り添いながら、安心して過ごせる時間を確保することが大切です。
- 心と体をゆっくり休める
- 好きなこと・興味のあることに取り組んでみる
- 元気が出てきたら無理のないペースで勉強を進める
上記のポイントに沿って、不登校中の小学生が家で少しずつ前向きになっていける過ごし方をご紹介します。
心と体をゆっくり休める
不登校にいたるまでには、子どもは多くの不安やストレスを感じてきたはずです。まずは「休むことが悪いことではない」と認め、心と体の回復を最優先にしましょう。
昼夜が逆転していても、無理に生活を正そうとせず、少しずつリズムを整えていくことが大切です。たっぷり眠る、好きなものを食べる、静かに過ごす。このような時間が、心の回復には欠かせません。
好きなこと・興味のあることに取り組んでみる
気持ちが落ち着いてきたら、子どもが好きなことや興味を持っていることに取り組む時間を作ってみましょう。ゲームやお絵描き、読書、プログラミング、料理など、なんでも構いません。
保護者の方に余裕があれば、一緒に取り組むのもおすすめです。会話のきっかけにもなり、親子の信頼関係がより深まります。好きなことを通じて「自分にもできることがある」という実感が、子どもの自己肯定感にもつながっていきます。
元気が出てきたら無理のないペースで勉強を進める
心と体が落ち着き、少しずつ前向きな気持ちが戻ってきたら、無理のない範囲で勉強に取り組んでみましょう。
いきなり学校のカリキュラムどおりに進めるのではなく、子どもの得意な教科や好きな分野からスタートすると、気負わずに取り組みやすくなります。
大切なのは、保護者の方が「遅れを取り戻さなければ」と焦らないことです。まずは学習の楽しさを思い出し、自信を取り戻すことが大切です。
トライのオンライン個別指導塾では正社員の教育プランナーがお子さまの希望に合った最適な学習プランを提案
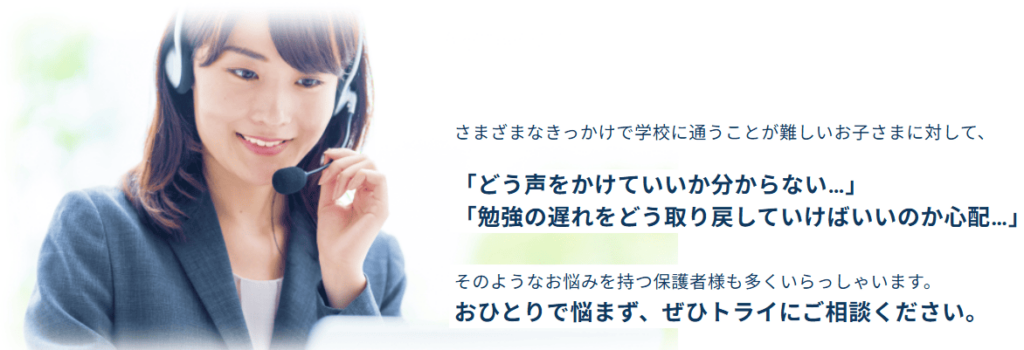
トライのオンライン個別指導塾では、不登校のお子さま一人ひとりに合わせて、無理のないペースで学習を進められるようサポートしています。
学習指導を担当する教師とは別に、正社員の教育プランナーが担任制でつくため、お子さまやご家庭の希望に合った最適な学習プランのご提案が可能です。
たとえば、「まずは得意な教科だけ進めたい」「1日1コマだけ取り組みたい」といったご希望にも柔軟に対応できます。
また、定期的な面談を通して学習状況を確認し、必要に応じてカリキュラムを見直します。
学習プランの進捗や授業中の様子は、LINEなどを通じて気軽に共有されるため、学習中のお子さまの様子が気になる保護者様も安心して見守ることが可能です。
画面越しでの授業なので、「対面は緊張する」というお子さまにも取り組みやすく、自宅にいながら安心して学習習慣を取り戻すことができるでしょう。
まとめ

この記事では、以下のポイントについて解説してきました。
- 不登校の小学生は全国的に増えており、子どもが安心して過ごせるサポートが必要
- 学年ごとの不登校の主な原因と、親ができる6つの対応
- 家で安心して過ごすための工夫と、無理のない学習再開の進め方
子どもが安心して自分のペースで過ごせることが、次の一歩につながります。焦らず、寄り添いながらサポートしていくことで、子ども自身が「またやってみよう」と思えるタイミングが訪れるでしょう。
不登校の小学生は年々増加傾向にあり、特別なことではありません。小さなきっかけや環境の変化、心の揺れ動きなど、さまざまな理由で学校に行けなくなる子どももいます。
ご家庭での対応に不安がある場合や、学習面での遅れが心配な場合は、無理せず外部のサポートも取り入れてみてください。まずはお子さまの心と学びに寄り添う環境を作りましょう。