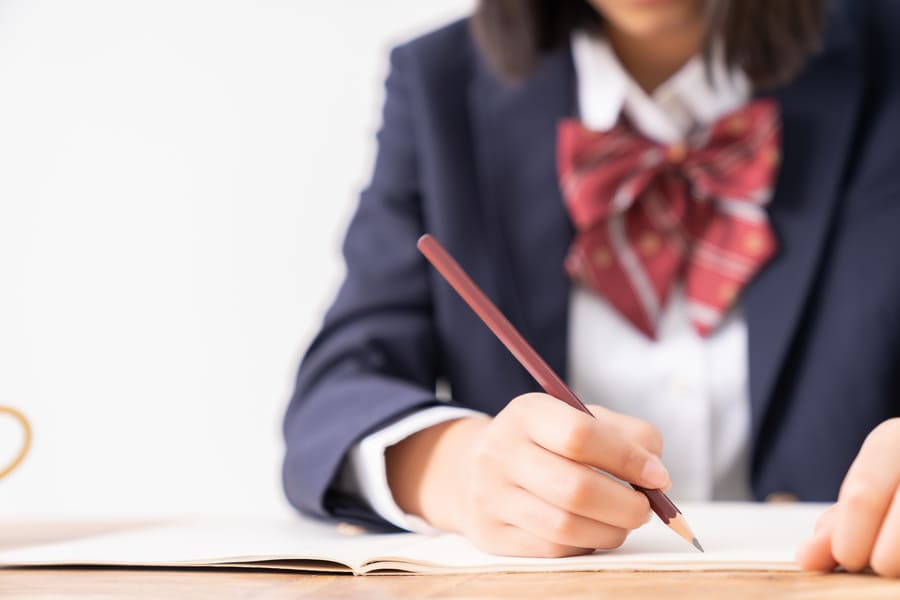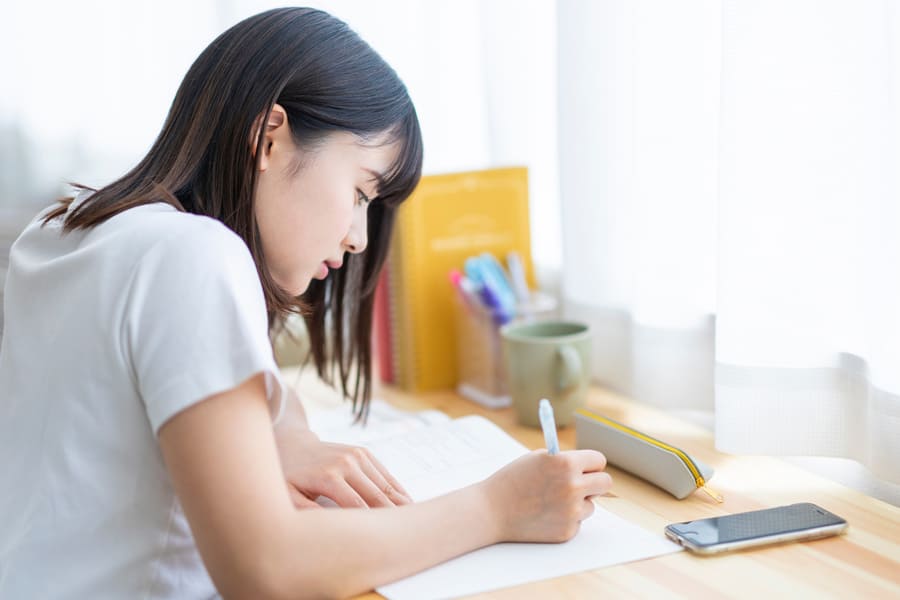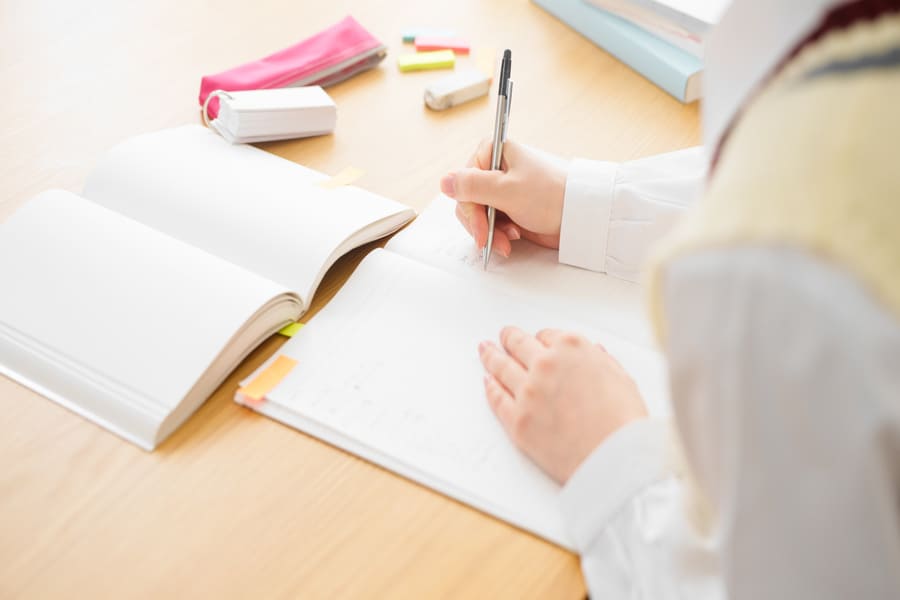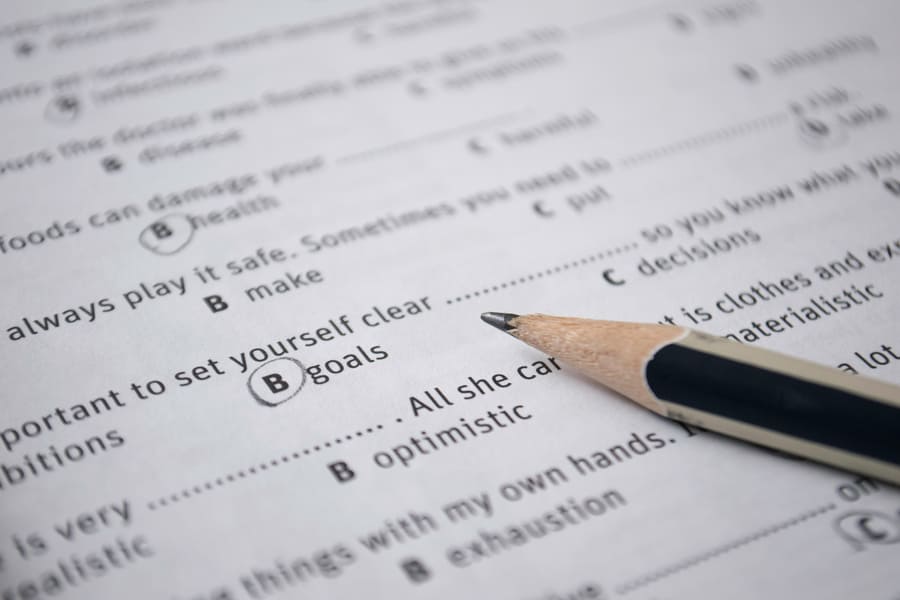「発達障がいの特性を持つ子どもの勉強をサポートしたい」
「子どもがあまり勉強できないのは発達障がいの特性が影響している?」
そんな不安を抱えている保護者の方は少なくありません。実際、発達障がいの特性がある場合、学習面で困難を感じることもあります。
しかし、発達障がいだからといって、勉強ができないと決まっているわけではありません。子どもがつまずきやすいポイントを知り、適切な方法でサポートすれば、無理なく学力を伸ばすことができるでしょう。
具体的には、以下のポイントについて詳しく解説します。
- 発達障がいと勉強の関係
- タイプ別に見る課題とおすすめの勉強法
- 親ができる3つのサポート
お子さまをサポートするヒントとして、ぜひご活用ください。
家庭教師のトライには、発達障がいのお子さまへの指導経験を持つ教師が多数在籍しているため、一人ひとりの特性に合った指導やサポートを受けられます。
無料学習相談も実施していますので、お子さまの学習をどのようにサポートするかお悩みの方は、家庭教師のトライにお気軽にご相談ください。
\家庭教師のトライについて詳しく見る!/

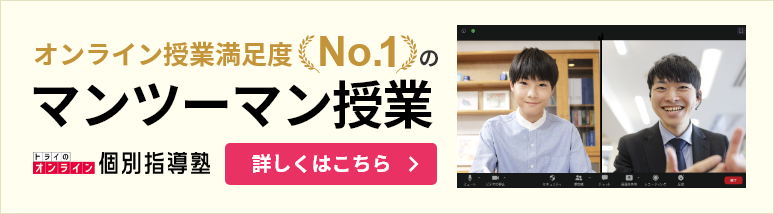
この記事の目次
発達障がいだからといって必ずしも勉強ができないとは限らない
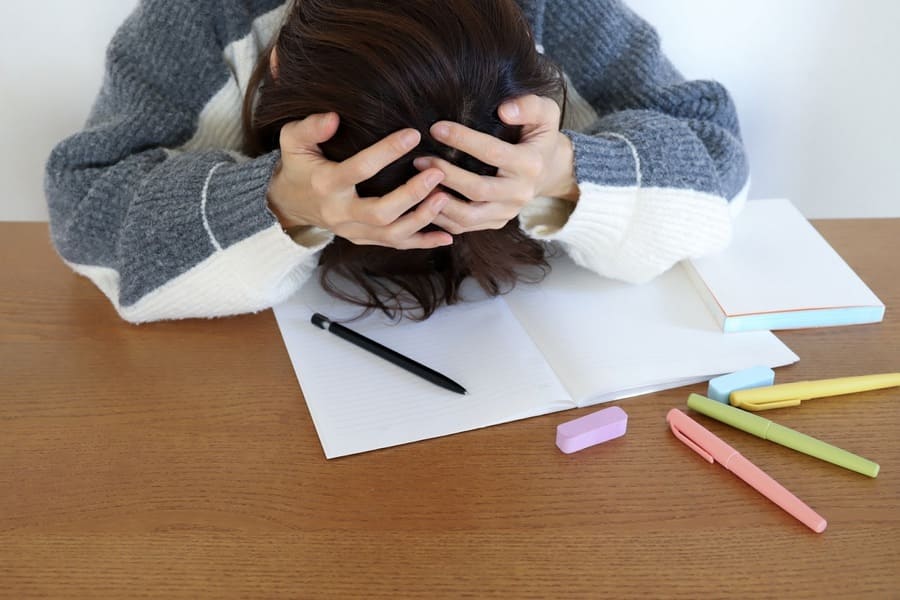
「発達障がい=勉強ができない」と考えてしまう方もいるでしょう。しかし、発達障がいといっても様々な種類があり、一概に勉強が苦手というわけではありません。
発達障がいには、ADHD(注意欠如・多動症)、ASD(自閉スペクトラム症)、SLD(学習障害)などがあります。このうちSLDは、読み書きや計算など特定の学習分野に困難を抱えがちです。
一方、ADHDやASDの場合は、必ずしも勉強が苦手ということはないものの、集中力の維持が難しい、記憶を保持しにくいといった特性が学習に影響することがあります。
こうした場合、勉強ができないのではなく、今の勉強方法がその子の特性に合っていないだけという可能性があります。そのため、何につまずいているのかを丁寧に探り、特性に合ったサポートを行うことが大切です。
記憶を保持する「ワーキングメモリ」の働きが影響している可能性も
発達障がいの子どもが学習でつまずく原因の一つに、ワーキングメモリの影響があります。
ワーキングメモリとは、情報を一時的に頭の中にとどめておく力のことです。
- 黒板の内容を見ながらノートに書き写す
- 文章題を読みながら頭の中で計算する
- 教師の話を聞きながら大事なポイントを覚えておく
このように、ワーキングメモリは日常生活や学習などのあらゆる場面で使われています。
発達障がいのある子どもは、このワーキングメモリの容量が少なかったり、うまく使えなかったりする傾向があります。そのため以下のような状態になりやすく、努力しているのに成果が出ない、という悩みにつながることがあるのです。
- 言われたことをすぐに忘れてしまう
- 問題文を読んでいる途中で何をしていたかわからなくなる
- 勉強したのに、テストで何も思い出せない
こうしたつまずきが重なることで、子ども自身が「自分は勉強ができない」と思い込んでしまうことも。だからこそ、特性に合わせた学び方で、成功体験を積み重ねることが大切です。
【特性別】発達障がいのある子どもが抱えやすい学習面の困りごと・おすすめの勉強法

発達障がいのある子どもは、それぞれの特性によって学習面で異なる困りごとを抱えることがあります。
ここでは、発達障がいの主なタイプ別に、よく見られる学習上の課題と、それぞれに合ったおすすめの勉強法を解説します。
- ADHD(注意欠如・多動症)|集中が続かず、話を聞き逃しやすい
- ASD(自閉スペクトラム症)|柔軟に対応するのが苦手で混乱しやすい
- SLD(ディスグラフィア/書字障害)|文字を書くことに強い苦手を感じる
- SLD(ディスレクシア/識字障害)|文字を読むことが極端に苦手
- SLD(ディスカリキュア/算数障害)|数の概念や計算のステップが理解しにくい
お子さまに合わせたサポートの参考にしてください。
ADHD(注意欠如・多動症)|集中が続かず、話を聞き逃しやすい
ADHDは、注意を持続させるのが難しい、落ち着きがないなどの特性が見られる発達障がいです。そのため、授業中に話を聞き逃してしまったり、ノートを取る途中で別のことに気がそれてしまったりすることがあります。
また、思いついたことをすぐに口にしてしまう衝動性や、じっと座っているのが苦手な多動性も、学習の妨げになることがあります。
ADHD(注意欠如・多動症)の子どもにおすすめの勉強法
ADHDの子どもにおすすめの勉強法は以下のとおりです。
- 短時間で区切って学習する(10〜15分ごとに休憩を挟む)
- タイマーやアラームを使って学習時間を見える化する
- 視覚的な教材や、体を動かしながら学べる方法を取り入れる
- 1対1の環境で、声かけしながら進める
集中力が続きにくいからこそ、時間や範囲を明確に区切ると、学習へのハードルがぐっと下がります。
ASD(自閉スペクトラム症)|柔軟に対応するのが苦手で混乱しやすい
ASDの子どもはこだわりが強く、急な予定変更や曖昧な表現に対応するのが苦手です。また、全体よりも細部に意識が向きやすく、課題の意図を読み取るのに時間がかかることもあります。
そのため、学習場面では、以下のつまずきが起きやすくなります。
- 説明の意味を理解できない
- 課題の背景や目的がわからない
ASD(自閉スペクトラム症)の子どもにおすすめの勉強法
ASDの子どもにおすすめの勉強法は以下のとおりです。
- 「いつ・何を・どれだけやるか」を明確に示すスケジュール表を使う
- 抽象的な言葉ではなく、具体的な表現を使う
(例:頑張って→あと5分頑張ろう) - 視覚的な支援(図・写真・チェックリスト)を活用する
- 興味のあるテーマを学習内容に取り入れて、理解しやすくする
予定や手順が見えるようにすると安心感が生まれ、学習にも集中しやすくなります。
SLD(ディスグラフィア/書字障害)|文字を書くことに強い苦手を感じる
ディスグラフィアは、文字をうまく書けなかったり、書くことに強い負担を感じたりする学習障害です。
文字を書くだけで疲れてしまい、問題を解く気力を無くしてしまう場合があります。
SLD(ディスグラフィア/書字障害)の子どもにおすすめの勉強法
ディスグラフィア/書字障害の子どもにおすすめの勉強法は以下のとおりです。
- 音声入力やタイピング学習を活用して、書く負担を減らす
- マス目の大きいノートやガイド付きプリントを使って書きやすくする
- 読む・聞く・話すなど、書く以外の手段で学習を進める
- 文字を書く練習ではなく、内容理解を優先する
「勉強=書くこと」にならないように、無理のない方法で知識をインプットやアウトプットできる環境づくりが大切です。
SLD(ディスレクシア/識字障害)|文字を読むことが極端に苦手
ディスレクシアは、文字を読むことに困難がある学習障害です。以下のような症状が見られるのが特徴です。
- 読んでも意味が頭に入らない
- ひらがながバラバラに見える
- 同じ文章を何度も読み直してしまう
SLD(ディスレクシア/識字障害)の子どもにおすすめの勉強法
ディスレクシア/識字障害の子どもにおすすめの勉強法は以下のとおりです。
- 音読ではなく、聞く学習(音声教材や読み聞かせ)を活用する
- 文字の大きさやフォントを工夫する(大きい文字やふりがな付きなど)
- 短い文章からスタートし、成功体験を積み重ねる
- 文章の内容を絵や図で補う
読むことが苦手でも、内容の理解ができないわけではありません。読むことに代わる手段を取り入れることが重要です。
SLD(ディスカリキュア/算数障害)|数の概念や計算のステップが理解しにくい
ディスカリキュアは、数や計算の概念をうまく理解できない学習障害です。
- 繰り上がり・繰り下がりがわからない
- 文章題の意味を読み取れない
- 九九がいつまでたっても覚えられない
これらのような困難を抱えることがあります。
SLD(ディスカリキュア/算数障害)の子どもにおすすめの勉強法
ディスカリキュア/算数障害の子どもにおすすめの勉強法は以下のとおりです。
- 数を視覚化する道具(ブロック、図、表など)を使って理解を助ける
- 一つの計算に絞って繰り返し練習し、ステップを丁寧に確認する
- 文章題には、図を描く・言葉で説明するなどの多様な手段でアプローチする
- 焦らず、理解のペースに合わせてステップを分解する
「なぜそうなるのか」が視覚的・体感的にわかるようにすると、理解が深まりやすくなります。
家庭教師のトライでは発達障がいの特性に合わせた完全マンツーマン授業でお子さまの学習を徹底サポート
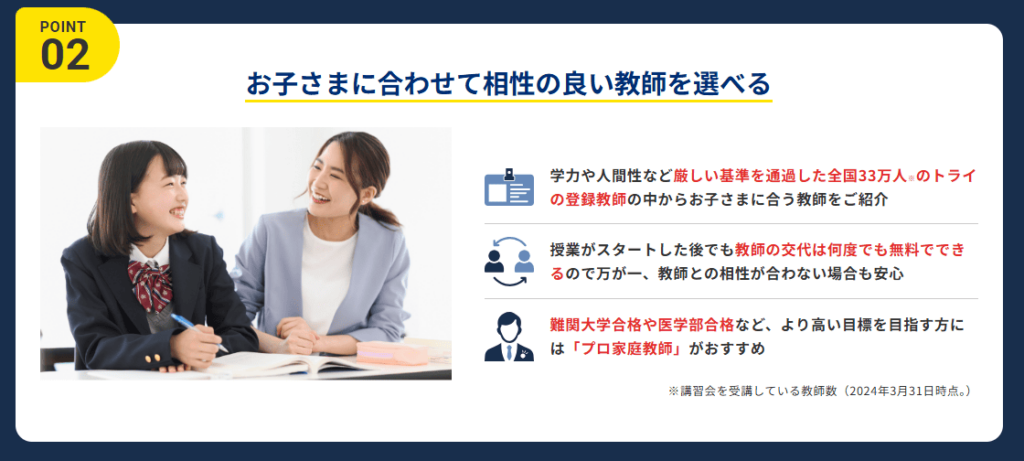
参照:家庭教師のトライ – 満足度No.1約33万人教師からあなたに最適な家庭教師をご紹介
発達障がいの特性があるお子さまは、それぞれに合ったやり方で、丁寧に学習を進めていく必要があります。
家庭教師のトライでは、発達障がいに関する知識と指導経験が豊富な教師が、お子さま一人ひとりの特性に合わせた完全マンツーマン授業を行っています。
また、学習面だけでなく、日々の関わりや声かけ、モチベーション管理にいたるまで、専門的な視点からトータルサポートが可能です。
発達障がいで勉強ができないと感じる子どもに親ができる3つのサポート
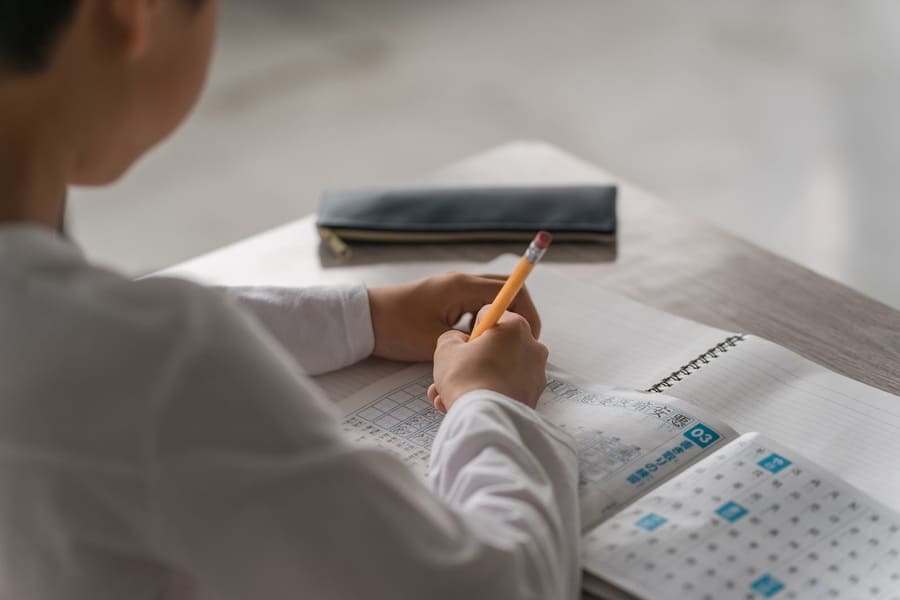
発達障がいのある子どもが学習に苦手意識を持ってしまう背景には、家庭でのサポートがうまく機能していないという事情があることも少なくありません。ここでは、保護者の方が日常で取り組める具体的な関わり方を3つご紹介します。
- 勉強に集中できる学習環境を整える
- 授業の内容を一つずつ定着させる
- 発達障がい向けの教育サポートを利用する
子どもが前向きに勉強に取り組めるよう、ぜひ取り入れてみてください。
1.勉強に集中できる学習環境を整える
発達障がいの有無に関わらず、集中できる環境づくりは学習のための前提と言えます。特にADHD傾向がある子どもは、周囲に刺激があると注意がそれやすいため、学習に適した静かで整った環境づくりが重要です。
たとえば、以下のような工夫を試してみてください。
- 机の上には必要なものだけを置く
- カラフルなものやおもちゃ類は視界に入らないようにする
- テレビやスマートフォンを遠ざけ、静かな場所で勉強する
こうした環境は、学習効率が上がるだけでなく、忘れ物や提出忘れなどのミスを減らす効果もあります。まずは環境を整えることから始めてみましょう。
2.授業の内容を一つずつ定着させる
学校では毎日さまざまな教科の授業が進んでいきます。しかし、ワーキングメモリが弱い子どもは情報の整理が難しく、内容を覚えるのに時間がかかることがあります。だからこそ、家庭では一つずつ・じっくり定着させる学習スタイルを意識しましょう。
たとえば以下のような工夫が効果的です。
- その日学校で習ったことを一つ選び、家で復習する
- ワークや問題集も、1ページずつ確実に理解しながら進める
- 覚えたことに対して「できたね」「昨日より進んだね」と声をかける
周りと比べてペースが遅くても、子ども自身が成果を実感することが自信になります。
トライのオンライン個別指導塾では、発達障がいの特性、ご家庭の要望を聞き取った上で、お子さまの夢や目標を実現するために最適な教師の紹介が可能です。
教師はもちろん、学習カリキュラムの作成や進路相談に対応する教育プランナーも専任制のため、継続的なサポートでお子さまを成績アップや志望校合格へと導きます。
\家庭教師のトライについて詳しくみる!/
3.発達障がい向けの教育サポートを利用する
家庭でのサポートはとても大切ですが、すべてを親だけで担おうとすると、負担が大きすぎることもあります。
子どもの特性に合った関わり方を1から10まで調べて試すのは、時間も労力もかかる上、時には不安になることもあるでしょう。
そんな時は、発達障がいに詳しい教育サポートの活用がおすすめです。たとえば、通級指導教室や発達支援に特化した塾、家庭教師を利用することで、以下のメリットが得られます。
- 子どもに合った学習方法や声かけの工夫を専門家から聞くことができる
- 一人ひとりの特性に適した学習指導を受けることができる
- 発達障がいに関する不安を相談することができる
親だけで抱え込まず、積極的にサポートを利用しましょう。
家庭教師のトライでは発達障がいに詳しい正社員の教育プランナーがお子さまにぴったりのサポート方法を提案
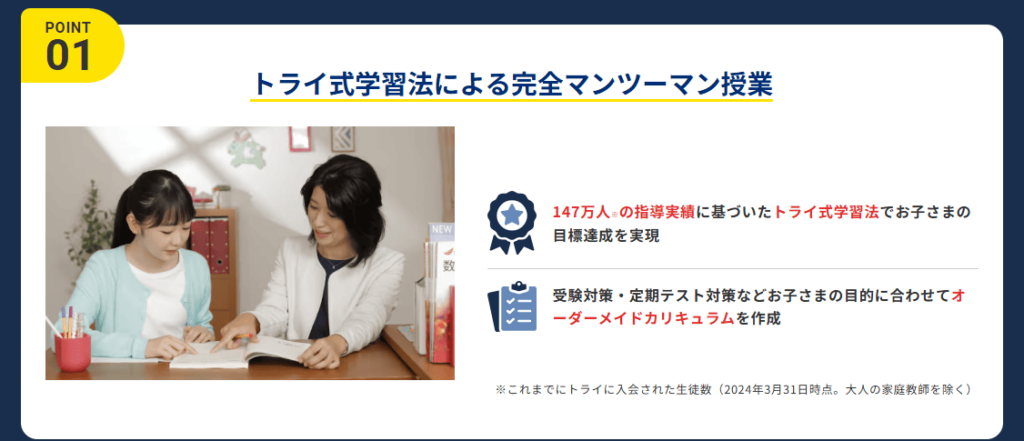
参照:家庭教師のトライ – 満足度No.1約33万人教師からあなたに最適な家庭教師をご紹介
家庭教師のトライには、発達障がいに理解の深い正社員の教育プランナーが在籍。お子さまの性格や特性を踏まえて最適な学習方法や教師のご提案を行っています。
授業は完全マンツーマン指導のため、周囲に気を取られることなく、お子さまのペースに合わせた丁寧なサポートが可能です。
また、教師との連携を通じて保護者の悩みにも寄り添い、家庭と一体となった支援体制で、お子さまの学びを支えます。
まとめ

発達障がいのある子どもは、「勉強ができない」と思い込んでしまうことがあります。しかし実際には、それぞれの特性が学習に影響を与えていることが原因のため、適切なサポートがあれば無理なく学習を進められる場合もあります。
重要なポイントは以下の3つです。
- 特性に合わせた学び方を知る
- 家庭でできる工夫を取り入れる
- 必要に応じて専門的なサポートを活用する
何より大事なのは「この子にはこの子のやり方がある」ということを理解し、寄り添いながら支えていく姿勢です。子どもが前向きに勉強に取り組めるように、できることから少しずつ始めてみましょう。