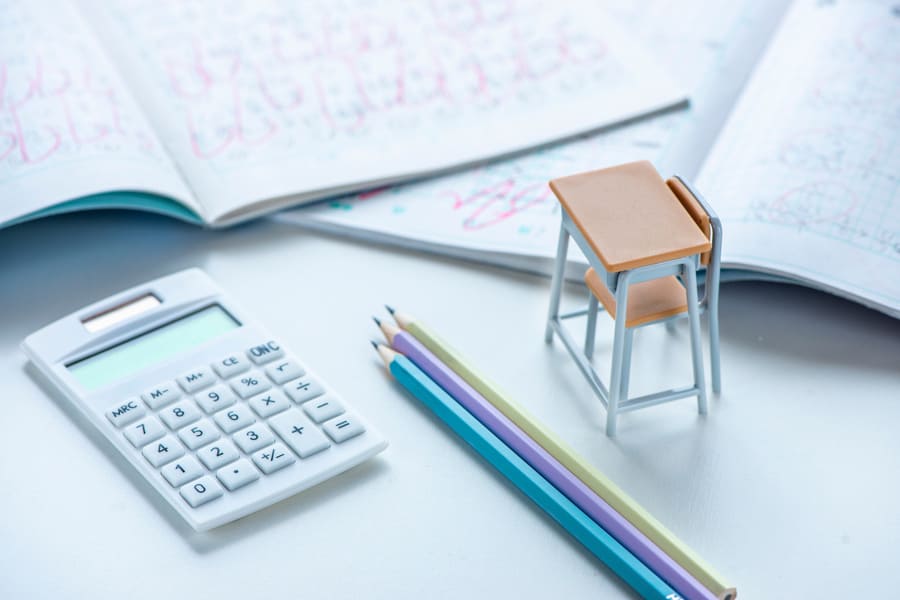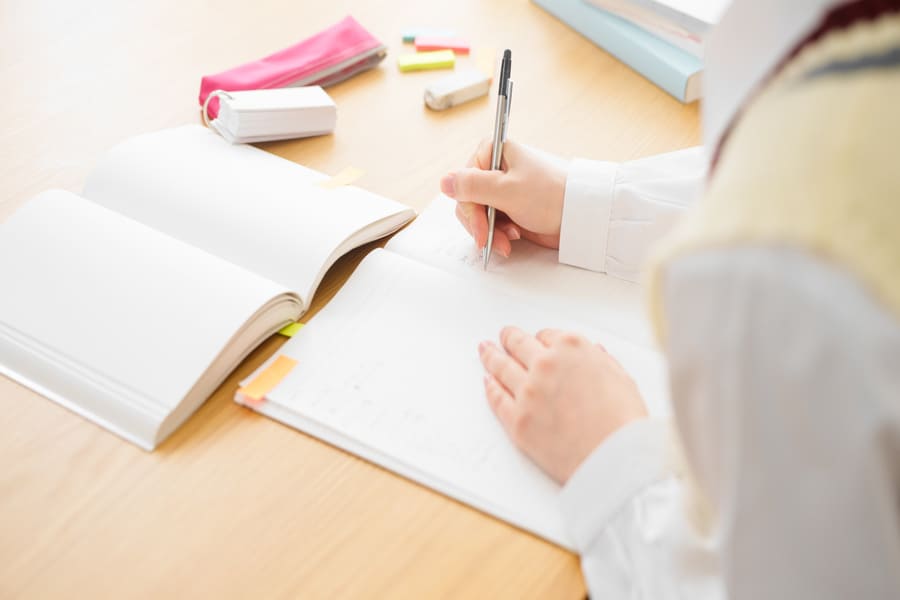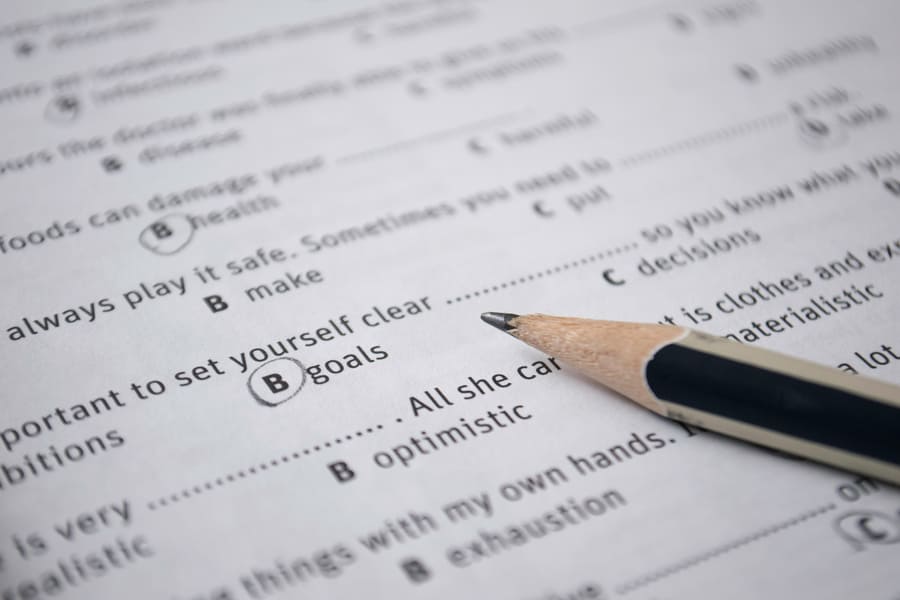「夏休み明けから学校に行きたがらない」
「2学期に入り、“登校しぶり”が目立ってきた」
「どう対応すればいいのかわからない」
こうした不安や戸惑いを感じている保護者様も多いのではないでしょうか。
実は、夏休み明けは不登校が増えやすい時期とされています。長期の休みで生活リズムが崩れるだけでなく、学校への不安やプレッシャーが強まることが主な理由です。
本記事では、次のポイントを中心に解説します。
- 夏休み明けに不登校が増える理由
- 子どもを安心させるための保護者の対応方法
- 不登校に関するよくある質問とその答え
保護者として何を意識すれば良いか、少しでもヒントを得られるよう、順を追って解説していきます。
トライのオンライン個別指導塾では、不登校のお子さまに向けて「不登校サポートコース」をご提供しています。自宅から無理なく指導を受けられるほか、お子さまのペースに合わせた幅広い学習のサポートが可能です。
「夏休み明けに不登校になった子どもをどのようにフォローしたらよいかわからない…」「無理なく学習を進められるようサポートする方法を知りたい」などとお悩みの保護者様は、トライのオンライン個別指導塾にお気軽にご相談ください。
\トライのオンライン個別指導塾について詳しくみる!/

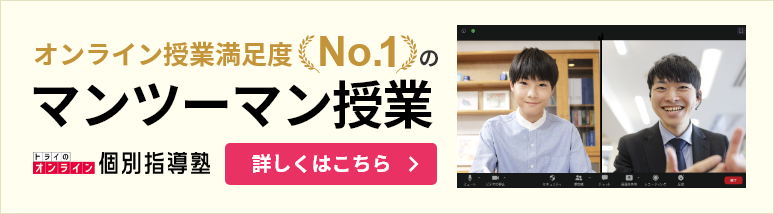
この記事の目次
夏休み明けは不登校が増えやすい時期!適切なサポートで少しずつ不安を取り除こう

夏休み明けは、学校への不安や生活の変化から、子どもが登校をためらいやすくなります。
文部科学省の調査によると、不登校になった時期として最も多かったのは9月で、小学生の約17.4%、中学生の約21.2%が9月に不登校になっています。これは1年間で最も高い割合です。
参照:令和5年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」文部科学省
夏休み明けの不登校は、長期休みの間に学校生活から離れていたことで、心身が学校生活のリズムに戻りづらくなっている状態とも考えられます。
また、1学期の嫌な思い出や、2学期からの新たな不安が重なり、登校のハードルが高くなってしまう場合もあります。
保護者として大切なのは、無理に登校を促すのではなく、子どもの気持ちに寄り添いながら、少しずつ不安を取り除くことだと言えるでしょう。
夏休み明けに不登校になりやすい主な理由

夏休み明けに不登校が増える背景には、子どもが抱えるさまざまな不安や心理的不安が関係しています。理由は一つではなく、いくつかの要因が複雑に絡み合っていることも少なくありません。
- 1学期に感じた心の負担を思い出してしまう
- 生活習慣が乱れて朝型のリズムを取り戻せない
- 2学期の学校生活についていける自信がない
特に多く見られる上記3つの主な理由について解説します。
1.1学期に感じた心の負担を思い出してしまう
夏休み中は学校から離れて気持ちが落ち着いていたとしても、休みが終わりに近づくにつれて、1学期に感じたストレスや不安が再び頭をよぎることがあります。
学校に戻ることで、「また同じつらい思いをするのではないか」という不安が強まり、登校への意欲を失ってしまうのです。
子どもが学校生活で負担に感じやすいこと
子どもが学校生活で感じやすい負担の例として、以下が挙げられます。
- 友だちや先生との人間関係に疲れてしまった
- 授業中に当てられることが怖かった
- 集団生活が合わず緊張する場面が多かった
- 部活動のプレッシャーが強く感じられた
- 勉強の内容についていけず劣等感を抱えていた
夏休みで心身がいったん回復しても、再び同じ環境に戻ることに抵抗を感じてしまうのは自然な反応でしょう。
2.生活習慣が乱れて朝型のリズムを取り戻せない
夏休みは自由な時間が増える分、生活リズムが乱れやすい時期です。夜更かしや昼夜逆転の生活が習慣になってしまい、朝起きること自体がつらくなっている子どもも少なくありません。
数日で生活リズムを戻せる場合は、大きな問題にならないこともあります。しかし、元に戻すのが難しくなっていると、登校が心身の負担となり億劫になりかねません。
欠席が続くとさらに学校に行きづらくなり、気付けば長期の不登校になってしまうこともあります。
家庭教師のトライでは、勉強の遅れを取り戻せるよう、オーダーメイドのカリキュラムと完全マンツーマン授業で徹底サポート。教師のスケジュールに合わせて授業日程を柔軟に調整できるため、自分に合ったペースで徐々に学習習慣を戻していきたいお子さまにピッタリです。
無料学習相談も受け付けていますので、まずはお気軽にご相談ください。
\家庭教師のトライについて詳しくみる!/
3.2学期の学校生活についていける自信がない
2学期は勉強の難易度が一段と上がる時期です。運動会や文化祭などの大きな行事が控えている場合もあります。これらを踏まえ、夏休み明けに対して次のような不安を感じる子どももいるでしょう。
- 授業についていけないかもしれない
- 2学期に控えている行事が苦手
- 部活動の大会や発表会が重荷になっている
特に勉強に苦手意識がある子どもは、授業に追いつけないと劣等感を抱きやすくなります。「どうせ頑張っても無理」といった気持ちから、登校を避ける場合もあるのです。
夏休みの宿題・課題が終わっていないことが不登校の理由になることも
「宿題が終わっていない」「課題を忘れていた」といったことが引っかかり、不登校のきっかけになることもあります。先生に叱られることへの不安や、友達にからかわれることへの不安が大きくなり、教室に入りづらくなってしまうのです。
ただし、夏休みの宿題が終わらない理由は、単なる怠けではない場合もあります。
- 勉強への苦手意識が強く、手をつけられなかった
- メンタル面の疲れでやる気が起きなかった
- 家庭内でのストレスが影響して集中できなかった
背景にさまざまな事情が隠れている場合もあるため、「なぜやらなかったのか」と責めるのではなく、まずは気持ちを受け止めることが大切です。
不登校になった子どもを安心させる保護者の対応方法

不登校が続くと、保護者様も不安や焦りを抱きがちです。しかし、無理に登校を促そうとすると、子どもの不安やプレッシャーがさらに強まり、逆効果になることがあります。
まずは、今の子どもの状態を受け止めることから始めましょう。そのうえで、少しずつ気持ちを回復させられるよう、日々の関わり方を見直すことが大切です。
- 無理に登校させず見守る
- まずはエネルギーの回復に専念する
- 子どものペースで生活習慣を整える
- 学校と連携しながら少しずつ登校日数を増やす
- 家庭や学校以外の居場所をつくる
上記に沿って、家庭でできる具体的なサポート方法を紹介します。
無理に登校させず見守る
子どもが学校に行けなくなったとき、保護者として「いつ登校できるようになるのだろう」と焦る気持ちが出るのは当然のことです。しかし無理に登校を促すことは、子どもの気持ちを追い詰めることにもつながります。
また、「なぜ学校に行けないのか」と理由を追及しすぎるのは逆効果になります。自分でも理由がわからず、混乱している子どもも少なくないからです。
まずは今の状態を責めずに受け入れ、「あなたの味方だよ」と安心感を伝えることが大切です。
まずはエネルギーの回復に専念する
不登校になった子どもは、学校生活によって心身ともにエネルギーを消耗しているかもしれません。表面的には元気そうに見えても、内面では不安や疲れを抱えていることもあります。
まずは、学校のことは一旦脇に置き、子どもが安心して休める環境を整えてあげましょう。
- 食事や睡眠をしっかりとる
- 好きなことに取り組む時間を作る
- 外に出る気力がなければ、家の中でできることを一緒に探す
気持ちが落ち着いてくると、次第に外の世界に目を向ける余裕が生まれてきます。
子どものペースで生活習慣を整える
夏休み中に昼夜が逆転した子どもは、まず生活リズムを整えることから始めましょう。ただし、無理に戻そうとすると、かえって負担が大きくなってしまいます。
たとえば、朝はいつもより30分早く起きることから始めたり、夜寝る前にスマートフォンを置く時間を一緒に決めたりと、できることから少しずつ挑戦していきます。
子どもが「できた」と感じられる経験を少しずつ積み重ねることで、徐々に自信が戻ってきます。
学校と連携しながら少しずつ登校日数を増やす
子どもが登校に前向きになった時は、学校と連携しながら少しずつ登校の機会を増やしていきましょう。ただし、いきなり通常どおりの登校を目指す必要はありません。
- 午前中だけ登校する
- 保健室や別室で過ごす
- 放課後に先生と面談だけする
このように、段階的に取り組むことで、学校に対する心理的ハードルを下げることができます。
途中で再び行けなくなることがあっても、決して責めずに「よくがんばったね」と声をかけることが、安心感につながります。
トライのオンライン個別指導塾では正社員の教育プランナーが不登校に関するさまざまな悩みに対応

「どうやって学校と連携を取ればいいかわからない」
「家庭での対応だけでは限界を感じている」
不登校で悩む場合、外部の専門サポートを活用するのも一つの方法です。
トライのオンライン個別指導塾では、不登校のお子さま向けに「不登校サポートコース」を提供しています。
正社員の教育プランナーが一人ひとりの状況に応じた学習・進路の相談に対応し、無理なく学校生活を再スタートできるようサポートしています。
- 画面越しで自宅から安心して学べる
- 学習面だけでなく、心のケアや生活リズムについての相談も可能
- 少しずつ社会とのつながりを取り戻す第一歩としても活用できる
不登校でお悩みの保護者の方は、トライのオンライン個別指導塾をご検討ください。
家庭や学校以外の居場所をつくる
不登校が続くと、どうしても家庭と学校という限られた空間で過ごす時間が長くなりがちです。そのため、家庭や学校以外に安心して過ごせる「居場所」を持つことを意識しましょう。
活用できる場所は以下があげられます。
- 地域のフリースクールや支援団体
- 図書館や公共施設など、静かに過ごせる場所
- オンラインの子ども向けコミュニティや学習サポート
家以外で誰かと関わる経験があると、「自分はここにいても良い」と感じられるようになります。その安心感が、再び学校に向かう意欲を生むことにつながるでしょう。
トライ式高等学院は、「家庭教師のトライ」で培ってきた学習ノウハウにもとづき、学習から卒業までをサポートする通信制高校サポート校です。
「トライ式不登校解決サポート」では、生徒の事情や希望に合わせて不登校の解決をサポート。自宅でのカウンセリングや個別授業、通学のサポートを通して自分のペースで無理なく登校できます。
不登校からの大学進学を目指すお子さまや、新しい高校で居場所をつくりたいと考えている高校生は、トライ式高等学院をぜひご検討ください。
\トライ式高等学院について詳しくみる!/
夏休み明けの不登校に関するよくある質問

最後に、保護者様からよく寄せられる疑問について解説します。
- 不登校の理由の1位はなんですか?
- 不登校になる前のサインは?
正しく理解し、少しずつ気持ちに余裕を持って対応できるようにしましょう。
Q.不登校の理由の1位は何ですか?
文部科学省の調査によると、不登校の主な理由として最も多かったのは「無気力・不安など学校における本人の問題」です。具体的には、次のような項目が上位に挙げられています。
- 小学生:学校生活に対して「無気力」29.9%、「不安」22.6%
- 中学生:学校生活に対して「無気力」40.5%、「不安」21.4%
参照:令和5年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」文部科学省
上記のように「何か特別な理由があるから不登校になる」と考えるより、漠然とした不安や心のエネルギー不足によって登校が難しくなっている場合が多いと言えます。
そのため、子どもが不登校になったときに理由を問い詰めたり、明確な原因を無理に見つけようとしたりする必要はありません。まずは気持ちを回復させることを優先しましょう。
Q.不登校になる前のサインは?
不登校になる前には、いくつかの変化やサインが見られることがあります。
以下のような行動や様子が見られたときには、心の中に不安や疲れが溜まっている可能性があるため、さりげなく声をかけてみることが大切です。
- 学校の話題になると急に口数が減る
- 夏休みの宿題に手をつけようとしない
- 夜更かしが増え、朝起きる時間が遅くなっている
- 外に出たがらず、家にこもることが多い
- 友だちと連絡を取らなくなる
- 食欲が落ちたり、イライラしたりすることが増える
こうしたサインがあっても、子ども自身が「まさか自分が不登校になるとは思っていない」場合もあります。
「なんとなく行きたくない」「理由はわからないけど気が重い」といった漠然とした気持ちが積み重なり、結果的に登校が難しくなるケースも少なくありません。
保護者の方が違和感を覚えたときには、問い詰めるのではなく、まずは穏やかに話を聞く姿勢を大切にしましょう。
まとめ

夏休み明けは、不登校が始まりやすい時期です。1学期の負担や学校生活への不安、生活リズムの乱れなどが複合的に影響し、登校することが難しくなる子どもは少なくありません。
不登校が始まったときに大切なのは、無理に登校を促すのではなく、子どもの気持ちを受け止め、安心できる環境を作ることです。
今回ご紹介したポイントは以下のとおりです。
- 夏休み明けは心身のエネルギーが不足しやすく、不登校のきっかけになりやすい
- 不登校の理由は一つではなく、子ども自身もはっきり説明できないことが多い
- 保護者は焦らず、子どものペースを尊重して見守る
- 小さな成功体験や安心できる居場所づくりが、再登校への第一歩になる
- 必要に応じて学校や外部の支援も活用し、ひとりで抱え込まない
子どもにとって「今の自分のままでも受け入れてくれる」と感じられる家庭は、心の回復にとって何より大きな支えになります。子どもに寄り添いながら、一緒に歩んでいける関係を大切にしていきましょう。